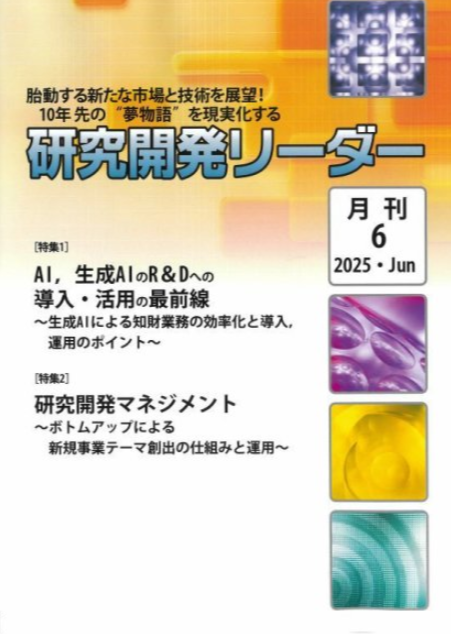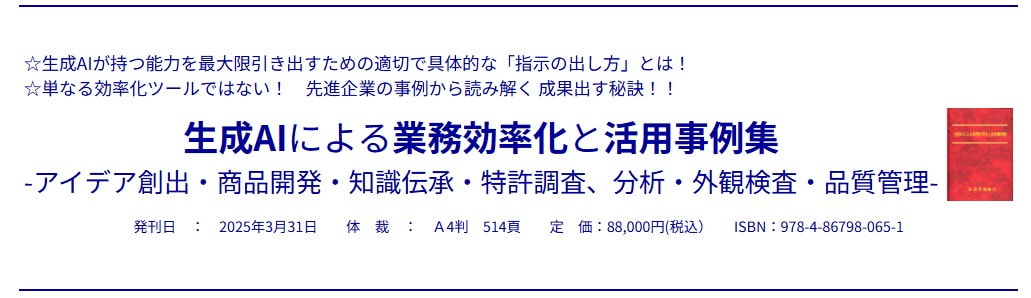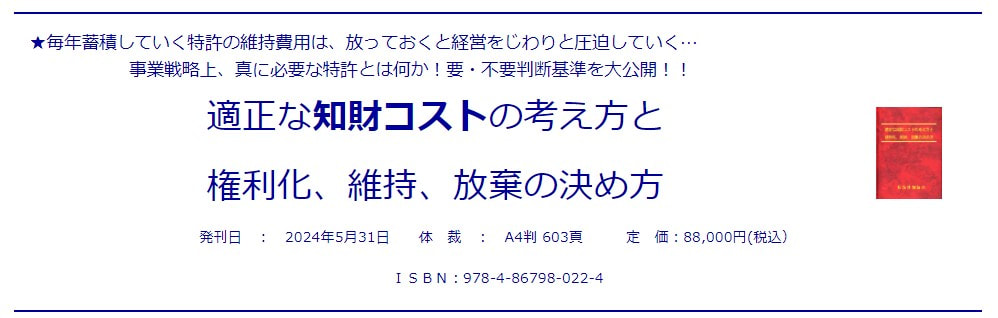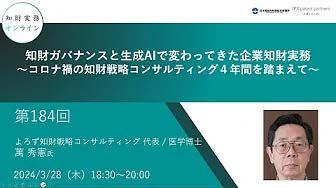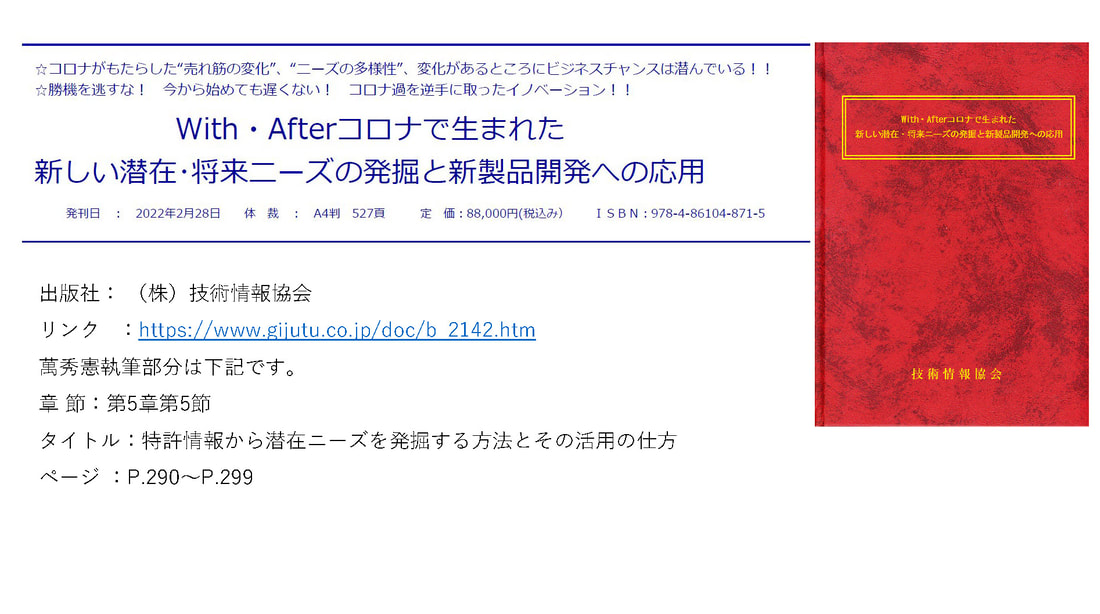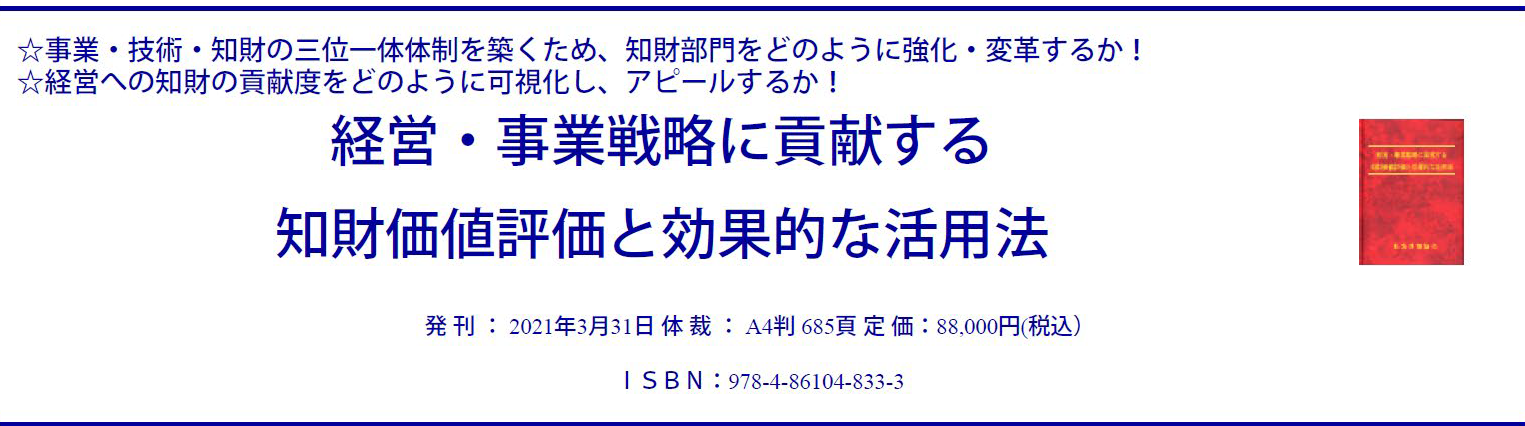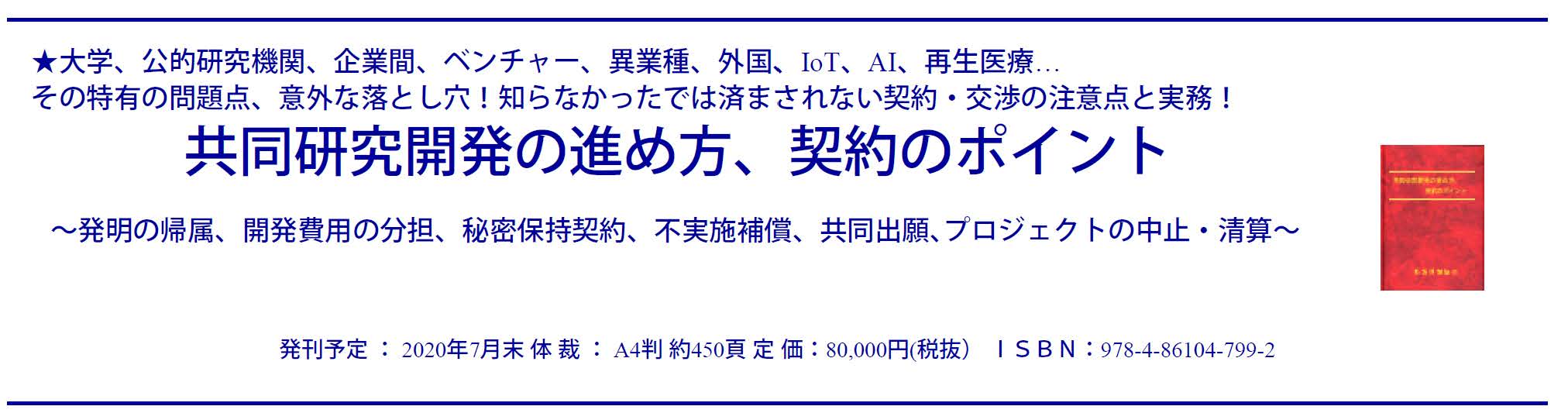これまでの経験を生かした知的財産活動全般のコンサルティング
一部上場企業2社での研究開発活動、知的財産活動で得た経験を次世代を担う方々に伝えたい、という想いから
コンサルティング活動を始めました。企業在職中から行ってきた各種セミナーの講師を継続しながら、コンサル
ティング業務や企業内セミナー等を行っています。
コンサルティング活動を始めました。企業在職中から行ってきた各種セミナーの講師を継続しながら、コンサル
ティング業務や企業内セミナー等を行っています。
2025年6月20日発刊の雑誌「研究開発リーダー」6月号の“《特集1》生成AIによる知財業務の効率化と導入,運用のポイント”に、「生成AIを活用した発明創出、発明提案書の書き方、特許明細書等チェックのコツ」(P.12~P.16)を執筆しました。 (株)技術情報協会 https://www.gijutu.co.jp/doc/magazine/R_2025_06.htm
2025年4月30日発刊の書籍「“知財DX”の導入と推進ポイント~知財調査・分析、特許評価、特許明細書の作成、翻訳、電子契約~」に、「生成AIを使った特許クリアランス調査」(第 4 章 第 9 節P.316~P.328)を執筆しました。
ISBN : 978-4-86798-070-5 出版社 : (株)技術情報協会
https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2292.htm
ISBN : 978-4-86798-070-5 出版社 : (株)技術情報協会
https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2292.htm
2025年3月31日発刊の書籍「生成AIによる業務効率化と活用事例集-アイデア創出・商品開発・知識伝承・特許調査、分析・外観検査・品質管理-」に、よろず知財戦略コンサルティング 代表 医学博士 萬 秀憲が執筆した「発明発掘・出願権利化/特許調査への生成 AI 活用」(第 8 章 第 3 節P.285~P.301)が掲載されています。 ISBN : 978‑4‑86798‑065‑1
出版社 : (株)技術情報協会
https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2285.htm
出版社 : (株)技術情報協会
https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2285.htm
Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document.
セミナーのご案内
萬秀憲が講師を務める外部セミナーのご案内です。
萬秀憲が講師を務める外部セミナーのご案内です。
1.【初めてからの】知財戦略の立案・策定法~考え方と検討事項・実施手順等~
●日時:2025年7月28日(月) 13:00-17:00
●受講料:
【オンライン受講(見逃し視聴なし)】:1名 46,200円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき35,200円
【オンライン受講(見逃し視聴あり)】:1名 51,700円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき40,700円株式会社
情報機構
https://johokiko.co.jp/seminar_chemical/AD2507N4.php
★講師紹介割引申込
講師の紹介ですと、受講料金が割引となります。
お申込みの際、備考欄に 講師紹介割引希望の旨と「Z-508」 の講師紹介専用番号を記載下さい。
割引額は通常受講料金(税別)より、1名ご参加の場合 \10,000円引き
2名以上参加の場合、通常の同時申込割引から更に1名につき¥2,000円引きとなります。
セミナー内容
1.知財戦略は、知的財産によって競争力を確保し、会社を伸ばすための戦略
(1)知財戦略とは?
(2)企業における知的財産活動の5つの発展段階に対応した知財戦略
レベル1:「ディフェンス」知財で事業を守る
レベル2:「コスト・コントロール」知財の管理費用を減らす
レベル3:「プロフィットセンター」知財で収益を上げる
レベル4:「インテグレーション」知財で企業を変える
レベル5:「ビジョン」知財で未来を創る
2.他者の知的財産権を侵害するリスク低減を中心にした知財戦略の立案・策定法
(1)他者の知的財産権を侵害するリスク低減を中心にした知財戦略立案・策定の基礎知識
(2)自社現状の確認方法
① 現在認識しているリスクへの対応は万全か?
② 現在認識していないリスクは存在していないか?
③ 現在の組織体制・運用に問題はないか?
(3)自社のあるべき姿の設定方法
(4)自社のあるべき姿を達成するためのシナリオの立案方法
(5)A社における知財戦略の事例研究
(6)B社における知財戦略の事例研究
3.特許出願・権利化戦略を中心にした研究開発型知財戦略の立案・策定法
(1)特許出願・権利化戦略を中心にした研究開発型知財戦略立案・策定の基礎知識
(2)自社現状の確認方法
① 自社技術の確実な保護ができているか?
② パテントポートフォリオをしっかり構築できているか?
③ 現在の組織体制・運用に問題はないか?
(3)自社のあるべき姿の設定方法
(4)自社のあるべき姿を達成するためのシナリオの立案方法
(5)C社における知財戦略の事例研究
(6)D社における知財戦略の事例研究
4.知的財産権の活用を中心にした事業貢献型知財戦略の立案・策定法
(1)知的財産権の活用を中心にした事業貢献型知財戦略立案・策定の基礎知識
① 自社の経営戦略・事業戦略・R&D戦略に沿った知財戦略の立案・策定
② 経営/事業部門/研究開発部門の課題の把握
③ 経営/事業部門/研究開発部門の課題解決への貢献の検討
④ 経営戦略/事業戦略/研究開発戦略を知財戦略への落としこみ
A)経営課題、事業課題、研究開発の課題と知財課題の位置付け
B)事業戦略のサイクルと知財サイクル(創造・保護・活用)の同期
C)事業をサポートする適切なパテントポートフォリオの構築
D)知的財産の活用(単独利用、ライセンス、事業提携)
E)障害他社特許対策(無効化、回避、断念、強行突破、交渉による解決)
(2)自社現状の確認方法
(3)自社のあるべき姿の設定方法
(4)自社のあるべき姿を達成するためのシナリオの立案方法
(5)E社における知財戦略の事例研究
(6)F社における知財戦略の事例研究
5.知財・無形資産への投資を中心にした未来創造型知財戦略
(1)知財・無形資産への投資を中心にした事業貢献型知財戦略立案・策定の基礎知識
① 2021年のコーポレートガバナンス・コード改訂
② 2023年の知財・無形資産ガバナンスガイドラインVer2.0
③ IPランドスケープ
(2)自社現状の確認方法
(3)自社のあるべき姿の設定方法
(4)自社のあるべき姿を達成するためのシナリオの立案方法
(5)G社における知財戦略の事例研究
(6)H社における知財戦略の事例研究
6.経営層、事業部に知財活動の貢献を認められる知財戦略推進組織の作り方
(1)知的財産活動による経営への貢献の考え方
(2)知的財産に積極的に取組む風土、組織・仕組み作り
(3)特許否定論への対応
(4)教育・啓蒙
(5)社内体制の構築
<質疑応答>
●日時:2025年7月28日(月) 13:00-17:00
●受講料:
【オンライン受講(見逃し視聴なし)】:1名 46,200円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき35,200円
【オンライン受講(見逃し視聴あり)】:1名 51,700円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき40,700円株式会社
情報機構
https://johokiko.co.jp/seminar_chemical/AD2507N4.php
★講師紹介割引申込
講師の紹介ですと、受講料金が割引となります。
お申込みの際、備考欄に 講師紹介割引希望の旨と「Z-508」 の講師紹介専用番号を記載下さい。
割引額は通常受講料金(税別)より、1名ご参加の場合 \10,000円引き
2名以上参加の場合、通常の同時申込割引から更に1名につき¥2,000円引きとなります。
セミナー内容
1.知財戦略は、知的財産によって競争力を確保し、会社を伸ばすための戦略
(1)知財戦略とは?
(2)企業における知的財産活動の5つの発展段階に対応した知財戦略
レベル1:「ディフェンス」知財で事業を守る
レベル2:「コスト・コントロール」知財の管理費用を減らす
レベル3:「プロフィットセンター」知財で収益を上げる
レベル4:「インテグレーション」知財で企業を変える
レベル5:「ビジョン」知財で未来を創る
2.他者の知的財産権を侵害するリスク低減を中心にした知財戦略の立案・策定法
(1)他者の知的財産権を侵害するリスク低減を中心にした知財戦略立案・策定の基礎知識
(2)自社現状の確認方法
① 現在認識しているリスクへの対応は万全か?
② 現在認識していないリスクは存在していないか?
③ 現在の組織体制・運用に問題はないか?
(3)自社のあるべき姿の設定方法
(4)自社のあるべき姿を達成するためのシナリオの立案方法
(5)A社における知財戦略の事例研究
(6)B社における知財戦略の事例研究
3.特許出願・権利化戦略を中心にした研究開発型知財戦略の立案・策定法
(1)特許出願・権利化戦略を中心にした研究開発型知財戦略立案・策定の基礎知識
(2)自社現状の確認方法
① 自社技術の確実な保護ができているか?
② パテントポートフォリオをしっかり構築できているか?
③ 現在の組織体制・運用に問題はないか?
(3)自社のあるべき姿の設定方法
(4)自社のあるべき姿を達成するためのシナリオの立案方法
(5)C社における知財戦略の事例研究
(6)D社における知財戦略の事例研究
4.知的財産権の活用を中心にした事業貢献型知財戦略の立案・策定法
(1)知的財産権の活用を中心にした事業貢献型知財戦略立案・策定の基礎知識
① 自社の経営戦略・事業戦略・R&D戦略に沿った知財戦略の立案・策定
② 経営/事業部門/研究開発部門の課題の把握
③ 経営/事業部門/研究開発部門の課題解決への貢献の検討
④ 経営戦略/事業戦略/研究開発戦略を知財戦略への落としこみ
A)経営課題、事業課題、研究開発の課題と知財課題の位置付け
B)事業戦略のサイクルと知財サイクル(創造・保護・活用)の同期
C)事業をサポートする適切なパテントポートフォリオの構築
D)知的財産の活用(単独利用、ライセンス、事業提携)
E)障害他社特許対策(無効化、回避、断念、強行突破、交渉による解決)
(2)自社現状の確認方法
(3)自社のあるべき姿の設定方法
(4)自社のあるべき姿を達成するためのシナリオの立案方法
(5)E社における知財戦略の事例研究
(6)F社における知財戦略の事例研究
5.知財・無形資産への投資を中心にした未来創造型知財戦略
(1)知財・無形資産への投資を中心にした事業貢献型知財戦略立案・策定の基礎知識
① 2021年のコーポレートガバナンス・コード改訂
② 2023年の知財・無形資産ガバナンスガイドラインVer2.0
③ IPランドスケープ
(2)自社現状の確認方法
(3)自社のあるべき姿の設定方法
(4)自社のあるべき姿を達成するためのシナリオの立案方法
(5)G社における知財戦略の事例研究
(6)H社における知財戦略の事例研究
6.経営層、事業部に知財活動の貢献を認められる知財戦略推進組織の作り方
(1)知的財産活動による経営への貢献の考え方
(2)知的財産に積極的に取組む風土、組織・仕組み作り
(3)特許否定論への対応
(4)教育・啓蒙
(5)社内体制の構築
<質疑応答>
2.=生成AI活用を追加=【期間限定】よろず先生の本当に役立つ知財講座 技術者コース(全5講座)
https://www.tech-d.jp/seminar/show/7937
【視聴期間】申込完了翌々営業日~2025年8月31日
【申込〆切日】2025年8月1日
【配信内容】オンデマンド(2024/10~2025/5/4に開催したセミナーの動画となります)
※視聴期間中は、いつでも何度でも視聴することができます
通常価格(全5講座1アカウント): 99,000円 (消費税込)
複数割引価格(全5講座1アカウント): 49,500円 (消費税込) ※2アカウント以上でお申込みの場合
1受講割引価格(全5講座1アカウント): 79,200円 (消費税込) ※5講座の中に受講した講座が1講座ある場合
2受講割引価格(全5講座1アカウント): 59,400円 (消費税込) ※5講座の中に受講した講座が2講座ある場合
3受講割引価格(全5講座1アカウント) : 49,500円 (消費税込) ※5講座の中に受講した講座が3講座以上ある場合
再受講割引価格(全5講座1アカウント): 49,500円 (消費税込) ※技術者コースを過去に受講した場合
https://www.tech-d.jp/seminar/show/7937
【視聴期間】申込完了翌々営業日~2025年8月31日
【申込〆切日】2025年8月1日
【配信内容】オンデマンド(2024/10~2025/5/4に開催したセミナーの動画となります)
※視聴期間中は、いつでも何度でも視聴することができます
通常価格(全5講座1アカウント): 99,000円 (消費税込)
複数割引価格(全5講座1アカウント): 49,500円 (消費税込) ※2アカウント以上でお申込みの場合
1受講割引価格(全5講座1アカウント): 79,200円 (消費税込) ※5講座の中に受講した講座が1講座ある場合
2受講割引価格(全5講座1アカウント): 59,400円 (消費税込) ※5講座の中に受講した講座が2講座ある場合
3受講割引価格(全5講座1アカウント) : 49,500円 (消費税込) ※5講座の中に受講した講座が3講座以上ある場合
再受講割引価格(全5講座1アカウント): 49,500円 (消費税込) ※技術者コースを過去に受講した場合
Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document.
3.特許調査への生成AIの活用~特許クリアランス調査を中心に~
【Live配信 or アーカイブ配信】
★調査時間の大幅な短縮!調査の精度!網羅性の向上を実現するために!
★データ収集と整形、具体的なプロンプトの設計など実施上のポイントと注意点!
技術情報協会
https://www.gijutu.co.jp/doc/s_509502.htm
■ 講師 よろず知財戦略コンサルティング 代表 萬 秀憲氏
■ 開催要領
日 時:【Live配信】2025年9月4日(木) 10:30~16:30
【アーカイブ(録画)配信】 2025年7月3日まで受付(視聴期間:9月16日~9月26日まで)
会 場:Zoomを利用したLive配信 または アーカイブ配信 ※会場での講義は行いません
セミナーの接続確認・受講手順は「こちら」をご確認下さい。
聴講料:1名につき 55,000円(消費税込、資料付)
〔1社2名以上同時申込の場合のみ1名につき49,500円〕
講師割引あり
■ プログラム
【講座の趣旨】
生成AIの飛躍的な進化により、従来のAIでは不可能だった高度な知的作業も実現可能となってきまし た。特許調査の分野でも、年間数千件規模のクリアランス調査に生成AIを導入する企業が現れ、実務への活用が加速 しています。生成AIは調査時間の大幅な短縮に加え、調査の精度や網羅性の向上にも寄与すると報告されており、そ の活用可否が企業の競争力を左右する時代が到来しつつあります。本講演では、生成AIの基礎から最新動向、特許調 査への応用と今後の展望までを俯瞰的に解説します。
【講座内容】
1.生成AI進化の概要とその可能性
1.1 生成AIとは?
1.2 生成AI進化の概要
1.3 生成AIが有効な領域とその可能性
2.技術動向調査への生成AIの活用
2.1 生成AI特許情報分析GPT
2.2 Deep Researchの活用
3.特許出願前先行技術調査への生成AIの活用
3.1 特許検索式作成GPT
3.2 生成AI先行技術調査GPT
4.特許クリアランス調査への生成AIの活用
4.1 特許クリアランス調査の基礎
(1)特許クリアランスの概念
(2)特許クリアランスが必要となる場面
(3)従来の特許クリアランス調査の課題
(4)クレームの意義と重要性
4.2 生成AIを用いた特許クリアランス調査の手法
(1)データの収集と整形
(2)検索クエリ生成と検索
(3)特許リストのフィルタリングと分類
(4)クレームチャートの自動生成・サマライズ
4.3 実運用におけるワークフロー例
(1)ワークフローの全体像
(2)第1段階:特許文献の抽出
(3)第2段階:侵害可能性評価
(4)まとめ:2段階比較による全体像
4.4 AIモデル選択と運用上のポイント
(1)AIモデル選択と学習
(2)実施上のポイントと注意点
(3)チーム構成・役割分担
4.5 生成AI活用におけるリスクと課題
(1)正確性・信頼性の問題
(2)プロンプト依存性とバイアス
(3)法的責任と知財リスク
(4)データプライバシーとセキュリティ
4.6 実際の利用例
(1)特許検索式作成
(2)特許検索
(3)特許検索
5.おわりに
【質疑応答】
【Live配信 or アーカイブ配信】
★調査時間の大幅な短縮!調査の精度!網羅性の向上を実現するために!
★データ収集と整形、具体的なプロンプトの設計など実施上のポイントと注意点!
技術情報協会
https://www.gijutu.co.jp/doc/s_509502.htm
■ 講師 よろず知財戦略コンサルティング 代表 萬 秀憲氏
■ 開催要領
日 時:【Live配信】2025年9月4日(木) 10:30~16:30
【アーカイブ(録画)配信】 2025年7月3日まで受付(視聴期間:9月16日~9月26日まで)
会 場:Zoomを利用したLive配信 または アーカイブ配信 ※会場での講義は行いません
セミナーの接続確認・受講手順は「こちら」をご確認下さい。
聴講料:1名につき 55,000円(消費税込、資料付)
〔1社2名以上同時申込の場合のみ1名につき49,500円〕
講師割引あり
■ プログラム
【講座の趣旨】
生成AIの飛躍的な進化により、従来のAIでは不可能だった高度な知的作業も実現可能となってきまし た。特許調査の分野でも、年間数千件規模のクリアランス調査に生成AIを導入する企業が現れ、実務への活用が加速 しています。生成AIは調査時間の大幅な短縮に加え、調査の精度や網羅性の向上にも寄与すると報告されており、そ の活用可否が企業の競争力を左右する時代が到来しつつあります。本講演では、生成AIの基礎から最新動向、特許調 査への応用と今後の展望までを俯瞰的に解説します。
【講座内容】
1.生成AI進化の概要とその可能性
1.1 生成AIとは?
1.2 生成AI進化の概要
1.3 生成AIが有効な領域とその可能性
2.技術動向調査への生成AIの活用
2.1 生成AI特許情報分析GPT
2.2 Deep Researchの活用
3.特許出願前先行技術調査への生成AIの活用
3.1 特許検索式作成GPT
3.2 生成AI先行技術調査GPT
4.特許クリアランス調査への生成AIの活用
4.1 特許クリアランス調査の基礎
(1)特許クリアランスの概念
(2)特許クリアランスが必要となる場面
(3)従来の特許クリアランス調査の課題
(4)クレームの意義と重要性
4.2 生成AIを用いた特許クリアランス調査の手法
(1)データの収集と整形
(2)検索クエリ生成と検索
(3)特許リストのフィルタリングと分類
(4)クレームチャートの自動生成・サマライズ
4.3 実運用におけるワークフロー例
(1)ワークフローの全体像
(2)第1段階:特許文献の抽出
(3)第2段階:侵害可能性評価
(4)まとめ:2段階比較による全体像
4.4 AIモデル選択と運用上のポイント
(1)AIモデル選択と学習
(2)実施上のポイントと注意点
(3)チーム構成・役割分担
4.5 生成AI活用におけるリスクと課題
(1)正確性・信頼性の問題
(2)プロンプト依存性とバイアス
(3)法的責任と知財リスク
(4)データプライバシーとセキュリティ
4.6 実際の利用例
(1)特許検索式作成
(2)特許検索
(3)特許検索
5.おわりに
【質疑応答】
Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document.
視点や質問のコツ等の発明発掘ノウハウ、発明発掘が上手くいかない阻害要因の克服法、更には発明発掘業務の組織化・体制づくりまで、講師の十数年にわたるトライ&エラーの経験および成功事例を踏まえて解説。生成AI活用も紹介。
4.特許出願の数と質の向上につながる発明発掘ノウハウ
https://www.tech-d.jp/seminar/show/7831
形式オンラインセミナー(Live配信)
日程/時間2025年 9月 18日(木) 13:30~16:30
配信について見逃し配信あり(視聴期間は10日程度)
当日の受講が難しい場合は見逃し配信をご利用ください。
資料(テキスト)PDFデータのダウンロード
受講料
(申込プラン)通常価格: 24,200円 (消費税込)
●詳細
1.良い発明とは?
1)発明
2)特許される発明
3)質の高い発明
4)良い発明
2.質の高い発明を発掘する方法
1)技術開発を行っていれば必ず発明は生まれている
2)発明者がなぜ自らの発明に気づかないのか?
3)発明発掘を阻害している要因とその克服法
・新規性、進歩性についての誤った考え方
・自社だけに通用する「技術用語」
・採用されなかった技術には見向きもしない
・自社の製品・製造方法・設備に縛られる
・発明者が先行技術をよく知らない
・発明者が開発者目線でしか技術を見ていない
・発明者がユーザー視点で技術をみていない
4)発明発掘のノウハウ
・発明は「課題」「作用効果」「構成」がセット
・構成の微差があれば、「課題」「作用効果」の違いが重要
・上位概念化と下位概念化
・発明は陣取り合戦
・発明の発掘は、実は発明の創造
5)急速に進化し第3ステージに入った生成AI(=AIエージェント)の発明発掘への活用
・生成AIの発明発掘への上手な使い方
・生成AIによる発明提案書の作成
3.開発業務に直結した、事業に直結した戦略的な発明発掘活動
1)事業に直結する
2)開発業務に直結する
3)組織体制
4)活動内容
<習得知識>
・知財部員やリエゾンマンが「こう考えれば良かったのか」と発明の発掘の仕方が習得できます。
・特許出願の数を大幅に増加させ、特許の質を大幅に向上させるためのヒントが得られます。
・発明の発掘を上手く行うための発明発掘業務の組織化、体制づくりのノウハウを修得できます。
・開発業務に直結した、事業に直結した、戦略的な特許発掘活動のヒントが得られます。
<講義概要>
多くの「発明」が通常の業務の中に潜んでいます。その「発明」に気づくには、知っているようで実は理解できてないことがあります。
本講習会では、「発明」に気付き、活用することができるように、まず、質の高い良い「発明」とは何かということを学びます。次に、どうして発明の発掘が上手くいかないのか、発明の発掘を阻害している要因を明らかにし、その克服法を説明します。そのうえで、発明発掘のノウハウを具体的に説明します。いずれも、講師の実務経験を踏まえた事例を交えます。
発明の発掘が上手くできていないと感じている知財部員やリエゾンマンが「こう考えれば良かったのか」と発明の発掘の仕方が理解でき、特許出願の数を大幅に増加させ、特許の質を大幅に向上させるためのヒントが得られます。
また、開発の初期段階から生産に至るまでの各ステップで、どのような組織体制でどのような活動をすべきか、技術者が製品開発に伴って日々の特許関連業務をいかに行うべきかを説明します。
更に、生成AIの発明発掘への活用、生成AIによる発明提案書の作成法について説明します。
4.特許出願の数と質の向上につながる発明発掘ノウハウ
https://www.tech-d.jp/seminar/show/7831
形式オンラインセミナー(Live配信)
日程/時間2025年 9月 18日(木) 13:30~16:30
配信について見逃し配信あり(視聴期間は10日程度)
当日の受講が難しい場合は見逃し配信をご利用ください。
資料(テキスト)PDFデータのダウンロード
受講料
(申込プラン)通常価格: 24,200円 (消費税込)
●詳細
1.良い発明とは?
1)発明
2)特許される発明
3)質の高い発明
4)良い発明
2.質の高い発明を発掘する方法
1)技術開発を行っていれば必ず発明は生まれている
2)発明者がなぜ自らの発明に気づかないのか?
3)発明発掘を阻害している要因とその克服法
・新規性、進歩性についての誤った考え方
・自社だけに通用する「技術用語」
・採用されなかった技術には見向きもしない
・自社の製品・製造方法・設備に縛られる
・発明者が先行技術をよく知らない
・発明者が開発者目線でしか技術を見ていない
・発明者がユーザー視点で技術をみていない
4)発明発掘のノウハウ
・発明は「課題」「作用効果」「構成」がセット
・構成の微差があれば、「課題」「作用効果」の違いが重要
・上位概念化と下位概念化
・発明は陣取り合戦
・発明の発掘は、実は発明の創造
5)急速に進化し第3ステージに入った生成AI(=AIエージェント)の発明発掘への活用
・生成AIの発明発掘への上手な使い方
・生成AIによる発明提案書の作成
3.開発業務に直結した、事業に直結した戦略的な発明発掘活動
1)事業に直結する
2)開発業務に直結する
3)組織体制
4)活動内容
<習得知識>
・知財部員やリエゾンマンが「こう考えれば良かったのか」と発明の発掘の仕方が習得できます。
・特許出願の数を大幅に増加させ、特許の質を大幅に向上させるためのヒントが得られます。
・発明の発掘を上手く行うための発明発掘業務の組織化、体制づくりのノウハウを修得できます。
・開発業務に直結した、事業に直結した、戦略的な特許発掘活動のヒントが得られます。
<講義概要>
多くの「発明」が通常の業務の中に潜んでいます。その「発明」に気づくには、知っているようで実は理解できてないことがあります。
本講習会では、「発明」に気付き、活用することができるように、まず、質の高い良い「発明」とは何かということを学びます。次に、どうして発明の発掘が上手くいかないのか、発明の発掘を阻害している要因を明らかにし、その克服法を説明します。そのうえで、発明発掘のノウハウを具体的に説明します。いずれも、講師の実務経験を踏まえた事例を交えます。
発明の発掘が上手くできていないと感じている知財部員やリエゾンマンが「こう考えれば良かったのか」と発明の発掘の仕方が理解でき、特許出願の数を大幅に増加させ、特許の質を大幅に向上させるためのヒントが得られます。
また、開発の初期段階から生産に至るまでの各ステップで、どのような組織体制でどのような活動をすべきか、技術者が製品開発に伴って日々の特許関連業務をいかに行うべきかを説明します。
更に、生成AIの発明発掘への活用、生成AIによる発明提案書の作成法について説明します。
Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document.
5.賢くなった生成AIによる特許調査・権利化・知財業務の高度化【LIVE配信】
~特許調査・権利化・知財業務によるAIの有用な活用法からそのリスクや対応策まで!~
2025年09月25日(木) 13:00~17:00
R&D支援センター
https://www.rdsc.co.jp/seminar/250978
※生成AIについて最新のモデルが発表された場合は、できるだけそれについてもフォローして内容に組み込みます※オンライン会議アプリZoomを使ったWEBセミナーです。ご自宅や職場のノートPCで受講できます。
【アーカイブ配信:9/26~10/6】の視聴を希望される方は、《こちら》からお申し込み下さい。
開催日時
2025年09月25日(木) 13:00~17:00
主催
(株)R&D支援センター
問い合わせ
Tel:03-5857-4811 E-mail:info@rdsc.co.jp 問い合わせフォーム
開催場所
【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
講師
よろず知財戦略コンサルティング 代表 医学博士 萬 秀憲 氏
価格
非会員: 49,500円 (本体価格:45,000円)
会員: 44,000円 (本体価格:40,000円)
学生: 49,500円 (本体価格:45,000円)
価格関連備考
会員(案内)登録していただいた場合、通常1名様申込で49,500円(税込)から
・1名で申込の場合、44,000円(税込)へ割引になります。
・2名同時申込で両名とも会員登録をしていただいた場合、計49,500円(2人目無料)です。
・3名以上での申込は1名につき24,750円
持参物
受講にはWindowsPCを推奨しております。
タブレットやスマートフォンでも受講可能ですが、機能が制限される場合があります。
備考
資料付
・セミナー資料は開催前日までにお送りいたします。
無断転載、二次利用や講義の録音、録画などの行為を固く禁じます。
講座の内容
習得できる知識
・「レベル3」に進化した生成AIの基本から活用の現状までを把握できます。
・特許調査業務における生成AIの活用法がわかります。
・特許出願・権利化業務における生成AIの活用法がわかります。
・知財戦略策定等の知財業務における生成AIの活用法がわかります。
・生成Al を巡る主なリスクと対応について理解できます。
趣旨
生成AIは、2022年に「レベル1(雑談AI)」で登場してから、2024年秋には「レベル2(博士号並みAI)」、2025年春には「レベル3(AIエージェント)」に急速に進化、ChatGPT一強からClaude, Geminiなど競合もChatGPTを凌ぐ性能を備えるようになり、企業での業務活用も急速に普及、あらゆる領域に大きなインパクトを与え続けています。
この進化で、知財業務での活用についても、「レベル1(雑談AI)」ではできなかった業務ができるようになったり、初心者レベルの対応しかできなかったのが中級者レベルの対応ができるようになってきており、FTO調査を全件生成AIで行う会社も出てきているなど、各社での知財業務への活用も進んできています。また、生成AIを組み込んだ知財ツールも次々と提案されてきています。
生成AIとはどういうものか、その概要、最新生成AIによってできるようになったこと、まだできないことを確認し、知財業務への生成AI活用法について、実際に使用した例を示しながら解説します。
さらに、生成AIを使用するにあたって注意しなければいけない主なリスクと対応方法についても解説します。
プログラム1.生成AIの活用に関して最近寄せられた質問から
1-1. AIを使用するにあたっての課題
1-2.プロンプト作成スキル・AIリテラシーに関する課題
1-3.回答の品質・信頼性・安定性に関する課題
1-4.セキュリティ・情報管理に関する課題
1-5.業務活用・個人利用における課題
1-6.組織としての運用・導入プロセスに関する課題
1-7.AIを使用した業務とその評価
2、群雄割拠の時代の生成AIの基本と活用について
2-1.大規模言語モデル(LLM)の急速な発展
2-2.OpenAI最新モデル
2-3.GoogleGemini最新モデ
2-4.AnthropicClude最新モデル
2-5.Deep Research
2-6.現段階での生成AIの賢い使い方
3.特許調査/分析業務における生成AI活用法について
3-1.検索式作成支援
3-2.SDI支援(AI自動分類)
3-3.分類作成支援
3-4.技術動向調査支援
3-5.特許の読み込み支援
4.特許出願・権利化業務における生成AI活用法について
4-1.発明発掘支援
4-2.発明提案書作成支援
4-3.特許明細書作成支援
4-4.拒絶理由通知の分析支援
4-5.拒絶理由通知の対応作成支援
4-6.発明評価支援
5.知財戦略策定等の業務における生成AI活用法について
5-1.知財戦略立案支援
5-2.権利活用支援
5-3.IPランドスケープ支援
5-4.知財教育支援
5-5.外国出願(翻訳)支援
5-6.知財契約書作成支援
6.生成Alを巡る主なリスクと対応、取り巻く環境
6-1.AI時代の知的財産権検討会
6-2.AI戦略会議
6-3.知的財産推進計画2024
6-4.「AI事業者ガイドライン」
6-5.欧州「AI 規則
6-6.行政の進化と革新のための生成 AI の調達・利活用に係るガイドライン
6-7.人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律
6-8.知的財産推進計画2025
~特許調査・権利化・知財業務によるAIの有用な活用法からそのリスクや対応策まで!~
2025年09月25日(木) 13:00~17:00
R&D支援センター
https://www.rdsc.co.jp/seminar/250978
※生成AIについて最新のモデルが発表された場合は、できるだけそれについてもフォローして内容に組み込みます※オンライン会議アプリZoomを使ったWEBセミナーです。ご自宅や職場のノートPCで受講できます。
【アーカイブ配信:9/26~10/6】の視聴を希望される方は、《こちら》からお申し込み下さい。
開催日時
2025年09月25日(木) 13:00~17:00
主催
(株)R&D支援センター
問い合わせ
Tel:03-5857-4811 E-mail:info@rdsc.co.jp 問い合わせフォーム
開催場所
【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
講師
よろず知財戦略コンサルティング 代表 医学博士 萬 秀憲 氏
価格
非会員: 49,500円 (本体価格:45,000円)
会員: 44,000円 (本体価格:40,000円)
学生: 49,500円 (本体価格:45,000円)
価格関連備考
会員(案内)登録していただいた場合、通常1名様申込で49,500円(税込)から
・1名で申込の場合、44,000円(税込)へ割引になります。
・2名同時申込で両名とも会員登録をしていただいた場合、計49,500円(2人目無料)です。
・3名以上での申込は1名につき24,750円
持参物
受講にはWindowsPCを推奨しております。
タブレットやスマートフォンでも受講可能ですが、機能が制限される場合があります。
備考
資料付
・セミナー資料は開催前日までにお送りいたします。
無断転載、二次利用や講義の録音、録画などの行為を固く禁じます。
講座の内容
習得できる知識
・「レベル3」に進化した生成AIの基本から活用の現状までを把握できます。
・特許調査業務における生成AIの活用法がわかります。
・特許出願・権利化業務における生成AIの活用法がわかります。
・知財戦略策定等の知財業務における生成AIの活用法がわかります。
・生成Al を巡る主なリスクと対応について理解できます。
趣旨
生成AIは、2022年に「レベル1(雑談AI)」で登場してから、2024年秋には「レベル2(博士号並みAI)」、2025年春には「レベル3(AIエージェント)」に急速に進化、ChatGPT一強からClaude, Geminiなど競合もChatGPTを凌ぐ性能を備えるようになり、企業での業務活用も急速に普及、あらゆる領域に大きなインパクトを与え続けています。
この進化で、知財業務での活用についても、「レベル1(雑談AI)」ではできなかった業務ができるようになったり、初心者レベルの対応しかできなかったのが中級者レベルの対応ができるようになってきており、FTO調査を全件生成AIで行う会社も出てきているなど、各社での知財業務への活用も進んできています。また、生成AIを組み込んだ知財ツールも次々と提案されてきています。
生成AIとはどういうものか、その概要、最新生成AIによってできるようになったこと、まだできないことを確認し、知財業務への生成AI活用法について、実際に使用した例を示しながら解説します。
さらに、生成AIを使用するにあたって注意しなければいけない主なリスクと対応方法についても解説します。
プログラム1.生成AIの活用に関して最近寄せられた質問から
1-1. AIを使用するにあたっての課題
1-2.プロンプト作成スキル・AIリテラシーに関する課題
1-3.回答の品質・信頼性・安定性に関する課題
1-4.セキュリティ・情報管理に関する課題
1-5.業務活用・個人利用における課題
1-6.組織としての運用・導入プロセスに関する課題
1-7.AIを使用した業務とその評価
2、群雄割拠の時代の生成AIの基本と活用について
2-1.大規模言語モデル(LLM)の急速な発展
2-2.OpenAI最新モデル
2-3.GoogleGemini最新モデ
2-4.AnthropicClude最新モデル
2-5.Deep Research
2-6.現段階での生成AIの賢い使い方
3.特許調査/分析業務における生成AI活用法について
3-1.検索式作成支援
3-2.SDI支援(AI自動分類)
3-3.分類作成支援
3-4.技術動向調査支援
3-5.特許の読み込み支援
4.特許出願・権利化業務における生成AI活用法について
4-1.発明発掘支援
4-2.発明提案書作成支援
4-3.特許明細書作成支援
4-4.拒絶理由通知の分析支援
4-5.拒絶理由通知の対応作成支援
4-6.発明評価支援
5.知財戦略策定等の業務における生成AI活用法について
5-1.知財戦略立案支援
5-2.権利活用支援
5-3.IPランドスケープ支援
5-4.知財教育支援
5-5.外国出願(翻訳)支援
5-6.知財契約書作成支援
6.生成Alを巡る主なリスクと対応、取り巻く環境
6-1.AI時代の知的財産権検討会
6-2.AI戦略会議
6-3.知的財産推進計画2024
6-4.「AI事業者ガイドライン」
6-5.欧州「AI 規則
6-6.行政の進化と革新のための生成 AI の調達・利活用に係るガイドライン
6-7.人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律
6-8.知的財産推進計画2025
6.インフレ時代の "三位一体" 戦略統合 知財戦略・技術戦略・事業戦略の相互理解と具体策~戦略の分断/断片化を回避するために~
~部門間の橋渡しに役立つフレームワーク・実践法とは~
受講可能な形式:【Live配信(アーカイブ配信付)】のみ
── 継続的な物価上昇、インフレにより経営戦略の転換が迫られる今、 分断された戦略では勝ち残れない
サイエンス&テクノロジー
https://www.science-t.com/seminar/K251009.html
本セミナーでは、知財・技術・事業部門が互いの戦略と役割を理解し協働することにより、イノベーションの創出や事業競争力強化を実現するための進め方を実務目線で解説。実際の成功/失敗事例とともに、明日からの社内連携を変える“ヒント”と“フレームワーク”を提供します。「自部門の戦略が全体から乖離している、独り歩きしているのではないか?」と感じている方に是非お役立ていただきたい一講です。
日時2025年10月9日(木) 13:00~16:30
受講料(税込)
各種割引特典49,500円 ( E-Mail案内登録価格 46,970円 )
定価:本体45,000円+税4,500円
E-Mail案内登録価格:本体42,700円+税4,270円
E-Mail案内登録なら、2名同時申込みで1名分無料 1名分無料適用条件
2名で49,500円 (2名ともE-Mail案内登録必須/1名あたり定価半額の24,750円)
1名でのお申込みには、お申込みタイミングによって以下の2つ割引価格がございます
早期申込割引価格対象セミナー【1名受講限定】
8月31日までの1名申込み : 受講料 31,900円(E-mail案内登録価格 31,900円)
定価/E-mail案内登録価格ともに:本体29,000円+税2,900円
※1名様で開催月の2ヵ月前の月末までにお申込みの場合、上記特別価格になります。
※本ページからのお申込みに限り適用いたします。※他の割引は併用できません。
テレワーク応援キャンペーン(1名受講)【オンライン配信セミナー受講限定】
9月1日からの1名申込み: 受講料 39,600円(E-Mail案内登録価格 37,840円)
定価:本体36,000円+税3,600円
E-Mail案内登録価格:本体34,400円+税3,440円
※1名様でオンライン配信セミナーを受講する場合、上記特別価格になります。
※お申込みフォームで【テレワーク応援キャンペーン】を選択のうえお申込みください。
※他の割引は併用できません。
配布資料製本テキスト(開催日の4、5日前に発送予定)
※開催まで4営業日~前日にお申込みの場合、セミナー資料の到着が、
開講日に間に合わない可能性がありますこと、ご了承下さい。
Zoom上ではスライド資料は表示されますので、セミナー視聴には差し支えございません。
オンライン配信ZoomによるLive配信 ►受講方法・接続確認(申込み前に必ずご確認ください)
セミナー視聴はマイページから
お申し込み後、マイページの「セミナー資料ダウンロード/映像視聴ページ」に
お申込み済みのセミナー一覧が表示されますので、該当セミナーをクリックしてください。
開催日の【2日前】より視聴用リンクが表示されます。
アーカイブ(見逃し)配信付き
視聴期間:10月10日(金)PM~10月17日(金)
※アーカイブは原則として編集は行いません
※視聴準備が整い次第、担当から視聴開始のメールご連絡をいたします。
(開催終了後にマイページでご案内するZoomの録画視聴用リンクからご視聴いただきます)
備考※講義中の録音・撮影はご遠慮ください。
※開催日の概ね1週間前を目安に、最少催行人数に達していない場合、セミナーを中止することがございます。
セミナー趣旨
日本経済は長期デフレを脱しつつあり、近年は物価上昇が定着しつつあります。このインフレ環境では、企業は従来以上に付加価値の高い製品・サービスで差別化し、価格転嫁やプレミアム戦略を追求することが求められます。こうした経営戦略の転換期において、知的財産戦略・技術開発戦略・事業戦略がバラバラに進められていては機会損失や競争力低下に直結しかねません。そこで本講演では、「戦略の分断/断片化を回避」し、知財部門・技術部門・事業部門が互いの戦略と役割を理解し協働するためのポイントと具体策を探ります。日本企業における成功事例と失敗事例を交え、部門間連携によってイノベーション創出や事業競争力強化を実現する上手な進め方を実務目線で解説します。中級レベルの知財担当者・技術開発担当者の方々に、明日から社内連携を促進するヒントを提供することが本講演の目的です。セミナー講演内容
第1部:経済環境の変化
1.デフレからインフレへの経済環境変化と企業戦略への影響
2.社内戦略の分断・断片化が招くリスク
3.インフレ環境下で統合的戦略が重要となる理由
第2部:戦略の分断を防ぐ“三位一体”アプローチの必要性
1.知財戦略・技術戦略・事業戦略の相互関係(“三位一体”のアプローチ)
2.各部門の役割理解と相互理解の必要性
3.部門間の共通言語づくりとコミュニケーション
4.部門間連携を促進する組織体制と仕組み
5.知財・技術・市場情報の共有と戦略立案への活用
6.インフレ時代の知財戦略:知財の攻めと守り
7.知財を軸としたオープンイノベーションと新規事業開拓
第3部:戦略連携の成功事例と失敗事例の分析
1.成功事例(戦略統合の効果)
2.失敗事例(戦略分断の教訓)
第4部:部門間の橋渡しに役立つフレームワークと実践法
1.部門間連携を促進するための実践ステップ
2.必要なスキル・マインドセットと今後の展望
おわりに
~部門間の橋渡しに役立つフレームワーク・実践法とは~
受講可能な形式:【Live配信(アーカイブ配信付)】のみ
── 継続的な物価上昇、インフレにより経営戦略の転換が迫られる今、 分断された戦略では勝ち残れない
サイエンス&テクノロジー
https://www.science-t.com/seminar/K251009.html
本セミナーでは、知財・技術・事業部門が互いの戦略と役割を理解し協働することにより、イノベーションの創出や事業競争力強化を実現するための進め方を実務目線で解説。実際の成功/失敗事例とともに、明日からの社内連携を変える“ヒント”と“フレームワーク”を提供します。「自部門の戦略が全体から乖離している、独り歩きしているのではないか?」と感じている方に是非お役立ていただきたい一講です。
日時2025年10月9日(木) 13:00~16:30
受講料(税込)
各種割引特典49,500円 ( E-Mail案内登録価格 46,970円 )
定価:本体45,000円+税4,500円
E-Mail案内登録価格:本体42,700円+税4,270円
E-Mail案内登録なら、2名同時申込みで1名分無料 1名分無料適用条件
2名で49,500円 (2名ともE-Mail案内登録必須/1名あたり定価半額の24,750円)
1名でのお申込みには、お申込みタイミングによって以下の2つ割引価格がございます
早期申込割引価格対象セミナー【1名受講限定】
8月31日までの1名申込み : 受講料 31,900円(E-mail案内登録価格 31,900円)
定価/E-mail案内登録価格ともに:本体29,000円+税2,900円
※1名様で開催月の2ヵ月前の月末までにお申込みの場合、上記特別価格になります。
※本ページからのお申込みに限り適用いたします。※他の割引は併用できません。
テレワーク応援キャンペーン(1名受講)【オンライン配信セミナー受講限定】
9月1日からの1名申込み: 受講料 39,600円(E-Mail案内登録価格 37,840円)
定価:本体36,000円+税3,600円
E-Mail案内登録価格:本体34,400円+税3,440円
※1名様でオンライン配信セミナーを受講する場合、上記特別価格になります。
※お申込みフォームで【テレワーク応援キャンペーン】を選択のうえお申込みください。
※他の割引は併用できません。
配布資料製本テキスト(開催日の4、5日前に発送予定)
※開催まで4営業日~前日にお申込みの場合、セミナー資料の到着が、
開講日に間に合わない可能性がありますこと、ご了承下さい。
Zoom上ではスライド資料は表示されますので、セミナー視聴には差し支えございません。
オンライン配信ZoomによるLive配信 ►受講方法・接続確認(申込み前に必ずご確認ください)
セミナー視聴はマイページから
お申し込み後、マイページの「セミナー資料ダウンロード/映像視聴ページ」に
お申込み済みのセミナー一覧が表示されますので、該当セミナーをクリックしてください。
開催日の【2日前】より視聴用リンクが表示されます。
アーカイブ(見逃し)配信付き
視聴期間:10月10日(金)PM~10月17日(金)
※アーカイブは原則として編集は行いません
※視聴準備が整い次第、担当から視聴開始のメールご連絡をいたします。
(開催終了後にマイページでご案内するZoomの録画視聴用リンクからご視聴いただきます)
備考※講義中の録音・撮影はご遠慮ください。
※開催日の概ね1週間前を目安に、最少催行人数に達していない場合、セミナーを中止することがございます。
セミナー趣旨
日本経済は長期デフレを脱しつつあり、近年は物価上昇が定着しつつあります。このインフレ環境では、企業は従来以上に付加価値の高い製品・サービスで差別化し、価格転嫁やプレミアム戦略を追求することが求められます。こうした経営戦略の転換期において、知的財産戦略・技術開発戦略・事業戦略がバラバラに進められていては機会損失や競争力低下に直結しかねません。そこで本講演では、「戦略の分断/断片化を回避」し、知財部門・技術部門・事業部門が互いの戦略と役割を理解し協働するためのポイントと具体策を探ります。日本企業における成功事例と失敗事例を交え、部門間連携によってイノベーション創出や事業競争力強化を実現する上手な進め方を実務目線で解説します。中級レベルの知財担当者・技術開発担当者の方々に、明日から社内連携を促進するヒントを提供することが本講演の目的です。セミナー講演内容
第1部:経済環境の変化
1.デフレからインフレへの経済環境変化と企業戦略への影響
2.社内戦略の分断・断片化が招くリスク
3.インフレ環境下で統合的戦略が重要となる理由
第2部:戦略の分断を防ぐ“三位一体”アプローチの必要性
1.知財戦略・技術戦略・事業戦略の相互関係(“三位一体”のアプローチ)
2.各部門の役割理解と相互理解の必要性
3.部門間の共通言語づくりとコミュニケーション
4.部門間連携を促進する組織体制と仕組み
5.知財・技術・市場情報の共有と戦略立案への活用
6.インフレ時代の知財戦略:知財の攻めと守り
7.知財を軸としたオープンイノベーションと新規事業開拓
第3部:戦略連携の成功事例と失敗事例の分析
1.成功事例(戦略統合の効果)
2.失敗事例(戦略分断の教訓)
第4部:部門間の橋渡しに役立つフレームワークと実践法
1.部門間連携を促進するための実践ステップ
2.必要なスキル・マインドセットと今後の展望
おわりに
2025年7月17日「隙のない特許明細書作成のための実施例・比較例の戦略的な書き方」(サイエンス&テクノロジー)が無事終了しました。
2025年7月11日「知財担当者のためのコミュニケーションスキル 〜経営層・技術者・特許事務所・他社・大学との円滑なやりとりの勘所・注意点〜」(テックデザイン)が無事終了しました。
2025年6月27日「少人数知財部における知財業務の効率化、連携、運営のポイント、実例の紹介 」(知財実務情報Lab.)が無事終了しました。
2025年6月19日 「特許の価値評価のコツ ~大王製紙・花王での成功・失敗事例をふまえ~」(テックデザイン)が無事終了しました。
2025年5月30日 「後発参入から競争優位を築く特許出願・権利化戦略(事例付)」(テックデザイン 後発参入で勝つための特許(網)分析と戦略)が無事終了しました。
2025年5月15日「拒絶理由通知分析,対応作成への生成AI活用」(技術情報協会)が無事終了しました。
2025年4月24日「知財業務における生成AIの賢い使い方ー特許調査・出願・中間処理の効率化のポイントと留意点 ー」(サイエンス&テクノロジー株式会社)が無事終了しました。
2025年4月17日「生成AIを活用した発明提案書の書き方と特許明細書チェックのコツ」(テックデザイン)が無事終了しました。
2025年3月25日「実用段階に入った生成AIの特許実務での活用法~特許調査・出願権利化等におけるプロンプト作成等の実演を交えて~」(情報機構)が無事終了しました。
2025年3月13日「研究者・技術者のための特許の“効率的な”読み方」(テックデザイン)が無事終了しました。
2025年2月19日「実用段階に入った生成AIの知財業務での活用」(一般社団法人日本食品・バイオ知的財産権センター令和6年度第3回特別講演会)、2025年2月28日「生成AIの知財業務での活用は早くも実用段階に」(紙パルプ技術協会2024年度特許セミナー)と生成AIの知財業務での活用に関するセミナーを無事終了することができました。活発なご質問ありがとうございました。
2025年2月13日のセミナー「特許侵害の判断基準・対応方法と特許網を回避した製品開発のポイント」(テックデザイン)が無事終了しました。
P2025年1月30日のセミナー「後発で勝つための特許戦略の進め方」(情報機構)が無事終了しました。
2025年1月28日のセミナー「少人数知財部における 効率的な知財業務の進め方」(技術情報協会)が無事終了しました。
2025年1月23日のセミナー「自社技術のノウハウ秘匿及び特許出願の選択指針とオープン&クローズ戦略の進め方 」(サイエンス&テクノロジー㈱)が無事終了しました。
2024年12月13日のセミナー「特許の権利維持・放棄の判断基準と価値評価の考え方 ~ 大王製紙、花王を例に挙げて ~ 」(知財実務情報Lab.)が無事終了しました。
2024年12月12日のセミナー「特許明細書の効率的な読み方と強い特許明細書のつくり方」(TH企画)が無事終了しました。
2024年12月5日のセミナー「効率的な特許調査(先行技術,侵害予防,無効資料)のコツ~生成AIの活用を含めて~」(テックデザイン)が無事終了しました。
2024年10月30日のセミナー「特許業務と生成AI(ChatGPT等)~懸念・リスクへの対応と特許実務への応用~」、JIPA 2024年度 臨時研修会 JA7(集合型研修東京開催/PCライブ研修)が無事終了しました。
2024年10月10日のセミナー「研究開発部門のための特許クレーム解釈~効率よく白黒を見極め、グレーゾーンを狭めるスキル~」(テックデザイン)が無事終了しました。
2024年9月20日のセミナー「生成AI/ChatGPTによる特許調査・知財業務の高度化」(R&D支援センター)が無事終了しました。
2024年8月23日のセミナー「後発でも勝てる特許戦略と先行特許の崩し方、攻め方 【第2部】先発企業の特許網の調査、弱みの特定と特許出願・権利化戦略」(技術情報協会)が無事終了しました。
2024年8月1日の.東薬工特許情報セミナー「生成 AI の知財業務での活用(実務への応用例を中心に)」が無事終了しました。
2024年7月25日の「【初めてからの】知財戦略の立案・策定法~考え方と検討事項・実施手順等~」(情報機構)が無事終了しました。
「知財管理」2024年7月号に、「生成AIの知財業務での活用」を執筆しました。
日本知的財産協会の「知財管理」2024年7月号に『生成AIの知財業務での活用』(よろず知財戦略コンサルティング 代表 医学博士 萬 秀憲)が掲載されました。
抄 録 ChatGPTなどの生成AIの知財業務での活用可能性を検討した。生成AIの活用方法としては,①生成AIをそのまま利用する,②生成AIと社内外のデータとを連携させる,③生成AIを組み込んだ外部ベンダーサービスを利用する,という3つの方法が考えられるため,それぞれの活用方法で評価した。結果,知財業務での生成AIの活用場面としては,特許調査業務としてSDI支援,分類作成支援,特許読み込み支援,出願・権利化業務として発明発掘支援,特許提案書作成支援,拒絶理由通知書の分析支援,そのほかの業務として知財教育支援,知財契約書作成支援について活用できる可能性が高いと考えられたので,検討結果の一部を報告する。また,活用にあたってのリスクと対応についても述べた。なお,本稿は2024年3月時点の生成AI技術に基づき執筆している。
目 次
1.はじめに
2.生成AIとは
2.1生成AIの基本
2.2生成AIによる社会への影響
2.3生成AIによる企業への影響
3.知財業務での生成AI活用
3.1知財業務での生成AI活用可能性
3.2特許調査業務での生成AI活用
3.3特許出願・権利化業務での生成AI活用
3.4知財教育支援業務での生成AI活用
4.生成AI活用にあたってのリスクと対応
4.1生成AIがもたらす新しいリスク
4.2リスクへの対応
5.おわりに
日本知的財産協会の「知財管理」2024年7月号に『生成AIの知財業務での活用』(よろず知財戦略コンサルティング 代表 医学博士 萬 秀憲)が掲載されました。
抄 録 ChatGPTなどの生成AIの知財業務での活用可能性を検討した。生成AIの活用方法としては,①生成AIをそのまま利用する,②生成AIと社内外のデータとを連携させる,③生成AIを組み込んだ外部ベンダーサービスを利用する,という3つの方法が考えられるため,それぞれの活用方法で評価した。結果,知財業務での生成AIの活用場面としては,特許調査業務としてSDI支援,分類作成支援,特許読み込み支援,出願・権利化業務として発明発掘支援,特許提案書作成支援,拒絶理由通知書の分析支援,そのほかの業務として知財教育支援,知財契約書作成支援について活用できる可能性が高いと考えられたので,検討結果の一部を報告する。また,活用にあたってのリスクと対応についても述べた。なお,本稿は2024年3月時点の生成AI技術に基づき執筆している。
目 次
1.はじめに
2.生成AIとは
2.1生成AIの基本
2.2生成AIによる社会への影響
2.3生成AIによる企業への影響
3.知財業務での生成AI活用
3.1知財業務での生成AI活用可能性
3.2特許調査業務での生成AI活用
3.3特許出願・権利化業務での生成AI活用
3.4知財教育支援業務での生成AI活用
4.生成AI活用にあたってのリスクと対応
4.1生成AIがもたらす新しいリスク
4.2リスクへの対応
5.おわりに
Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document.
.2024年6月28日の「技術者・研究者のための特許の効率的な読み方と強い特許取得への生かし方」(R&D支援センター)が無事終了しました。
2024年6月20日の「後発でも勝てる特許出願と権利化戦略 ~先発企業の特許網の調査,弱みの特定と特許出願・権利化戦略~」(TH企画)が無事終了しました。
2024年 6月 12日の「第4回 知財よろず勉強会【生成AI/ChatGPT】」(テックデザイン)が無事終了しました。
2024年6月10日の「知財担当者が身に付けておくべきコミュニケーションスキル ~権利化業務、戦略業務に役立つスキルを解説~」(企業研究会)が無事終了しました。
書籍「適正な知財コストの考え方と権利化、維持、放棄の決め方」出版のお知らせ
2024年5月31日に萬秀憲が執筆者の一人となっている書籍「適正な知財コストの考え方と権利化、維持、放棄の決め方」が出版されました。
https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2250.htm
「第5章 保有特許の価値評価、ポートフォリオ管理と適正な知財コストの考え方」の「第1節 適正な知財投資の考え方と保有特許の価値評価、ポートフォリオ管理の仕方」を執筆しました。
第5章 保有特許の価値評価、ポートフォリオ管理と適正な知財コストの考え方
第1節 適正な知財投資の考え方と保有特許の価値評価、ポートフォリオ管理の仕方
1.適正な知財投資の考え方
1.1 コーポレートガバナンス・コードの改訂による知財投資の重要性の浸透
1.2 コーポレートガバナンス・コード改訂の影響
1.3 統合報告書等にみるコーポレートガバナンス・コード改訂後の変化
1.4 適正な知財投資についての考え方
1.5 知財投資の費用対効果評価のポイント
1.6 過去の知財投資に関する費用対効果の実績評価
1.7 過去の知財投資に関する費用対効果の実績評価詳細
1.8 仮想例の過去の知財投資に関する費用対効果の実績評価
2.保有特許の価値評価の仕方
2.1 自社における保有特許の価値評価
2.2 外部機関による保有特許の価値評価
2.3 ライセンス可能性の評価
2.4 評価のタイミング
2.5 権利維持、放棄の基準
3.ポートフォリオ管理の仕方
3.1 ポートフォリオ管理の重要性
3.2 ポートフォリオ管理のステップ
3.3 ポートフォリオ管理のポイント
https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2250.htm
「第5章 保有特許の価値評価、ポートフォリオ管理と適正な知財コストの考え方」の「第1節 適正な知財投資の考え方と保有特許の価値評価、ポートフォリオ管理の仕方」を執筆しました。
第5章 保有特許の価値評価、ポートフォリオ管理と適正な知財コストの考え方
第1節 適正な知財投資の考え方と保有特許の価値評価、ポートフォリオ管理の仕方
1.適正な知財投資の考え方
1.1 コーポレートガバナンス・コードの改訂による知財投資の重要性の浸透
1.2 コーポレートガバナンス・コード改訂の影響
1.3 統合報告書等にみるコーポレートガバナンス・コード改訂後の変化
1.4 適正な知財投資についての考え方
1.5 知財投資の費用対効果評価のポイント
1.6 過去の知財投資に関する費用対効果の実績評価
1.7 過去の知財投資に関する費用対効果の実績評価詳細
1.8 仮想例の過去の知財投資に関する費用対効果の実績評価
2.保有特許の価値評価の仕方
2.1 自社における保有特許の価値評価
2.2 外部機関による保有特許の価値評価
2.3 ライセンス可能性の評価
2.4 評価のタイミング
2.5 権利維持、放棄の基準
3.ポートフォリオ管理の仕方
3.1 ポートフォリオ管理の重要性
3.2 ポートフォリオ管理のステップ
3.3 ポートフォリオ管理のポイント
2024年5月31日の「<大学・企業間、民間企業間の>共同研究契約の進め方および実情に応じた留意点~様々なトラブル事例とチェックポイント・具体的対処法等~」(情報機構)が無事終了しました。
2024年 5月16日の「研究開発部門における特許出願の数・質の飛躍的向上策」(テックデザイン)が無事終了しました。
2024年 5月13日の「【オンライン】拒絶理由通知対応の実務と勘どころ」(企業研究会)が無事終了しました。
2024年3月28日(木)18時30分~20時にYouTubeで無料公開される(第184回)知財実務オンライン:「知財ガバナンスと生成AIで変わってきた企業知財実務~コロナ禍の知財戦略コンサルティング4年間を踏まえて~」(ゲスト:よろず知財戦略コンサルティング 代表 萬 秀憲)に出演しました。アーカイブ動画が視聴できます。
https://www.youtube.com/watch?v=o63kSxqJcSM
https://www.youtube.com/watch?v=o63kSxqJcSM
2024年3月22日の「【Live配信セミナー】特許調査・知財業務への生成AI/ChatGPTの活用法」(技術情報協会)が無事終了しました。
2024年3月8日の「事例にみる共同研究/開発のトラブル防止策&解決策~不実施補償や発明の帰属、技術流出などに対処した契約書の書き方~」(テックデザイン)が無事終了しました。
2024年2月19日の「【オンライン】知財担当者が身に付けておくべきコミュニケーションスキル~権利化業務、戦略業務に役立つスキルを解説~」(一般社団法人企業研究会)が無事終了しました。
2024年2月6日の「【オンライン】拒絶理由通知対応の実務と勘どころ」(一般社団法人企業研究会)が無事終了しました。
2024年1月31日「知財予算の策定・管理と予算獲得のポイント【第2部】知財投資の費用対効果の説明と予算獲得のポイント」(技術情報協会)が無事終了しました。
2024年1月29日「後発で勝つための特許戦略のすすめ方」(情報機構)が無事終了しました。会場でのセミナー開催でした。
2024年1月26日「拒絶理由通知への備えと対策ノウハウ〜広い権利範囲を有利に確実に権利化する技術〜」(TH企画セミナーセンター)が無事終了しました。
2023年12月14日「特許の価値評価のコツ【権利維持・放棄】【特許出願】【権利化】シーンごとに徹底解説!」が無事終了しました。
2023年12月8日「特許の権利維持・放棄の判断基準と価値評価の考え方 ~ 大王製紙、花王を例に挙げて ~」知財実務情報Lab.が無事終了しました。
2023年11月10日「拒絶理由通知への備えと対策ノウハウ~より広い権利範囲を、より有利に、より確実に権利化するために~」が無事終了しました。
2023年11月7日「第3回 知財よろず勉強会【知財レビュー】=経営層・事業部門・研究開発部門に評価される知財(戦略)レビューの仕方=」が無事終了しました。
2023年10月28日淡路町ゼミ「花王、大王製紙での成功と失敗、知財支援3年間で気になっていること」が無事終了しました。
2023年10月24日のセミナー「特許調査、分析、特許出願業務での生成AI活用のポイント」(技術情報協会)が無事終了しました。
2023年月10月20日のセミナー「BtoB事業における知財戦略・知財活動のポイント」(テックデザイン)が無事終了しました。
2023年月10月5日のセミナー「 特許を効率的に読む技術ならびに強い特許取得のポイント 」(TH企画セミナーセンター)が無事終了しました。
2023年9月22日のセミナー「 ChatGPT等の生成AIの知財実務への活用ポイントと留意点」(テックデザイン)が無事終了しました。知財で著名な大学教授にも参加いただき、正規の時間を超えて質問等もいただきました。聴講されていた方にも参考になったようです。
2023年7月27日のセミナー「 【初めてからの】知財戦略の立案・策定法~考え方と検討事項・実施手順等~」(情報機構)が無事終了しました。
「研究開発リーダー」2023年7月号に、「数値限定発明・パラメータ発明の特許要件と権利行使における問題点」を執筆しました。
技術情報協会発行の月刊「研究開発リーダー」2023年7月号に『数値限定発明・パラメータ発明の特許要件と権利行使における問題点』(よろず知財戦略コンサルティング 代表 医学博士 萬 秀憲)が掲載されました。
詳細は、下記技術情報協会のページと月刊「研究開発リーダー」紙面にてご確認ください。
https://www.gijutu.co.jp/doc/magazine/R_2023_07.htm
1.はじめに
「発明を特定するための事項を, 数値範囲により数量的に表現した」数値限定発明, 数値限定発明の一種である「先行技術には記載のない特性等を, 数値範囲や数式で限定している」パラメータ発明について, 特許要件を確認したうえで, 数値限定発明・パラメータ発明の権利行使における問題点を解説する.
2.数値限定発明・パラメータ発明の特許要件について
2.1 数値限定発明・パラメータ発明とは?
2.2 数値限定発明・パラメータ発明の新規性
2.3 数値限定発明・パラメータ発明の進歩性
2.4 数値限定発明・パラメータ発明の記載要件
3.数値限定発明・パラメータ発明の権利行使における問題点
3.1 測定方法・測定条件の記載
3.2 製品ごとの物性のばらつき
3.3 測定結果がわずかに外れる場合
3.4 先使用権の抗弁
3.5 数値限定発明・パラメータ発明の権利行使時の主張・立証のポイント
4.おわりに
技術情報協会発行の月刊「研究開発リーダー」2023年7月号に『数値限定発明・パラメータ発明の特許要件と権利行使における問題点』(よろず知財戦略コンサルティング 代表 医学博士 萬 秀憲)が掲載されました。
詳細は、下記技術情報協会のページと月刊「研究開発リーダー」紙面にてご確認ください。
https://www.gijutu.co.jp/doc/magazine/R_2023_07.htm
1.はじめに
「発明を特定するための事項を, 数値範囲により数量的に表現した」数値限定発明, 数値限定発明の一種である「先行技術には記載のない特性等を, 数値範囲や数式で限定している」パラメータ発明について, 特許要件を確認したうえで, 数値限定発明・パラメータ発明の権利行使における問題点を解説する.
2.数値限定発明・パラメータ発明の特許要件について
2.1 数値限定発明・パラメータ発明とは?
2.2 数値限定発明・パラメータ発明の新規性
2.3 数値限定発明・パラメータ発明の進歩性
2.4 数値限定発明・パラメータ発明の記載要件
3.数値限定発明・パラメータ発明の権利行使における問題点
3.1 測定方法・測定条件の記載
3.2 製品ごとの物性のばらつき
3.3 測定結果がわずかに外れる場合
3.4 先使用権の抗弁
3.5 数値限定発明・パラメータ発明の権利行使時の主張・立証のポイント
4.おわりに
2023年7月14日のセミナー「 技術者・研究者のための特許の効率的な読み方と強い特許取得への生かし方」(株式会社R&D支援センター)が無事終了しました。
2023年7月7日のセミナー「 特許出願・ノウハウ秘匿の考え方と選択基準」(テックデザイン)が無事終了しました。
.2023年7月3日の「第2回知財よろず勉強会【ChatGPT】~知財業務を革新できる? ChatGPTの活用ポイントと留意点~」が無事終了しました。非常に多くの方に参加いただき、関心の高いテーマであることを再認識しました。
2023年5月30日の「第1回 知財よろず勉強会【IPランドスケープ】」(テックデザイン)が無事終了しました。
2023年5月18日の「<大学・企業間、民間企業間の>共同研究契約の進め方とその実情・留意点~契約書のチェックポイント・様々なトラブル事例とその具体的対処等~」(情報機構)が無事終了しました。
2023年4月19日の「特許出願の数と質の向上につながる発明発掘ノウハウ」(テックデザイン)が無事終了しました。
2023年3月13日の「特許明細書の効率的な読み方と強い特許明細書のつくり方」(技術情報協会)が無事終了しました。
2023年 3 月 8日 の「CGC(コーポレートガバナンス・コード)改訂に対応した知財ガバナンス体制の構築と実践ポイント 【第1部】知財・無形資産ガバナンスガイドラインの解釈と実務対応」が無事終了しました。
2023年 3 月 7日 の「.数値限定発明・パラメータ発明を有利に、確実に権利化するための出願・権利化のノウハウ~ 理解を深めるために成功例・失敗例を含めて事例を解説 ~」は、久しぶりの会場受講のみの対面によるセミナーで、会場がしっかり埋まりました。対面だと受講者の反応がしっかり把握でき、コミュニケーションもとれ、終了後の個別の突っ込んだ質問もあり、やっぱり良いなあと思いました。
2023年 3 月 3日 の「大学・企業間または民間企業間の共同研究契約の進め方とその実情・留意点~契約書のチェックポイント・様々なトラブル事例とその具体的対処等~」が無事終了しました。
2023年 1月30日 の「特許の読み方を半日で習得する!!研究者・技術者のための特許を効率的に読む技術 ~短時間で習得できる読み方のノウハウ~ 」が無事終了しました。20名を超える受講者で質問も活発でした。
2023年1月20日の「~知らないと損をする︕より広く・より有利な権利取得に役立つ~特許面接審査の活用ノウハウ」が無事終了しました。
2023年1月17日の「後発で勝つための特許戦略のすすめ方」が無事終了しました。
2022年12月9日の「特許の権利維持・放棄の判断基準と価値評価の考え方~大王製紙、花王を例に挙げて~」が無事終了しました。
2022年12月2日の「拒絶理由通知への対応手順と勘どころ」が無事終了しました。 受講者からの質問が非常に多く寄せられました。ありがとうございました。
2022年11月17日の「適正な知財コストの考え方と権利維持、放棄の決め方」が無事終了しました。
2022年9月16日の「特許の価値評価のコツ 【権利維持・放棄】【特許出願】【権利化】シーンごとに徹底解説!」が無事終了しました。
書籍「研究開発部門と他部門の壁の壊し方、協力体制の築き方」(発刊日:2022年8月31日)が出版されました。
「第5章 R&D部門と知財部との連携によるスムーズなテーマ推進、権利化の取組み 第1節 研究開発部門、知財部門の連携によるR&Dテーマの発掘」を執筆しました。
発刊日:2022年8月31日 体 裁:A4判 592頁 定 価:88,000円(税込)
ISBN:978-4-86104-888-3
https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2166.htm
第5章 R&D部門と知財部との連携によるスムーズなテーマ推進、権利化の取り組み◇
第1節 研究開発部門、知財部門の連携によるR&Dテーマの発掘
1.顧客が求めている潜在的な課題の発掘がR&Dテーマの発掘
1.1 顕在ニーズと潜在ニーズ
1.2 潜在ニーズの発掘法
2.特許情報から潜在ニーズを発掘する方法
2.1 自社は気づいていないが他社が気づいている潜在ニーズを整理する
2.1.1 課題解決マトリックス
2.1.2 課題の年次別整理
2.2 今は必要としないが大きな変化により必要になる将来ニーズを整理する
3.研究開発部門と知財部門の連携の仕方
3.1 R&D部門、知財部門の従来の役割を超えた越境的取り組み
3.1.1 R&D部門主導で行うR&D部門、知財部門の従来の役割を超えた越境的取り組み
3.1.2 知財部門主導で行うR&D部門、知財部門の従来の役割を超えた越境的取り組み
3.2 新規事業創造におけるR&Dテーマの発掘
4.IPランドスケープ推進による研究開発部門と知財部門の連携
「第5章 R&D部門と知財部との連携によるスムーズなテーマ推進、権利化の取組み 第1節 研究開発部門、知財部門の連携によるR&Dテーマの発掘」を執筆しました。
発刊日:2022年8月31日 体 裁:A4判 592頁 定 価:88,000円(税込)
ISBN:978-4-86104-888-3
https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2166.htm
第5章 R&D部門と知財部との連携によるスムーズなテーマ推進、権利化の取り組み◇
第1節 研究開発部門、知財部門の連携によるR&Dテーマの発掘
1.顧客が求めている潜在的な課題の発掘がR&Dテーマの発掘
1.1 顕在ニーズと潜在ニーズ
1.2 潜在ニーズの発掘法
2.特許情報から潜在ニーズを発掘する方法
2.1 自社は気づいていないが他社が気づいている潜在ニーズを整理する
2.1.1 課題解決マトリックス
2.1.2 課題の年次別整理
2.2 今は必要としないが大きな変化により必要になる将来ニーズを整理する
3.研究開発部門と知財部門の連携の仕方
3.1 R&D部門、知財部門の従来の役割を超えた越境的取り組み
3.1.1 R&D部門主導で行うR&D部門、知財部門の従来の役割を超えた越境的取り組み
3.1.2 知財部門主導で行うR&D部門、知財部門の従来の役割を超えた越境的取り組み
3.2 新規事業創造におけるR&Dテーマの発掘
4.IPランドスケープ推進による研究開発部門と知財部門の連携
書籍「費用対効果に基づく外国特許出願国の選び方・進め方」(発刊日:2022年7月29日)が出版されました。
「第6章 外国特許出願/ノウハウ秘匿の選択基準 第1節 外国への特許出願/ノウハウ保護のメリットとデメリット」を執筆しました。
https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2164.htm
はじめに
1.外国への特許出願によるメリットとデメリット
2.日本で特許出願して外国へ特許出願しないメリットとデメリット
3.外国でのノウハウ秘匿によるメリットとデメリット
4.特許出願するか、ノウハウとして秘匿するか判断するプロセス
5.営業秘密によるノウハウの保護
6.先使用権によるノウハウの保護
「第6章 外国特許出願/ノウハウ秘匿の選択基準 第1節 外国への特許出願/ノウハウ保護のメリットとデメリット」を執筆しました。
https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2164.htm
はじめに
1.外国への特許出願によるメリットとデメリット
2.日本で特許出願して外国へ特許出願しないメリットとデメリット
3.外国でのノウハウ秘匿によるメリットとデメリット
4.特許出願するか、ノウハウとして秘匿するか判断するプロセス
5.営業秘密によるノウハウの保護
6.先使用権によるノウハウの保護
「月刊 研究開発リーダー 」2022年7月号に、「先発企業の特許網の調査、弱みの特定と特許出願・権利化戦略」を執筆しました。
https://www.gijutu.co.jp/doc/magazine/R_2022_07.htm
1.はじめに
後発で市場に進出する場合、市場の壁、技術の壁、知的財産権の壁があり、これらの壁を打破できるか否かが鍵となる。強力な特許網で先発メーカーが圧倒的なシェアを持っていた市場へ参入する場合には、参入障壁となる先発企業の特許網をくぐり抜けて、自社技術で先発企業の商品・サービスを凌ぐ品質の商品・サービスを作り上げ、さらに競合他社が同様の品質の商品・サービスを実現できないように強力な特許網を構築していく必要がある。
2.参入障壁となる先発企業の特許網の調査と弱みの特定
3.後発で勝つための特許出願・権利化戦略
4.おわりに
https://www.gijutu.co.jp/doc/magazine/R_2022_07.htm
1.はじめに
後発で市場に進出する場合、市場の壁、技術の壁、知的財産権の壁があり、これらの壁を打破できるか否かが鍵となる。強力な特許網で先発メーカーが圧倒的なシェアを持っていた市場へ参入する場合には、参入障壁となる先発企業の特許網をくぐり抜けて、自社技術で先発企業の商品・サービスを凌ぐ品質の商品・サービスを作り上げ、さらに競合他社が同様の品質の商品・サービスを実現できないように強力な特許網を構築していく必要がある。
2.参入障壁となる先発企業の特許網の調査と弱みの特定
3.後発で勝つための特許出願・権利化戦略
4.おわりに
「COSMETIC STAGE」 2022年4月号に、「特許面接審査を活用した広い権利範囲の取得」を執筆しました。
1. はじめに
特許庁では,特許出願の審査が円滑かつ的確に進むようにするための有効な手続きとして,審査官との「面接審査」を設け,その活用をすすめているが,面接審査はごく一部で利用されるにとどまり,面接審査経験者からその活用の利点や実施ノウハウを学ぶ機会が少ないことが懸念される。情報の少なさから,漠然と面接審査にかかる時間や手間を考え,実施に二の足を踏んでいる担当者も少なくない。
しかしながら,事業・経営戦略における特許の重要性が高まる中,より広い権利範囲を,より有利に,より確実に権利化したいという場面においては,面接審査を選択肢の一つに入れられるかどうかで結果が変わり,事業・経営戦略に影響を及ぼすことも十分考えられる。以下,面接審査を活用し広い権利範囲を取得するやり方について述べる。
2. 面接審査によるメリット
2.1 面接審査の実施率
2.2 面接審査実施案件の特許査定率
2.3 早期審査案件での面接審査実施率と特許査定率
3. まずは審査官を知る
3.1 審査官とはどんな人たちか︖
3.2 審査官が守らなければいけないマニュアル「特許・実用新案審査基準」 「特許・実用新案審査ハンドブック」 3.3 特許庁の面接ガイドライン【特許審査編】
4. 面接前の準備
4.1 審査官の傾向の分析
4.2 拒絶理由通知の分析
4.3 争点整理
4.4 補正書案と意見書案
4.5 審査官に納得してもらうポイントと 面接方針の決定
5. 審査官との面接
5.1 当該技術分野の技術説明
5.2 本願発明の本質の説明
5.3 拒絶理由に対する出願人の判断と対応の説明
5.4 審査官と出願人の主張に関する議論
5.5 面接記録の記載
5.6 面接時のコツ
6. 面接後の対応
7. まとめ
1. はじめに
特許庁では,特許出願の審査が円滑かつ的確に進むようにするための有効な手続きとして,審査官との「面接審査」を設け,その活用をすすめているが,面接審査はごく一部で利用されるにとどまり,面接審査経験者からその活用の利点や実施ノウハウを学ぶ機会が少ないことが懸念される。情報の少なさから,漠然と面接審査にかかる時間や手間を考え,実施に二の足を踏んでいる担当者も少なくない。
しかしながら,事業・経営戦略における特許の重要性が高まる中,より広い権利範囲を,より有利に,より確実に権利化したいという場面においては,面接審査を選択肢の一つに入れられるかどうかで結果が変わり,事業・経営戦略に影響を及ぼすことも十分考えられる。以下,面接審査を活用し広い権利範囲を取得するやり方について述べる。
2. 面接審査によるメリット
2.1 面接審査の実施率
2.2 面接審査実施案件の特許査定率
2.3 早期審査案件での面接審査実施率と特許査定率
3. まずは審査官を知る
3.1 審査官とはどんな人たちか︖
3.2 審査官が守らなければいけないマニュアル「特許・実用新案審査基準」 「特許・実用新案審査ハンドブック」 3.3 特許庁の面接ガイドライン【特許審査編】
4. 面接前の準備
4.1 審査官の傾向の分析
4.2 拒絶理由通知の分析
4.3 争点整理
4.4 補正書案と意見書案
4.5 審査官に納得してもらうポイントと 面接方針の決定
5. 審査官との面接
5.1 当該技術分野の技術説明
5.2 本願発明の本質の説明
5.3 拒絶理由に対する出願人の判断と対応の説明
5.4 審査官と出願人の主張に関する議論
5.5 面接記録の記載
5.6 面接時のコツ
6. 面接後の対応
7. まとめ
書籍「With· Afterコロナで生まれた新しい潜在・将来ニーズの発掘と新製品開発への応用」出版のお知らせ
2022年2月28日.に、萬秀憲が執筆者の一人となっている書籍「With· Afterコロナで生まれた新しい潜在・将来ニーズの発掘と新製品開発への応用」が出版されました。(第5章 第5節 特許情報から潜在ニーズを発掘する方法とその活用の仕方」を担当しました。著者紹介割引(定 価:88,000円(税込)→特別割引:70,400円(税込)で購入可能とのこと。ご希望の方はcontact@yorozuipsc.comまでご連絡いただければ、著者紹介割引申込書をメールで送付します。)
https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2142.htm
https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2142.htm
2022年6月14日の「より広い権利範囲を、より有利に、より確実に権利化するための特許面接審査の活用ノウハウ」が無事終了しました。
2022年6月7日の「新規性・進歩性の判断方法と新規性・進歩性による拒絶理由通知への対応、技術情報協会」が無事終了しました。
2022年5月31日の「<大学・企業間、民間企業間の>共同研究契約の進め方とその実情・留意点~契約書のチェックポイント・様々なトラブル事例とその具体的対処等~」が無事終了しました。
2022年5月23日の「改訂コーポレートガバナンス・コードの解釈と実務対応のポイント~CGC改訂に対応した知財ガバナンス体制と知財投資活用戦略の構築、知財情報開示の見直し~, テックデザイン」が無事終了しました。
【オンデマンド】で視聴可能です。視聴期間:2022年6月6日(月)~2022年6月30日(木) ※期間中何度でも視聴可能です。
https://www.tech-d.jp/seminar/show/6093
【オンデマンド】で視聴可能です。視聴期間:2022年6月6日(月)~2022年6月30日(木) ※期間中何度でも視聴可能です。
https://www.tech-d.jp/seminar/show/6093
2022年4月12日の「後発で勝つ︕知財戦略と実践ノウハウ【事例付】 ~先発企業の解析方法、先行商品を超える商品を開発するコツ~」が無事終了しました。
2022年3月29日の「研究者・技術者のための特許を効率的に読む技術~短時間で習得できる読み方のノウハウ~【WEB受講(Zoomセミナー)】が無事終了しました。
2022年2月25日の「特許の権利維持・放棄の判断基準と価値評価の考え方~大王製紙、花王を例に挙げて~」, 知財実務情報Labが無事終了しました。
2022年2月2日の「~少人数でもすぐに始められる!~IPランドスケープによる知財戦略の策定手法」, テックデザインが無事終了しました。
2022年2月1日の『ナノセルロースジャパン(NCJ)』の会員向けのオンラインセミナー「ナノセルロース特許入門」が無事終了しました。
2021年12月7日の「オンライン座談会︓知財よろず相談室」, テックデザインが無事終了しました。
2021年11月19日のセミナー「中長期を見据えた知的財産戦略の策定とその遂行」セミナーの「第2部 未来を見据えた知財戦略の立案と事業戦略への活かし方」, 技術情報協会が無事終了しました。
2021年11月9日のセミナー「知財担当者のためのコミュニケーションスキル~経営層・技術者・特許事務所・他社・大学との円滑なやりとりの勘所・注意点~」が、最初パソコン画面が映らないというとトラブルがありましたが、無事終了しました。
2021年10月26日のセミナー「技術・研究・開発担当者が心得ておくべき特許の重要性と理想的な発明現場・体制の構築法」が無事終了しました。
2021年10月15日の第32回国立大学法人産学連携センター長等会議研究会でのキーノートスピーチ「コロナ禍での産学官連携~新しい連携への道の模索~」, パネルディスカッション「コロナ禍での産学官連携について」でのコメンテーター 無事終了しました。
2021年10月12日のセミナー「特許の価値評価のコツ【権利維持・放棄】【特許出願】【権利化】シーンごとに徹底解説!」が無事終了しました。
9月28日のセミナー「後発で勝つための特許戦略のすすめ方」が無事終了しました。
9月14日のセミナー「 知財教育カリキュラムとポイント~利益につながる知財力を養う教育システムの作り方~」が無事終了しました。
8月25日のセミナー「研究者・技術者のための特許を効率的に読む技術~短時間で習得できる読み方のノウハウ~」が無事終了しました。
8月20日のセミナー「 =経営・事業部に評価される=知財戦略の策定と活動のやり方・見せ方」が無事終了しました。
7月21日のセミナー「 事例にみる共同研究/開発のトラブル防止策&解決策」が無事終了しました。
7月13日のセミナー「 絶対に押さえておきたい知財戦略 3トレンド ①後発で勝つための知財戦略 ②オープン&クロース戦略に基づく知財戦略 ③DXを支える知財戦略 」が無事終了しました。
6月4日、8日、11日、18日の「4回連続講座 特許の読み方、調査のコツと他社の特許網を回避した製品開発のポイント」【第1講】 特許侵害の判断基準・対応方法と特許網を回避した製品開発のポイント 6月4日、【第2講】発明提案書の書き方と特許明細書チェックのコツ 6月8日、【第3講】 研究者・技術者のための特許の"効率的な"読み方 6月11日、【第4講】効率的な特許調査(先行技術調査、侵害予防調査、無効資料調査)のコツ 6月18日 、及び、6月15日の「研究者・技術者のための特許の“効率的な”読み方+オンライン座談会:知財よろず相談室」が無事終了しました。
5月17日セミナー「研究開発・事業部門における知財教育のすすめ方~特許の意識付け・啓発のポイントからカリキュラム・手法の具体例まで~」、及び、5月18日セミナー「研究開発部門のための特許クレーム解釈~効率よく白黒を見極め、グレーゾーンを狭めるスキル~」が無事終了しました。
2021年4月20日セミナー「~少人数でもすぐに始められる!~IPランドスケープによる知財戦略の策定手法」が無事終了しました。
書籍「経営・事業戦略に貢献する知財価値評価と効果的な活用法」出版のお知らせ
3月末に、萬秀憲が執筆者の一人となっている書籍「経営・事業戦略に貢献する知財価値評価と効果的な活用法」が出版されました。https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2092.htm
ほんの一部ですが執筆しましたので、特別著者紹介割引(定 価:88,000円(税込)→特別割引:70,400円(税込)で購入可能とのこと。ご希望の方はcontact@yorozuipsc.comまでご連絡いただければ、著者紹介割引申込書をメールで送付します。)
ほんの一部ですが執筆しましたので、特別著者紹介割引(定 価:88,000円(税込)→特別割引:70,400円(税込)で購入可能とのこと。ご希望の方はcontact@yorozuipsc.comまでご連絡いただければ、著者紹介割引申込書をメールで送付します。)
書籍「研究開発テーマの評価と中止/撤退判断の仕方」出版のお知らせ
3月末に、萬秀憲が執筆者の一人となっている書籍「研究開発テーマの評価と中止/撤退判断の仕方」が出版されました。
https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2091.htm
ほんの一部ですが執筆しましたので、著者紹介割引(定 価:88,000円(税込)→特別割引:70,400円(税込)で購入可能とのこと。ご希望の方はcontact@yorozuipsc.comまでご連絡いただければ、著者紹介割引申込書をメールで送付します。)
https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2091.htm
ほんの一部ですが執筆しましたので、著者紹介割引(定 価:88,000円(税込)→特別割引:70,400円(税込)で購入可能とのこと。ご希望の方はcontact@yorozuipsc.comまでご連絡いただければ、著者紹介割引申込書をメールで送付します。)
2021年4月20日セミナー「~少人数でもすぐに始められる!~IPランドスケープによる知財戦略の策定手法」が無事終了しました。
2021年3月10日セミナー「特許侵害の判断基準・対応方法と特許網を回避した製品開発のポイント」が無事終了しました。
2月16日セミナー「知的財産業務の効率化と経営に資する知財組織・体制づくり」が無事終了しました。
オンラインセミナー特有のトラブルがあり、一時はどうなることかと思いましたが、無事終了しました。
オンラインセミナー特有のトラブルがあり、一時はどうなることかと思いましたが、無事終了しました。
2月9日Webセミナーが無事終了しました。
発明提案書の書き方と特許明細書チェックのコツ
発明提案書の書き方と特許明細書チェックのコツ
1月19日Webセミナーが無事終了しました。
事例にみる共同研究/開発のトラブル防止策&解決策
~不実施補償や発明の帰属、技術流出などに対処した契約書の書き方~
事例にみる共同研究/開発のトラブル防止策&解決策
~不実施補償や発明の帰属、技術流出などに対処した契約書の書き方~
新セミナーを企画しました。「萬秀憲の本当に役立つ知財セミナー【全12回】」
2021年の1年間12回のコースで新しいセミナーを企画しました。
https://www.tech-d.jp/seminar/show/5268
「若い人に研究開発や知財の実務で本当に役立つ知識・ノウハウを伝えたい!」そんな思いから企画したシリーズ講座です。
12のテーマは、自身の企業経験を振り返り、重要だと感じたものをトピック形式で企画しています。
1年を通じた長丁場な講座ですが、オンライン形式で、かつ、アーカイブもありますので、無理なく、楽しんで受講できると思います。
多くの若い人に、知財に強い、頼られる実務者に成長していただけることを願っています。
日程 /タイトル/活用シーン
1/19(火) ①事例にみる共同研究/開発のトラブル防止策&解決策 ⇒共同研究のスムーズな進め方とリスクの最小化に役立つ内容です
2/9(火) ②発明提案書の書き方と特許明細書チェックのコツ ⇒面倒な特許書類作成が短時間で終わり、かつ質も高まるコツをお伝えします。
3/10(水) ③特許侵害の判断基準・対応方法と特許網を回避した製品開発のポイント⇒特許侵害の予防対策、発生時の対応方法だけでなく、他社特許網を回避し、弱点をつく開発のポイントも解説します。
4/20(火) ④IPランドスケープによる知財戦略の策定手法⇒「IPランドスケープに興味はあるが、やり方がわからない」「知財戦略が上手くいかない」という方々にお役に立てる内容です。
5/18(火) ⑤研究開発部門のための特許クレーム解釈⇒他社特許の有効性や権利範囲を過大評価せず、 ビジネスチャンスを逃さないための特許分析技術をレクチャーします。
6/15(火) ⑥研究者・技術者のための特許の“効率的な”読み方⇒発明のヒント、特許化、侵害判断、無効化、弱点発見等の活用など、 目的に応じた特許の読み方を身につけます。
7月 特許出願の数と質の向上につながる発明発掘ノウハウ
8月 知財戦略Ⅰ(後発、オープンクローズ、DX)
9月 知財戦略Ⅱ(戦略策定、組織作り、実践)
10月 知財教育
11月 知財マネジメント
12月 知財に必要なコミュニケーションスキル(交渉力、情報提供力)
2021年の1年間12回のコースで新しいセミナーを企画しました。
https://www.tech-d.jp/seminar/show/5268
「若い人に研究開発や知財の実務で本当に役立つ知識・ノウハウを伝えたい!」そんな思いから企画したシリーズ講座です。
12のテーマは、自身の企業経験を振り返り、重要だと感じたものをトピック形式で企画しています。
1年を通じた長丁場な講座ですが、オンライン形式で、かつ、アーカイブもありますので、無理なく、楽しんで受講できると思います。
多くの若い人に、知財に強い、頼られる実務者に成長していただけることを願っています。
日程 /タイトル/活用シーン
1/19(火) ①事例にみる共同研究/開発のトラブル防止策&解決策 ⇒共同研究のスムーズな進め方とリスクの最小化に役立つ内容です
2/9(火) ②発明提案書の書き方と特許明細書チェックのコツ ⇒面倒な特許書類作成が短時間で終わり、かつ質も高まるコツをお伝えします。
3/10(水) ③特許侵害の判断基準・対応方法と特許網を回避した製品開発のポイント⇒特許侵害の予防対策、発生時の対応方法だけでなく、他社特許網を回避し、弱点をつく開発のポイントも解説します。
4/20(火) ④IPランドスケープによる知財戦略の策定手法⇒「IPランドスケープに興味はあるが、やり方がわからない」「知財戦略が上手くいかない」という方々にお役に立てる内容です。
5/18(火) ⑤研究開発部門のための特許クレーム解釈⇒他社特許の有効性や権利範囲を過大評価せず、 ビジネスチャンスを逃さないための特許分析技術をレクチャーします。
6/15(火) ⑥研究者・技術者のための特許の“効率的な”読み方⇒発明のヒント、特許化、侵害判断、無効化、弱点発見等の活用など、 目的に応じた特許の読み方を身につけます。
7月 特許出願の数と質の向上につながる発明発掘ノウハウ
8月 知財戦略Ⅰ(後発、オープンクローズ、DX)
9月 知財戦略Ⅱ(戦略策定、組織作り、実践)
10月 知財教育
11月 知財マネジメント
12月 知財に必要なコミュニケーションスキル(交渉力、情報提供力)
主 催 申込・問合先 株式会社テックデザイン( http://www.tech-d.jp/ )
住 所 〒102-0074 東京都千代田区九段南3-9-14 九段南センタービル5 階
電 話 03-6261-7920 FAX 03-6261-7924 E-mail entry@tech-d.jp (申込) / info@tech-d.jp (問合)【Webセミナー】
https://www.tech-d.jp/seminar/show/5268
【受 講 料】全12回:198,000円(税込/テキスト付) 講師紹介割引で158,000円になります。(スポット受講より総額76,000円お得です。)ご希望の方はご連絡ください。hidenori.yorozu@yorozuipsc.com までご連絡いただければ、講師紹介割引申込書をメールで送付します。
【テキスト】各回ごとに電子データで配布
【形 式】オンライン講座となります
【備 考①】スポット受講も可能です。
【備 考②】全講座、アーカイブ配信をしますので、開催日にご都合が合わなくても、受講(視聴)できます
【備 考③】お申込時点で終了した講座がある場合、アーカイブ配信を視聴してください
住 所 〒102-0074 東京都千代田区九段南3-9-14 九段南センタービル5 階
電 話 03-6261-7920 FAX 03-6261-7924 E-mail entry@tech-d.jp (申込) / info@tech-d.jp (問合)【Webセミナー】
https://www.tech-d.jp/seminar/show/5268
【受 講 料】全12回:198,000円(税込/テキスト付) 講師紹介割引で158,000円になります。(スポット受講より総額76,000円お得です。)ご希望の方はご連絡ください。hidenori.yorozu@yorozuipsc.com までご連絡いただければ、講師紹介割引申込書をメールで送付します。
【テキスト】各回ごとに電子データで配布
【形 式】オンライン講座となります
【備 考①】スポット受講も可能です。
【備 考②】全講座、アーカイブ配信をしますので、開催日にご都合が合わなくても、受講(視聴)できます
【備 考③】お申込時点で終了した講座がある場合、アーカイブ配信を視聴してください
You Tube 配信の知財実務オンライン(第17回)「共同開発・知的財産で会社を元気にする ~共同開発・契約のコツ、特許出願大幅増・質向上のコツ~」が、1,800回を超えて視聴されました。
10月1日(18:30-20:21)に、You Tube で無料配信されている、知財実務オンライン(第17回)「共同開発・知的財産で会社を元気にする ~共同開発・契約のコツ、特許出願大幅増・質向上のコツ~」に、よろず知財戦略コンサルティング 代表 萬 秀憲が登壇しました。アーカイブ視聴が1,600回を超えました。
セミナータイトル:共同開発・知的財産で会社を元気にする ~共同開発・契約のコツ、特許出願大幅増・質向上のコツ~
日時:2020年10月1日(木) 18時30分~20時21分
場所:You Tubeによるオンライン配信
https://www.youtube.com/watch?v=xU9G0fc_wzI
講師:萬 秀憲
主催:知財実務オンライン
詳細:無料で、アーカイブ視聴できます
10月1日(18:30-20:21)に、You Tube で無料配信されている、知財実務オンライン(第17回)「共同開発・知的財産で会社を元気にする ~共同開発・契約のコツ、特許出願大幅増・質向上のコツ~」に、よろず知財戦略コンサルティング 代表 萬 秀憲が登壇しました。アーカイブ視聴が1,600回を超えました。
セミナータイトル:共同開発・知的財産で会社を元気にする ~共同開発・契約のコツ、特許出願大幅増・質向上のコツ~
日時:2020年10月1日(木) 18時30分~20時21分
場所:You Tubeによるオンライン配信
https://www.youtube.com/watch?v=xU9G0fc_wzI
講師:萬 秀憲
主催:知財実務オンライン
詳細:無料で、アーカイブ視聴できます
来年3月10日に「特許侵害の判断基準・対応方法と特許網を回避した製品開発のポイント」というセミナーを行うことになりました。
2021年3月10日(水) 14:00~17:00
【Webセミナー(Live配信)】https://www.tech-d.jp/seminar/show/5289
<講義概要>社特許侵害の有無の⾒極めと適切な侵害対応法、侵害予防策の組織体制について具体的に解説します。更に、単に侵害を回避するだけでなく、他社の特許の抜け道から優れたアイデアを生み出す方法を紹介します。
2021年3月10日(水) 14:00~17:00
【Webセミナー(Live配信)】https://www.tech-d.jp/seminar/show/5289
<講義概要>社特許侵害の有無の⾒極めと適切な侵害対応法、侵害予防策の組織体制について具体的に解説します。更に、単に侵害を回避するだけでなく、他社の特許の抜け道から優れたアイデアを生み出す方法を紹介します。
来年2月9日に「発明提案書の書き方と特許明細書チェックのコツ」というセミナーを行うことになりました。
2021年2月9日(火) 14:00~17:00
【Webセミナー(Live配信)】https://www.tech-d.jp/chemical/seminar/show/5270
<講義概要>
特許出願を契機に、自らの発明に気づき、発明を自らの手で育て上げることが、研究者・技術者自身の大きな財産となります。限られた時間で的を射た「発明提案書」や「特許明細書」を書くことは創造活動そのものとも言えます。
演者は長年にわたり、研究者および管理者として発明創出、出願、知財組織作りに従事してきました。その中での数多くの提案書や明細書の作成や添削チェックの経験と実績をベースに、「発明提案書」を書くのが“苦手・嫌い”という研究者・技術者が、苦手意識を払しょくし、「発明提案書」に取り組みやすくなり、短時間で且つ質の高い「発明提案書」を書けるようになるポイント、及び、事業に貢献するという視点での「発明提案書」の書き方を解説します。
また、研究者・技術者が、外部弁理士が書いた「特許明細書」を的確にチェック・評価し、広くて強い特許を取得することができるようになるための基礎知識とノウハウ(コツ)について解説します。
2021年2月9日(火) 14:00~17:00
【Webセミナー(Live配信)】https://www.tech-d.jp/chemical/seminar/show/5270
<講義概要>
特許出願を契機に、自らの発明に気づき、発明を自らの手で育て上げることが、研究者・技術者自身の大きな財産となります。限られた時間で的を射た「発明提案書」や「特許明細書」を書くことは創造活動そのものとも言えます。
演者は長年にわたり、研究者および管理者として発明創出、出願、知財組織作りに従事してきました。その中での数多くの提案書や明細書の作成や添削チェックの経験と実績をベースに、「発明提案書」を書くのが“苦手・嫌い”という研究者・技術者が、苦手意識を払しょくし、「発明提案書」に取り組みやすくなり、短時間で且つ質の高い「発明提案書」を書けるようになるポイント、及び、事業に貢献するという視点での「発明提案書」の書き方を解説します。
また、研究者・技術者が、外部弁理士が書いた「特許明細書」を的確にチェック・評価し、広くて強い特許を取得することができるようになるための基礎知識とノウハウ(コツ)について解説します。
12月9日Webセミナーが無事終了しました。
~特許否定論への対応、組織を特許体質へと変える実践方法(事例付)~
研究開発部門における特許出願の数・質の飛躍的向上策
2020年12月9日(水) 14:00~17:00【Webセミナー(Live配信)】
多くの方にご参加いただきありがとうございました。
~特許否定論への対応、組織を特許体質へと変える実践方法(事例付)~
研究開発部門における特許出願の数・質の飛躍的向上策
2020年12月9日(水) 14:00~17:00【Webセミナー(Live配信)】
多くの方にご参加いただきありがとうございました。
10月21日Webセミナーが無事終了しました。
研究者・技術者のための特許の“効率的な”読み方
2020年10月21日(水) 10:00~12:30 【Webセミナー(Live配信)】
特許出願の数と質の向上につながる発明発掘ノウハウ
2020年10月21日(水) 13:30~16:00 【Webセミナー(Live配信)】
多くの方にご参加いただきありがとうございました。
研究者・技術者のための特許の“効率的な”読み方
2020年10月21日(水) 10:00~12:30 【Webセミナー(Live配信)】
特許出願の数と質の向上につながる発明発掘ノウハウ
2020年10月21日(水) 13:30~16:00 【Webセミナー(Live配信)】
多くの方にご参加いただきありがとうございました。
10月7日Zoomセミナーが無事終了しました。
経営層・事業部門への知的財産の貢献度評価と効果的な報告の仕方
2020年10月7日(水) 10:00~17:00
【第3部】経営層、事業部に知財活動、貢献度を報告できる組織の作り方担当14:00 - 17:00)Zoomセミナー
多くの方にご参加いただきありがとうございました。
経営層・事業部門への知的財産の貢献度評価と効果的な報告の仕方
2020年10月7日(水) 10:00~17:00
【第3部】経営層、事業部に知財活動、貢献度を報告できる組織の作り方担当14:00 - 17:00)Zoomセミナー
多くの方にご参加いただきありがとうございました。
You Tube で配信されている「知財実務オンライン」に登壇しました。
10月1日(18:30-20:21)に、You Tube で無料配信されている、知財実務オンライン(第17回)「共同開発・知的財産で会社を元気にする ~共同開発・契約のコツ、特許出願大幅増・質向上のコツ~」に、よろず知財戦略コンサルティング 代表 萬 秀憲が登壇しました。アーカイブ視聴できます。
セミナータイトル:共同開発・知的財産で会社を元気にする ~共同開発・契約のコツ、特許出願大幅増・質向上のコツ~
日時:2020年10月1日(木) 18時30分~20時21分
場所:You Tubeによるオンライン配信
https://www.youtube.com/watch?v=xU9G0fc_wzI
講師:萬 秀憲
主催:知財実務オンライン
詳細:無料で、ライブ視聴、及び、アーカイブ視聴できます
「知財実務オンライン」は、マクスウェル国際特許事務所 パートナー弁理士:加島 広基さんと特許業務法人IPX代表弁理士CEO:押谷 昌宗さんが司会を務め、今年の6月から行っているチャネルです。知財業界のゲストの講演に加え、2人の司会者とのディスカッションに加え、視聴者の皆様からのリアルタイムのご質問にも答える「相互」スタイルのウェビナーを配信しており、知財部向けの話がメインで、チャンネル登録者数 690人とのこと。毎週木曜日18時30分からのライブのほかに、そのアーカイブも視聴できます。過去のアーカイブも無料で視聴できます。
10月1日(18:30-20:21)に、You Tube で無料配信されている、知財実務オンライン(第17回)「共同開発・知的財産で会社を元気にする ~共同開発・契約のコツ、特許出願大幅増・質向上のコツ~」に、よろず知財戦略コンサルティング 代表 萬 秀憲が登壇しました。アーカイブ視聴できます。
セミナータイトル:共同開発・知的財産で会社を元気にする ~共同開発・契約のコツ、特許出願大幅増・質向上のコツ~
日時:2020年10月1日(木) 18時30分~20時21分
場所:You Tubeによるオンライン配信
https://www.youtube.com/watch?v=xU9G0fc_wzI
講師:萬 秀憲
主催:知財実務オンライン
詳細:無料で、ライブ視聴、及び、アーカイブ視聴できます
「知財実務オンライン」は、マクスウェル国際特許事務所 パートナー弁理士:加島 広基さんと特許業務法人IPX代表弁理士CEO:押谷 昌宗さんが司会を務め、今年の6月から行っているチャネルです。知財業界のゲストの講演に加え、2人の司会者とのディスカッションに加え、視聴者の皆様からのリアルタイムのご質問にも答える「相互」スタイルのウェビナーを配信しており、知財部向けの話がメインで、チャンネル登録者数 690人とのこと。毎週木曜日18時30分からのライブのほかに、そのアーカイブも視聴できます。過去のアーカイブも無料で視聴できます。
9月15日のZoomセミナーが無事終了しました。
知財戦略を遂⾏するために押さえておきたい3スキル〜①戦略策定②組織づくり
③特許棚卸 第1部 事業部門/研究開発部門の課題解決のための知財戦略の作り⽅
2020年9月15日(火) 13:00~16:30(第1部は13:00 - 14:00)Zoomセミナー
多くの方にご参加いただきありがとうございました。
知財戦略を遂⾏するために押さえておきたい3スキル〜①戦略策定②組織づくり
③特許棚卸 第1部 事業部門/研究開発部門の課題解決のための知財戦略の作り⽅
2020年9月15日(火) 13:00~16:30(第1部は13:00 - 14:00)Zoomセミナー
多くの方にご参加いただきありがとうございました。
書籍「“後発で勝つ”ための研究開発・知財戦略の立て方、進め方」出版のお知らせ
9月末に、萬秀憲が執筆者の一人となっている書籍「“後発で勝つ”ための研究開発・知財戦略の立て方、進め方」が出版されました。(第9章第2節を執筆、著者紹介割引;2割引きで購入可能とのこと。ご希望の方はcontact@yorozuipsc.comまでご連絡いただければ、著者紹介割引申込書をメールで送付します。)
https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2064.htm
https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2064.htm
9月15日のセミナーがZoomセミナーに変更されました。
知財戦略を遂⾏するために押さえておきたい3スキル〜①戦略策定②組織づくり
③特許棚卸 第1部 事業部門/研究開発部門の課題解決のための知財戦略の作り⽅
2020年9月15日(火) 13:00~16:30(第1部は13:00 - 14:00)Zoomセミナー
・URL:https://www.tech-d.jp/seminar/show/4937
知財戦略を遂⾏するために押さえておきたい3スキル〜①戦略策定②組織づくり
③特許棚卸 第1部 事業部門/研究開発部門の課題解決のための知財戦略の作り⽅
2020年9月15日(火) 13:00~16:30(第1部は13:00 - 14:00)Zoomセミナー
・URL:https://www.tech-d.jp/seminar/show/4937
コロナ禍で新規感染者が増加していることから、9月15日に予定されていたセミナーがオンラインセミナーになりました。
Zoomセミナーのため、好きな場所で受講でき、見逃し・復習用として、配信動画の録画を視聴できるとのことです。
(テキストはPDFデータのダウンロード)
Zoomセミナーのため、好きな場所で受講でき、見逃し・復習用として、配信動画の録画を視聴できるとのことです。
(テキストはPDFデータのダウンロード)
書籍「共同研究開発の進め方、契約のポイント」出版のお知らせ
7月末に、萬秀憲が執筆者の一人となっている書籍「共同研究開発の進め方、契約のポイント~発明の帰属、開発費用の分担、秘密保持契約、不実施補償、共同出願、プロジェクトの中止・清算~」が出版されました。(第5章 第1節 大学と企業との共同研究開発におけるトラブル事例とトラブル未然防止策」を担当、著者紹介割引;2割引きで購入可能とのこと。ご希望の方はご連絡ください。contact@yorozuipsc.comまでご連絡いただければ、著者紹介割引申込書をメールで送付します。)
https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2060.htm
https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2060.htm
ブログの紹介
8月31日 AIが研究・執筆・査読のすべてを担う異色の学会
8月30日 不二製油の新中期経営計画で知財戦略はどう変わるか?
8月30日 令和8年度 特許特別会計概算要求のポイント
8月29日 Perplexityがメディアに収益を分配すると表明
8月29日 Anthropicと作家が著作権侵害裁判で和解案に合意
8月28日 ROICスプレッド経営が知的財産戦略に与える影響
8月28日 日本企業のROICとROICスプレッド
8月27日 朝日新聞と日経新聞がPerplexityを著作権侵害で提訴
8月26日 北海道大学サマーセミナー2025四日目
8月26日 AIは特許発明者になれるのか?
8月25日 北海道大学サマーセミナー2025三日目
8月25日 高成長が続く中国ロボット産業
8月25日 DeepSeek V3.1の波紋
8月24日 北海道大学サマーセミナー2025二日目
8月24日 日本特許庁における生成AIの活用状況
8月24日 中国特許庁における生成AIの活用状況
8月23日 欧州特許庁における生成AIの活用状況
8月23日 北海道大学サマーセミナー2025
8月23日 米国特許商標庁(USPTO)における生成AI活用
8月23日 旭鉄工の生成AI活用
8月22日 「企業価値担保権」施行に対する銀行の対応
8月22日 知財実務オンライン「生成AI時代の新たな標準業務工程の試み 」
8月21日 令和5年(行ケ)第10078号判決 発明者の認定
8月20日 シルバニアファミリー不適切動画裁判、エポック社が和解
8月20日 三井物産、量子コンピューターの新研究用プラットフォームを発表
8月19日 反論成功率から「拒絶理由の併せ打ち」について分析
8月19日 そーとく日記の連載「阻害要因という誤謬」
8月19日 知的財産や生産設備のデータ提供を強いる事例調査
8月18日 企業の経営戦略と知財の融合を行うビジネスアーキテクト
8月17日 人工知能が発明した人工知能技術が特許査定
8月17日 「RAG(検索拡張生成)」が幻滅期に
8月17日 Claude Opus 4.1の評価・評判
8月16日 Grok 4 Heavyの性能
8月16日 Gemini 2.5 Pro Deep Thinkの性能
8月16日 ChatGPT-5 Proが知財部門の商標業務にもたらす新たな可能性
8月16日 ChatGPT-5 Proが意匠関連業務にもたらす新たな可能性
8月16日 ChatGPT-5 Proが企業の著作権関連業務にもたらす影響
8月16日 GPT-5 Proによる特許侵害調査の新機能と業務効率向上
8月15日 日本最大のCNF複合樹脂の商用プラントが稼働
8月15日 除くクレームの限界についての検討(パテント誌)
8月15日 GPT-5 Proによる特許価値評価業務の新機能と改善点
8月15日 ChatGPT-5 Proがもたらしたパラメータ特許無効化業務への革新
8月15日 ChatGPT-5 Proがもたらす知財権活用業務の進化
8月15日 ChatGPT-5 Proによる知財ROIC評価業務の進化
8月15日 ChatGPT-5 Proが企業価値創造プロセス分析にもたらす新たな可能性
8月14日 短期間で特許化可能なアイデアを量産するIprova
8月14日 Gemini 3.0に関するリーク情報、噂
8月14日 ChatGPT-5 Proによる特許中間処理業務の進化 ~GPT o3 Proとの比較~
8月14日 ChatGPT-5 Proによる発明創出支援 – GPT o3 Proからの飛躍
8月14日 ChatGPT-5 Proが変える戦略的特許出願業務
8月13日 NTTデータとグーグルが「AIエージェント」を共同開発
8月13日 ChatGPT-5 Proの知能指数(Mensa Norway)
8月13日 ChatGPT-5 Proによる知財戦略立案業務の革新
8月12日 2025 知財・情報フェア&コンファレンス 出展者プレゼンテーション
8月12日 ChatGPT-5 ProによるIPランドスケープ業務の高度化・効率化
8月11日 ChatGPT-5 Proが特許調査業務にもたらす新たな可能性
8月11日 着実に進歩したものの期待を超えるには至らなかった新型モデルGPT-5
8月11日 特許実施率をKPIとする事業連動型知財戦略の是非
8月11日 防衛的・受動的・リスク回避型の特許戦略の是非
8月11日 NTTデータとMistral AIの包括的提携
8月10日 ChatGPT-5 Proによる知的財産業務の改善可能性
8月10日 「自社特許を狭く解釈し、他社特許を広く解釈する」ダブルスタンダード
8月10日 GPT-5 ProとGemini 2.5 Pro Deep Thinkの徹底比較
8月10日 GPT-5発表後OpenAIの優位性が低下、Googleへの期待増
8月 9日 GPT-5、GPT-5 Thinking、GPT-5 Pro の比較
8月 9日 ChatGPT-5とOpenAI o3の比較
8月 9日 OpenAIがChatGPT-5をリリース
8月 9日 生成AIの学習支援モード
8月 8日 知的財産関連業務におけるClaude Opus 4.1の可能性
8月 8日 Anthropic Claude Opus 4.1
8月 8日ゲーム企業の“生成AI活用”
8月 7日 OpenAI、「GPT-5」を8月8日(金)午前2時発表へ
8月 7日 OpenAIオープンウェイト言語モデルによる知財関連業務の変化
8月 7日 OpenAIのオープンウェイト言語モデル
8月 6日 清水建設 自社特許技術を社外に開放
8月 6日 三井住友FGの「AI―CEO」
8月 5日 キリンHD「AI役員 CoreMate」を導入
8月 4日 EUのAI法施行
8月 3日 強化推論モード「Gemini Deep Think」登場
8月 3日 ブリヂストンの知財ROIC深堀り
8月 2日 エンジニアAIエージェント
8月 1日 R&D投資増額の効果発現時期
7月31日 知財・無形資産への投資効果が顕在化するまでの期間
7月30日 PatentScore: LLM生成特許クレームの多次元評価
7月29日 ビデオゲームの企業別特許総価値でソニーGが2位、任天堂が5位
7月29日 東京地裁「糖質カット炊飯器」への消費者庁措置命令を取消す判決
7月28日 顧客対応AIエージェント
7月28日 購買AIエージェント
7月27日 稼ぐ力の強化に向けた知財・無形資産戦略
7月27日 IPで世界中を熱狂させるKADOKAWA
7月27日 営業AIエージェント
7月26日 経理AIエージェント
7月26日 バランスシートに現れない特許資産の定量評価
7月25日 トランプ大統領が署名したAI分野の大統領令
7月25日 企業の法務部門におけるAIエージェントの活用
7月25日 生成AIは単なるチャットツールから社会を変革するパートナーへ
7月24日 著作物を用いたAI学習はフェアユースとして保護されるべきか
7月24日 RAG導入が思い通りに進んでいない
7月23日 マーケティングAI Agentの進化
7月23日 特許権活用業務でのChatGPT Agentの活用
7月22日 ChatGPT AgentのIPランドスケープ業務での活用
7月22日 ChatGPT Agentの特許調査業務での活用
7月21日 USPTO、特許審査におけるAI活用を義務化
7月21日 ChatGPT Agentの評判
7月20日 生成AIを活用した知財業務の高付加価値化
7月20日 アサヒGHDのBAC戦略と知財戦略
7月20日 アサヒGHDのBAC戦略
7月19日 ロート製薬メディカル事業積極投資に伴う知財戦略の変化
7月19日 ロート製薬がメディカル事業に積極投資
7月19日 年6回収穫も可能な水耕稲作
7月18日 日本ガイシの新規事業創出
7月17日 孫正義氏「10億AIエージェント、年内に実現」
7月17日 知財実務オンライン『投資家との対話』の成功の鍵
7月17日 ブリヂストンの新規分野への取り組み
7月16日 ブリヂストンとIT企業との戦略的提携
7月16日 住友ゴムとNECが戦略的パートナーシップを締結
7月15日 LexisNexis PatentSight+ Summit 2025「知財領域におけるAIの活用」
7月15日 日本AI戦略の未来
7月14日 研究開発調査1年を1週間に短縮する「Memory AI」
7月13日 電通グループ「dentsu Japan AIセンター」発足
7月12日 生成AIはエージェント時代からイノベーターの時代へ
7月12日 EUがAI規制法順守の行動指針案を公表
7月12日 xAIが発表した最新AIモデル「Grok 4」
7月11日 「パラメータ発明」の進歩性判断
7月10日 「除くクレーム」進歩性判断
7月 9日 AIリサーチ市場で広がる“第二の波”
7月 8日 推論モデル生成AIの時代
7月 7日 弁理士業界におけるAIによる業務自動化
7月 6日 ハーバード大学・MIT・シカゴ大学論文「ポチョムキン理解」
7月 6日 KADOKAWAの知財戦略
7月 5日 生成AIとDeepResearch技術を活用したIPランドスケープ
7月 5日 DeepResearch最新活用術
7月 4日 Deep Researchとは?従来のAI検索との違い
7月 3日 (株)レイテック 破産手続き開始決定
7月 3日 弁理士の日記念ブログ企画2025「生成AIと知財業界」
7月 2日 コンテンツ産業関連、AI搭載ロボット産業関連の楽天モバイル出願特許
7月 2日次世代の日本の勝ち筋に楽天モバイルはどう貢献できるか
7月 2日 楽天モバイルの知財活動
7月 1日 コンテンツ産業関連、AI搭載ロボット産業関連のレゾナック出願特許
7月 1日 次世代の日本の勝ち筋にレゾナックはどう貢献できるか
6月30日 生成AI作成画像等を外部向けに公開する場合の注意点
6月30日 化学分野における研究開発を加速するためのAI活用ツール
6月30日 かゆみ改善薬に関する用途特許侵害
6月29日 コンテンツ産業関連、AI搭載ロボット産業関連のブリヂストン出願特許
6月29日 次世代の日本の勝ち筋にブリヂストンはどう貢献できるか
6月29日 ブリヂストン 生成AIで予測精度が向上、開発期間短縮
6月29日 コンテンツ産業関連、AI搭載ロボット産業関連の旭化成出願特許
6月29日 次世代の日本の勝ち筋に旭化成はどう貢献できるか
6月28日 次世代の日本の勝ち筋に東京大学はどう貢献できるか
6月28日 東京大学知的財産戦略の分析と新戦略の提案
6月28日 次世代の日本の勝ち筋は?
6月27日 産業爆発が2027年に始まる可能性
6月27日 ロボット本体のGPU上で完全にローカルに動作するAIモデル
6月26日 悪魔の「除くクレーム」
6月25日 除くクレームの限界
6月25日 企業は従来のヒト主体からAIエージェント主体となる
6月24日 世界の特許事務所・企業知的財産部門の生成AI活用状況
6月24日 企業価値担保権(事業全体を対象とする担保制度)
6月23日 日立製作所「Hitachi Investor Day 2025」
6月23日 浜松ホトニクスと東京精密の特許訴訟
6月23日 サントリーの知財戦略
6月22日 島津製作所知的財産部門における生成AI活用(2025年6月)
6月22日 2025SNAが日本企業に与える影響
6月22日 戸田建設の新中期経営計画で知財戦略はどう変わるか?
6月21日 AIエージェント NTT Com「知財文書作成エージェント」
6月20日 日本経済がインフレへ移行する中での企業知財部門の変化
6月19日 日本経済がインフレへ移行する中での企業経営の変化
6月18日 エア・ウォーターの新中期経営計画で知財戦略はどう変わるか?
6月17日 参天製薬の新中期経営計画で知財戦略はどう変わるか?
6月17日 ソフトバンクG、1万件超のAI関連出願 その狙いと影響
6月16日 タチエスの新中期経営計画で知財戦略はどう変わるか?
6月16日 一般社団法人 知財・無形資産ガバナンス協会 (IPIAGA)
6月16日 生成AIが提案「納豆ビジネス月商1億円達成ロードマップ」
6月15日 イノベーション拠点税制(イノベーションボックス税制)
6月15日 生成AIに関する研究と特許出願の状況
6月15日 東ソー 新中期経営計画で知財戦略はどう変わるか?
6月14日 スクウェア・エニックス 新中期経営計画で知財戦略はどう変わるか?
6月13日 「のれん」償却制度の見直しにより想定される影響
6月13日 穏やかなシンギュラリティ
6月13日 佐藤食品工業 中期経営計画「Vision 2028」で知財戦略はどう変わるか?
6月12日 AI時代の情報検索技術
6月12日 九州電力「九電グループ経営ビジョン 2035」で知財戦略はどう変わるか?
6月11日 AI Samurai、トヨタテクニカルディベロップメントの完全子会社に
6月11日 5年後に、弁理士の今の仕事のうち何割がなくなるか?
6月10日 5年後に、企業知財部員の今の仕事のうち何割がなくなるか?
6月10日 マーケターの今の仕事、8割は5年後なくなる
6月 9日 AI論文検索ツールをどう使い分ける?
6月 9日 医療分野での生成AIの活用
6月 9日 新聞協会:生成AIにおける報道コンテンツの保護に関する声明
6月 8日 生成AIは1億倍の記憶能力を持つオウムか?
6月 8日 令和6年(行ケ)第10013号 新規事項追加
6月 7日 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会第54回小委員会
6月 7日 知的財産推進計画2025に関する報道や専門家の反応
6月 7日 企業の社内各部門での生成AI活用状況
6月 6日 知的財産推進計画2025~IP トランスフォーメーション~
6月 5日 知財部門での生成AI 活用は、他部門に比べて遅れている?
6月 5日 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(AI法)
6月 5日 UBE株式会社の新中期経営計画で知財戦略はどう変わるか?
6月 4日 外国産米を輸入したときの2025年下半期~2026年の米価格を予測
6月 4日 東京エレクトロン、特許成長力で1位
6月 3日 2025年下半期~2026年の米需給動向と価格を予測
6月 3日 日産化学新中期経営計画『Vista2027 StageⅡ』で知財戦略はどう変わるか?
6月 2日 経営戦略立案における生成AI活用
6月 2日 Sakana AIの「ダーウィン・ゲーデルマシン」
6月 1日 「ChatGPT Pro」「Gemini Ultra」「Claude Max」
6月 1日 テレビ東京の新中期経営計画で知財戦略はどう変わるか?
6月 1日 生成AIで競合を分析してビジネス戦略を立案
5月31日 科学的発見を自動化するマルチエージェントシステム「Robin」
5月31日 Claude Opus 4 と ChatGPT o3(OpenAI o3) との比較
5月31日 三菱製紙の新中期経営計画で知財戦略はどう変わるか?
5月30日 「企図する因果パス」 理研ビタミンのケース
5月30日 理研ビタミンの新中期経営計画で知財戦略はどう変わるか?
5月29日 「企図する因果パス」 森永乳業のケース
5月29日 LexisNexis PatentSight+ Summit 2025
5月29日 森永乳業の新中期経営計画で知財戦略はどう変わるか?
5月28日 「企図する因果パス」徹底解説
5月27日 生成AIを活用したIPランドスケープの最新動向
5月26日 生成AIを活用した特許分析の最新動向
5月25日 ⽣成A I特許分析GPT s
5月24日 TDKのグローバル知財ガバナンス 挑戦と課題
5月24日 アミノサイエンス®を核とした知財戦略の進化と価値創造
5月24日 未来を拓く知財人財とは?― 次世代を育てる戦略と視点
5月23日 京セラの知的財産部門における生成AIの活用
5月23日 島津製作所の知的財産部門における生成AIの活用
5月23日 旭化成の知的財産部門における生成AIの活用
5月22日 京都大学のGoogleテナントでの生成AI活用に向けた取り組み
5月22日 ニチレイの新中期経営計画で知財戦略はどう変わるか?
5月21日 Google DeepMindの「AlphaEvolve」
5月21日 持田製薬の新中期経営計画で知財戦略はどう変わるか?
5月20日 明電舎の新中期経営計画で知財戦略はどう変わるか? 5月19日 人工知能の発展におけるLLM層とアプリケーション層の役割
5月19日 アキレスの新中期経営計画で知財戦略はどう変わるか?
5月19日 シャープの新中期経営計画で知財戦略はどう変わるか?
5月18日 京王電鉄の新中期経営計画で知財戦略はどう変わるか?
5月18日 住友金属鉱山の中期経営計画で知財戦略はどう変わるか?
5月17日 AlphaEvolve: AIが全く新しい科学的発見を生み出せることを実証
5月17日 産業爆発はいつどのように起きるのか
5月17日 ノリタケの新中期経営計画で知財戦略はどう変わるか?
5月17日 令和6年度 我が国の知的財産制度が経済に果たす 役割に関する調査報告書
5月16日 ヤマハ株式会社の新中期経営計画で知財戦略はどう変わるか?
5月16日 生成AIを用いた文献調査ツールの動向
5月15日 JFEホールディングス「JFE ビジョン 2035」・第8次中期経営計画で知財戦略はどう変わるか?
5月14日 日本テレビの新「経営ビジョン」「中期経営計画 2025-2027」で知財戦略はどう変わるか?
5月13日 三井ハイテック新中期経営計画で知財戦略はどう変わるか?
5月12日 はままつ知財研究会第109回知財問題研究部会(IP部会)
5月12日 マルハニチロ新長期ビジョン・新中期経営計画で知財戦略はどう変わるか?
5月11日 村田製作所のROIC経営見直し
5月11日 将来見ぬROIC経営に落とし穴
5月11日 ヤマハ発動機新中期経営計画で知財戦略はどう変わるか?
5月11日 スズキ新中期経営計画で知財戦略はどう変わるか?
5月10日 ナブテスコ新中期経営計画で知財戦略はどう変わるか?
5月10日 ライオン新中期経営計画で知財戦略はどう変わるか?
5月 9日 三菱鉛筆新中期経営計画で知財戦略はどう変わるか?
5月 8日 キッコーマン新中期経営計画で知財戦略はどう変わるか?
5月 7日 富士通における知財活用の取り組み
5月 7日 パーパスに基づくパナソニック知財の取組み
5月 6日 日立製作所 新経営計画「Inspire 2027」で知財戦略はどう変わるか?
5月 6日 東宝株式会社「中期経営計画 2028」で知財戦略はどう変わるか?
5月 6日 OpenAI o3を使うことで知的財産業務はどう変わるか?
5月 5日 goodbye, GPT-4. you kicked off a revolution.
5月 5日 オリエンタルランド「2035長期経営戦略」で知財戦略はどう変わるか?
5月 5日 東京メトロ 新中期経営計画「Run!~次代を翔けろ~」で知財戦略はどう変わるか?
5月 5日 「NotebookLM」の音声概要機能
5月 4日 OpenAI o3のレベル3該当性およびレベル4到達時期
5月 4日 コマツ 新中期経営計画「Driving value with ambition 価値創造への挑戦」で知財戦略はどう変わるか?
5月 4日 「企業成長の道筋~投資家との対話の質を高める知財・無形資産の開示~」
5月 3日 「「稼ぐ力」を強化する取締役会5原則」と「「稼ぐ力」のCGガイダンス」
5月 3日 住友化学 新中期経営計画「Leap Beyond ~成長軌道へ回帰~」で知財戦略はどう変わるか?
5月 2日 知財実務オンライン:「知財は人を育てる!」
5月 2日 王子ホールディングス「中期経営計画2027(骨子)」で知財戦略はどう変わるか?
5月 1日 日本触媒「中期経営計画 2027」で知財戦略はどう変わるか?
4月30日 ニデック新中期経営計画「Conversion 2027」で知財戦略はどう変わるか?
4月29日 化粧品油剤世界市場における日清オイリオの市場シェア拡大の可能性
4月29日 特許分析からの具体的な特許出願パッケージ提案例
4月28日 特許分析からの技術開発・特許創出戦略提言
4月27日 生成AIによる日清オイリオの特許技術ポートフォリオ分析
4月27日 日清オイリオ新中期経営計画「Value UpX」で知財戦略はどう変わるか?
4月26日 生成AIによる特許技術ポートフォリオ分析
4月25日 アントレプレナーシップ教育の一環として行う知財教育
4月24日 生成AIを利用したデザイン創作の意匠法上の保護の在り方
4月23日 第53回特許制度小委員会
4月22日 令和6年(行ケ)第10049号審決取消請求事件 進歩性
4月21日 主要AI企業のDeep Research機能比較分析
4月20日 スズキ、社長と特許発明社員の座談会
4月19日 松尾研発スタートアップ株式会社エムニによる「AI特許ロケット」
4月18日 VALUENEXのSaaS型解析ツール「Radar QFD」
4月18日 生成AIとの「壁打ち」で、新たな発明を創出する方法
4月17日 OpenAIの新モデル「o3」と「o4-mini」
4月17日 生成AIとTRIZの融合による発明創出
4月16日 ニッスイ中期経営計画「GOOD FOODS Recipe2」で知財戦略はどう変わるか?
4月15日 AIで生成した事業アイデア700を万博「住友館」で披露
4月15日 第52回特許制度小委員会議事録
4月14日 2025年、人々は生成AIを実際にどのように使用しているか
4月14日 生成AIを活用した他社特許技術牽制戦略
4月13日 旭化成「中期経営計画2027」で知財戦略はどう変わるか?
4月13日 「AI 2027」
4月13日 次世代AIエージェント比較
4月12日 ソフトバンクの大量特許出願が4月に約1万件公開
4月11日 特許出願書類作成を生成AIで効率化する『ユアサポAI』
4月11日 生成AIを活用した知財戦略の策定方法
4月11日 経営視点で再定義する新規事業の”未財務”的価値
4月10日 Deep Research で Gemini 2.5 Pro Experimental 利用可能に
4月10日 知財活動のROICへの貢献
4月 9日 生成AI時代の経営戦略 DeNAの第2の創業
4月 9日 AI応用研究紹介YouTube動画
4月 8日 AIエージェント「Genspark Super Agent」
4月 8日 OpenAI「o3」、「o4-mini」、「GPT-5」
4月 7日 Metaのネイティブマルチモーダル AI「Llama 4」
4月 7日 生成AI市場のシェア獲得競争
4月 6日 4月に入って5000件以上公開:ソフトバンクの大量特許出願戦略
4月 5日 「グローバル知財戦略フォーラム2025」の開催報告書
4月 5日 イノベーション拠点税制(イノベーションボックス税制)
4月 4日 特許庁が「除くクレーム」に関する留意点を公表
4月 3日 古河電工が生んだ新製品の裏に特許分析あり
4月 3日 知財高裁大合議判決令和5年(ネ)第10040号 判決全文
4月 2日 実は今が始めどき!「生成AI×法務」の知らない世界
4月 2日 発明を発掘するのではなく発明を開発する
4月 1日 米国の特許競争力指標「US-YK値」
4月 1日 INPITが知財支援人材スキルマップを作成
3月31日 特許庁ステータスレポート2025
3月30日 ChatGPTの画像生成機能で「ジブリ風」イラストの問題点
3月30日 生成AIを活用した特許明細書作成支援サービス比較
3月30日 DeepIPの特許草案作成支援AIアシスタント
3月30日 2025年は人型ロボット元年
3月29日 Gemini 2.5 TRACKING AI Mensa NorwayでIQ130
3月29日 デジタル庁が生成AIの調達・利活用に係るガイドライン(案)を公表
3月29日 生成AI利活用ガイドライン
3月28日 ChatGPTの新しい画像生成機能「4o Image Generation」
3月27日 Gemini 2.5 最もインテリジェントな AI モデル
3月27日 SDIにおける特許調査の考え方と運用管理
3月26日 株価2年で4倍のSWCCの知財・無形資産に関する取組み
3月25日 審判実務者研究会報告書2024
3月24日 生成AIがニュースコンテンツを正確に検索し引用する能力
3月24日 企業経営における知財・無形資産の活用
3月24日 「人的資本経営」への道筋
3月23日 技術経営とROIC経営の両輪でイノベーション:オムロン
3月22日 知財高裁大合議判決令和5年(ネ)第10040号 豊胸用組成物
3月21日 令和6年(行ケ)第10005号 明確性
3月20日 日本のスタートアップが開発したAI検索エンジン Felo AI
3月20日 LexisNexis® PatentSight+「AI Assistant」
3月19日 業界初のAI搭載IP管理ソフトウェア(IPMS):「Equinox」
3月18日 第4回日経統合報告書アワード 総合グランプリ3社
3月17日 構想委員会での「AI Samurai」説明内容
3月16日 高石秀樹弁護士の今後の知財活動を推論モデルで予測
3月16日 令和6年(ネ)第10026号 特許権侵害行為差止等請求控訴事件
3月15日 【知財戦略】国際競争力を維持・強化
3月15日 AIによるオンライン語学学習、生成AIとRAGを用いた研究支援システムなど
3月14日 Gemini Deep ResearchがGemini 2.0へアップグレード
3月14日 AGC 生成AIにより、2024年に11万時間以上を創出
3月14日 統合報告書に記載された知財KPIの事例と傾向
3月13日 “100%”AI生成の論文が査読通過:Sakana AI
3月13日 Manusを含めたDeep Research AIの各社比較
3月12日 法律としての知的財産法
3月12日 中国発AIエージェント「Manus」
3月11日 「サマリア」の今後の開発ロードマップ
3月11日 金融庁、AIディスカッションペーパーを公表
3月11日 Deep Research、論文検索AI、AIエージェント
3月11日 大手飲料メーカーの生成AI活用比較
3月11日 イノベーション投資としての知的財産
3月10日 検索特化型生成AI Deep Research ツール
3月10日 特許審査におけるAI活用は本当に喫緊の課題
3月 9日 企業の知的財産部門における生成AI活用事例
3月 9日 企業の情報システム部門における生成AI活用事例
3月 9日 住友電工がグループ全社規模のRAG基盤を構築
3月 9日 イノベーション創出のための特許庁の取組
3月 9日 ビジネス変化の波を乗りこなせ!生成AI時代のビジネス戦略
3月 8日 孫正義氏「超知能AIは⽇本の⼤企業から始まる」
3月 8日 企業の研究開発部門における生成AI活用事例
3月 8日 AI技術の発達を踏まえた特許制度上の適切な対応
3月 7日 DNPが研究開発部門等に「ChatGPT Enterprise」導入
3月 7日 企業のマーケティングにおける生成AI活用事例
3月 7日 Microsoftの営業部門向けAIエージェント
3月 6日 企業の営業活動における生成AI活用事例
3月 6日 WIPO 日本事務所 Webinar「特許とAI」
3月 5日 AIを使えない人はほっておけ
3月 5日 製造業における顧客対応部門での生成AI活用事例
3月 4日 ⽣成AIを特許のスクリーニングに活⽤する⽅法
3月 4日 日本企業における生成AIの利用率
3月 4日 大学生の約半数が生成AIを継続的に利用している
3月 3日 Claude 3.7 Sonnetの凄さ
3月 2日 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案
3月 2日 サマリアの分類支援機能
3月 1日 不利益がある発明、成功確率が低い発明、効果が低い発明・・・
3月 1日 最後の非推論モデル「ChatGPT 4.5(GPT-4.5)」の登場
2月28日 デクセリアルズの知的財産活動
2月28日 カプコンの知的財産活動
2月27日 アシックスの知的財産活動
2月26日 旭化成の用途探索支援AI
2月25日 AIの利用・開発に関する契約チェックリスト
2月25日 拡張思考に対応した「Claude 3.7 Sonnet」
2月24日 AIが戦略策定をどう変えるのか
2月24日 生成AIを活用した知財戦略の策定方法
2月23日 Gemini 2.0 を使用して構築された「AI co-scientist 」
2月22日 ブランド価値による日本ブランドのランキングTop100
2月21日 6つの「Deep Research」を比較
2月20日 世界のイノベーションをリードする企業100社
2月19日 進化したappia-engine:生成AIによる特許明細書作成
2月19日 AI活用がもたらす発明創造プロセスのパラダイムシフト
2月18日 サマリア、Appia-engine、AI Samurai、Axelidea、AI孔
2月17日 知財・無形資産ガバナンス表彰(2024年度)
2月16日 Grok 3 :Smartest AI on Earth.
2月15日 知的財産推進計画2025に向けた第3回構想委員会の検討
2月14日 LIXILの知的財産戦略
2月13日 Patentfield AIR, Summaria, Tokkyo AI, AI Samuraiの比較
2月12日 Deep Research丸投げは非効率?
2月12日 特許の崖という業界の常識と戦う塩野義製薬
2月11日 令和6年(行ケ)第10023号「情報処理端末」
2月10日 サマリア新機能:包袋管理機能、OCR機能、文書整形機能
2月10日 令和5年(行ケ)第10132号「地盤固結材および地盤改良工法」
2月 9日 令和6年(行コ)第10006号 出願却下処分取消請求控訴事件
2月 9日 生成AIを用いた特許文書品質向上
2月 9日 NTTの生成AI事業
2月 8日 日中イノベーション共創
2月 8日 Cool Galapagos as a Competitive Advantage
2月 8日 マイクロ波化学の知的財産活用レベル
2月 8日 三菱電機の知的財産活用レベル
2月 7日 ロート製薬の知的財産活用レベル
2月 6日 知財活動のROICへの貢献
2月 6日 サントリーの知的財産活用レベル
2月 6日 世界で最もAIを開発・活用しやすい国のAI法
2月 5日 2025 ライフサイエンス知財フォーラム
2月 5日 ブリヂストンの知的財産活用レベル
2月 5日 社内に眠る技術を生成AIが特許出願提案:「AI孔明」
2月 5日 大企業向けの最先端AI「クリスタル・インテリジェンス」
2月 4日 OpenAI「Deep Research」:ソニーのエンターテインメントおよび AI 分野における知財戦略
2月 4日 ナブテスコの知的財産活用レベル
2月 3日 生成AI 最新高性能モデルの比較
2月 3日 ユニ・チャームの知的財産活用レベル
2月 2日 ソフトバンクの知的財産活用レベル
2月 1日 リクルートの知的財産活用レベル
1月31日 オムロンの知的財産活用レベル
1月30日 アステラス製薬の知的財産活用レベル
1月29日 信越化学工業の知的財産活用レベル
1月28日 村田製作所の知的財産活用レベル
1月27日 非財務指標と短期財務指標バランス良い活用
1月26日 知財活動のROICへの貢献:計算法、オムロン、荏原製作所
1月25日 ファナックの知的財産活用レベル
1月24日 コニカミノルタの知的財産活用レベル
1月24日 ChatGPTが東大合格レベルに
1月23日 味の素の知的財産活用レベル
1月22日 エーザイの知的財産活用レベル
1月21日 武田薬品の知的財産活用レベル
1月20日 パナソニックの知的財産活用レベル
1月19日 旭化成の知的財産活用レベル
1月18日 AI技術の発達を踏まえた特許制度上の適切な対応
1月18日 知的財産活用レベル:トヨタ自動車、花王、富士フイルム、資生堂
1月17日 知的財産活用レベル:日立製作所、キーエンス
1月16日セミナー「ChatGPTを使って中間対応案を検討する」
1月15日 知財・無形資産で日本企業の価値向上と持続的成長を如何にして実現するか
1月15日 大学1年生の数学(線形代数)は生成AIに理解できるのか
1月14日 知的財産活用レベルがレベル5「ビジョン(未来創造)」の企業
1月14日 公開情報を活用して知財情報開示の改善の方向を考える
1月13日 知的財産を「攻め」の武器に:企業の未来を拓く5段階レベル戦略
1月13日 人工生命の誕生
1月13日 RAG活用、製造業でも本格化
1月12日 ソフトバンクグループの成長戦略における知的財産部門の貢献
1月12日 リクルートの成長戦略における知的財産部門の貢献
1月12日 オムロンの成長戦略における知的財産部門の貢献
1月12日 アステラス製薬の成長戦略における知的財産部門の貢献
1月12日 村田製作所の成長戦略における知的財産部門の貢献
1月12日 信越化学工業の成長戦略における知的財産部門の貢献
1月11日 ファナックの成長戦略における知的財産部門の貢献
1月11日 コニカミノルタの成長戦略における知的財産部門の貢献
1月11日 味の素の成長戦略における知的財産部門の貢献
1月11日 エーザイの成長戦略における知的財産部門の貢献
1月10日 武田薬品の成長戦略における知的財産部門の貢献
1月10日 NotebookLM, GPTs, Projects の比較
1月10日 パナソニックの成長戦略における知的財産部門の貢献
1月10日 2024年の生成AIアップデートとAGI、ASI
1月 9日 検索特化型生成AIの使い使い比べ
1月 9日 資生堂の成長戦略における知的財産部門の貢献
1月 9日 富士フイルムの成長戦略における知的財産部門の貢献
1月 9日 トヨタ自動車の成長戦略における知的財産部門の貢献
1月 8日 花王の成長戦略における知的財産部門の貢献
1月 8日 「知財・無形資産の投資・活用戦略の構築・開示・発信」の優れた日本企業
1月 8日 キーエンスの成長戦略における知的財産部門の貢献
1月 8日 人間には簡単でも生成AIには難しい問題
1月 7日 旭化成の成長戦略における知的財産部門の貢献
1月 7日 ソニーの成長戦略における知的財産部門の貢献
1月 6日 生成AIが特許審査において新規性判断基準に与える影響
1月 6日 日立製作所の成長戦略における知的財産部門の貢献
1月 5日 生成AIが特許審査において進歩性判断基準に与える影響
1月 4日 統合報告での特許情報の開示とインタンジブルズ・ミックス
1月 4日 OpenAI o1版『生成AIを活用した特許明細書の書き方』
1月 3日 OpenAI o1版『特許明細書の書き方―初学者向けー』
1月 2日 2025年生成AIをめぐって起きる知財関連の事件を予想
1月 1日 孫正義氏の“ChatGPT壁打ち”が生む新時代の創造力
1月 1日 生成AI進化で2025年日本企業の知的財産業務はどう変わる?
12月31日 2025年に生成AIはどこまで進化するか?
12月31日 パテント・インテグレーション:6件の特許権侵害訴訟提起
12月31日 Sakana AI:人工生命の自動探索を行う「ASAL」
12月30日 特許競争力、三菱ケミカルが首位
12月29日 新たな知財高裁大合議事件
12月28日 初等中等教育における生成AIの利活用に関するガイドライン
12月27日 三井化学が独自開発した生成AI活用特許チャット
12月26日 第12回AI戦略会議&第6回AI制度研究会
12月26日 外部特許事務所での特許明細書作成割合を増やすべきか
12月25日 『VALUE DESIGN SUMMIT 2024』イベントレポート
12月25日 特許サーチャーを知財アナリストに移行させる
12月24日 AI時代の競争力を生む知財エコシステム
12月23日 関西知的財産セミナー「AIと知財」
12月22日 特許検索式作成における生成AIの活用方法
12月22日 OpenAI、新世代モデル「o3」、「o3 mini」を発表
12月21日 新たな推論AIモデル「Gemini 2.0 Flash Thinking」
12月21日 USPTOの特許審査品質向上に向けたAI活用の取り組み
12月20日 特許の審査、サーチにおけるAIの活用
12月19日 旭化成の2024年「無形資産戦略説明会」
12月18日 IPランドスケープ:知財情報をビジネスに役立てる
12月17日 生成AIを使い特許調査の効率と精度を上げる
12月16日 『生成AIの知財業務への活用』―企業知財担当者のための戦略的新基盤
12月15日 OpenAI o1のIQは133?
12月15日 カシオ、不正競争訴訟で中国企業に勝訴
12月14日 第50回特許制度小委員会議事録
12月14日 「知的財産推進計画2025」に向けた検討
12月13日 旭化成の生成AI活用
12月13日 NGB「生成AIを活用して特許公報を読む」第2弾
12月12日 知財実務オンライン:進歩性の重要論点
12月11日 特許の現存率の推移と特許出願件数動向
12月11日 ソフトウェア分野の特許明細書の書き方講座
12月10日 AIが化学業界にもたらす新たな可能性
12月 9日 リコーのプライベートLLMを中核としたDX加速
12月 9日 特許情報を研究開発の現場で使える粒度へまとめ上げる
12月 8日 意匠法における創作者の認定
12月 7日 生成AI技術の発達を踏まえた意匠制度
12月 7日 特許審査・審判で、今、何が起こっているのか
12月 7日 AI関連発明を適切に保護するための考え方
12月 6日 食品知財の黒船
12月 6日 長期投資に役立つ特許情報の読み方
12月 5日 生成AIを活用した事業開発プロセスの効率化と革新
12月 5日 特許法・意匠法・商標法が目指す「産業の発達」
12月 4日 AI技術の事業活用と知財戦略を推進する専門組織
12月 4日 多様な事業へ生成AIの導入を加速する東芝
12月 3日 レゾナックの生成AIを活用した共創型研究開発
12月 3日 生成AIと企業価値創造
12月 2日 NECや日立はかつて「エヌビディア的存在」だった
12月 1日 GoogleとOpenAIの熾烈な性能アップ競争
12月 1日 Chugai AI Assistant R&Dや治験にも生成AI
11月30日 松尾豊教授が語る生成AIの次の10年、「絶望から挑戦へ」
11月30日 生成AI関連サービスが急速に浸透
11月30日 生成AI技術を活用した「AI松下幸之助」
11月29日 意匠(関連意匠・部分意匠・組物・画像)の戦略的活用法
11月29日 生成AIに関する特許権侵害訴訟の追訴提起
11月28日 キリンHD、マーケティング部門から生成AI導入
11月27日 失われた30年とは「知財戦略で敗れた30年」
11月26日 知財実務情報Lab.特許文書の読み方
11月25日 特許庁デジタル戦略202X
11月24日 AI 関連発明の出願 日米欧中韓で日本が最も少ない
11月23日 AI活用が特許調査の作業時間短縮に直結しない
11月23日 生成AI「プロンプト集」は不要
11月22日 著者に聴く!「Patent Information For Victory 」
11月22日 OpenAIの最新GPT-4oが再度1位に浮上
11月21日 特許・実用新案公報×生成 AI 業務効率化と価値向上への取り組み
11月21日 「生成AI Innovation Awards」最優秀賞は中外製薬
11月21日 サマリアの分類支援機能を特許情報分析に活用
11月20日 令和4年(行ケ)第10118号 副引用発明の上位概念化
11月20日 NVIDIA Supercomputing 2024 (SC24)特別講演
11月19日 OpenAI CEO サム・アルトマンが語る生成AIの将来
11月19日 生成AIの知財実務における可能性と課題
11月18日 Google新実験モデル「Gemini-Exp-1114」が世界トップに
11月18日 Patent Information For Victory
11月18日 生成AIが科学的発見とイノベーションに与える影響
11月17日 生成系Alの特許情報活用新パラダイム
11月17日 就業規則や秘密保持誓約書が営業秘密の秘密管理性に与える影響
11月16日 AIが判決を下す日
11月16日 AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめの手引き(権利者向け)
11月15日 一人知財業務で生成AIを味方につける
11月15日 NVIDIA とソフトバンクが推進するAI 産業革命
11月14日 食品業界における知的財産活動
11月14日 「好ましい」という文言を用いると限定解釈される?
11月13日 生成AIによる「技術開発領域可視化システム」
11月12日 「知的財産推進計画 2025」の策定に向けた意見募集
11月12日 2025年にAGI
11月11日 生成 AIは知財創出・強化に繋がる
11月11日 大規模日英特許対訳コーパス
11月10日 弁理士業務への生成AIの活用
11月10日 生成AIを用いた特許文書品質向上
11月 9日 特許情報を活用した技術創造AI
11月 9日 特許庁におけるAIの活用
11月 8日 特許調査における生成AI、サマリアの活用方法
11月 8日 「SoftBank World 2024」孫正義氏特別講演
11月 7日 化学発明における実施例の作成
11月 7日 知財活動をドライブさせる戦略的組織・リーダーシップ(知財実務オンライン)
11月 6日 サーチャーからアナリストへ-企業における IPランドスケープの実践-
11月 6日 生成AIの知財侵害防止へ2026年に意匠法改正
11月 5日 国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明の権利保護
11月 5日 生成AI技術に関連する特許権侵害訴訟 Patentfieldのコメント
11月 4日 生命誕生からChatGPT38億年の創発
11月 4日 日本でもChatGPTの独走状態が続いている
11月 4日 米国生成AIシェア ChatGPTの独走
11月 3日 「ChatTokkyo」を搭載した「プライベートAI特許」
11月 3日 AIエージェントの時代到来
11月 3日 AIが特許を発明する時代
11月 2日 口頭指示で化学実験するロボット研究助手
11月 2日 検索に特化した生成AI
11月 1日 OpenAI 「SearchGPT」の提供開始
10月31日 知財分野での生成AI活用で訴訟勃発
10月31日 Qualified Patent Information Professional(認定特許情報プロフェッショナル)
10月30日 令和5年(行ケ)第10019号「医薬」か「治験薬」かだけの違い
10月30日 技術者・研究者からの知財キャリアパス
10月29日 メタバースからみた生成AIのインパクト
10月28日 「実用段階フェイズ」に到達した生成AIの活用
10月27日 生成AIが学術ジャーナルで果たす役割
10月27日 2024年AI業界の全貌と未来予測
10月26日 NGB知財チャンネル「生成AI×特許調査」
10月26日 東南アジアの知財情報の効率的な調査・収集
10月25日 イノベーションボックス税制で成長の好循環を
10月25日 生成AIは情報市場を壊した?
10月24日 Claude 3.5 Sonnet(New)にプロンプト入力でPCを操作させる機能
10月24日 発明の権利はスタートアップに。KDDIのスタートアップ知財支援
10月23日 Google「NotebookLM」のアップデート
10月23日 自律型AIサービス
10月23日 究極の効率化に向けた知財DX
10月22日 大規模言語モデルのあるべき姿とは?
10月22日 いわゆる「容易の容易」
10月21日 イノベーション拠点税制(イノベーションボックス税制)
10月20日 デザイン分野でのAIイノベーション
10月20日 OpenAI o1の推論能力
10月19日 人間のCEOとAIのCEO
10月18日 AIが生成した発明(「自律的」AI生成物)の取り扱い
10月17日 企業知財人材に必要な実務教育
10月17日 米国に追い抜かれた日本の生成AI活用
10月16日 自社のノウハウを特定・識別する
10月16日 ある会社のノウハウを公開情報から分析する
10月15日 R&D投資効率、日本急落
10月15日 平将明&松尾豊 日本のAI戦略を語り尽くす
10月14日 特許明細書案をClaude 3.5 Sonnet に作成させる
10月14日 特許明細書案をGemini 1.5 Pro に作成させる
10月14日 特許明細書案をOpenAI o1-preview に作成させる
10月14日 特許明細書案をChatGPT-4oに作成させる
10月13日 『天秤AI』使い方・活用事例7選
10月13日 AI各社が小型言語モデル(SLM)を発表 AI業界に生まれる新たな潮流
10月12日 6つの生成AIによるアイデア生成
10月12日 AXELIDEA Patentがパワーアップ
10月11日 日本/欧州/韓国におけるIPランドスケープ(旭化成中村氏)
10月10日 「知的財産推進計画2025」に向けた検討
10月10日 発明から探る「孫正義氏の頭の中」
10月 9日 用途探索手法 : 生成AIとテキストマイニングの比較
10月 9日 サマリア プレゼン「生成AIの特許実務における利活用の最前線」
10月 8日 製造業における生成AI活用
10月 8日 生産現場が注目する「生成AI×オンプレ」
10月 7日 ChatGPTに編集特化機能「Canvas」が追加
10月 7日 教育における生成AIの可能性
10月 6日 2024知財・情報フェア&コンファレンスの入場者数
10月 6日 Patent troll Sable pays up, dedicates all its patents to the public!
10月 5日 「超知性は10年以内」 SoftBank World 2024
10月 5日 生成AIが教育に与える影響
10月 4日 大学での語学教育へのChatGPT活用
10月 4日 本格的な生成AIブームはこれから到来する
10月 3日 知的財産部門の生き残り方
10月 3日 生成AIの主役は「クラウド」から「エッジ」に?
10月 2日 特許検索式作成GPTと人間の比較
10月 1日 AIによりあらゆる発明が当たり前にできてしまう時代の特許制度
9月30日 弁理士法人ITOH「特許明細書の書き方 改訂10版」
9月29日 知財実務オンライン「俯瞰解析企業VALUENEXの最近の取り組み」
9月28日 無料の天秤AIで「OpenAI o1-preview」も使える
9月28日 「特許出願の手続2024」(INPIT知的財産e-ラーニングサイト)
9月27日 2024年版「世界イノベーション指数」で日本13位
9月26日 ChatGPTのAdvanced Voice Mode
9月26日 令和6年度特許審査の質についてのユーザー評価調査報告書
9月25日 超知能は数千日以内に実現
9月25日 令和5(ネ)10010 特許権侵害行為差止等請求控訴事件 公然実施
9月24日 PatentSight Summit 2024 投資家が求める知財情報の開示
9月23日 なぜ、いま『攻めの知財』なのか?
9月23日 Genspark Autopilot Agent
9月22日 令和3年(ワ)第2873号 発明の技術的範囲
9月22日 Sakana AI GENIAC成果報告会
9月21日 令和5年(行ケ)第10098号 周知技術
9月20日 令和6年(行ケ)第10002号 技術常識
9月20日 OpenAI、「OpenAI o1」の制限を緩和
9月19日 LLMが苦手な問題
9月19日 ChatGPT搭載の特許明細書作成サービス「appia-engine」
9月18日 サマリアが図面も考慮して解析できるように機能アップ
9月18日 検索特化生成AI「Genspark」
9月17日 LLMが出すアイデアは人間が出すアイデアよりもいいか?
9月16日 OpenAI o1のIQが120
9月16日 「OpenAI o1」を使ってみた(4)
9月15日 「OpenAI o1」を使ってみた(3)
9月15日 「OpenAI o1」を使ってみた(2)
9月14日 「OpenAI o1」を使ってみた(1)
9月13日 ChatGPT新型モデル「OpenAI o1」
9月12日 知財実務オンライン:IPランドスケープ実践に役立つ「論理と情理」
9月11日 2027年までに生成AIソリューションの40%がマルチモーダルに
9月10日 日立が挑む「生成AI活用による人手不足の解消」
9月 9日 サマリア分類支援機能を特許情報分析に活用
9月 8日 不純物クレームの特許性
9月 7日 欧州特許庁における「課題解決アプローチ」
9月 6日 人工知能の普及下での「当業者」と「普遍的一般知識」
9月 5日 当業者(POSITA)の技術水準
9月 4日 「除くクレーム」とする補正
9月 3日 進歩性判断の第三の道 非容易推考説と技術的貢献説の協調運用
9月 2日 北大サマーセミナー田村善之先生「判例研究の手法」
9月 1日 アカデミアにおけるAI×知財情報の最前線
9月 1日 カスタマーサポートの新常識 生成AIの導入
8月31日 Excelとオープンツールを使った特許分析の現状
8月31日 令和5年(行ケ)第10053号 パラメータ発明の進歩性
8月30日 AIはどうして急に賢くなったのか、これからどうなるのか
8月29日 弁理士としての新たな顧客価値創
8月29日 令和3年(ネ)第10086号「ランプ及び照明装置」 先使用権
8月28日 令和5年(行ケ)第10002号「光源ユニット及び照明器具」 機能的表現
8月28日 人工知能学会「AGIの実現は目前か?」
8月27日 サマリアの拒絶対応支援
8月27日 「機械学習パラダイス」の日本、生成AIとクリエイター権利保護
8月26日 知財はマーケティングの最強ツール
8月25日 製造業での人工知能活用には大きなチャンスがある
8月24日 マーケターの生成AI活用
8月23日 ソフトウェア特許を取得する際のポイント、ノウハウ
8月23日 天秤AIで生成AIの回答を比較:知財戦略策定の勘どころ
8月22日 文化庁が「AIと著作権」の講演映像を公開
8月22日 AI検索
8月21日 講演録「研究者から見た裁判実務」
8月20日 数値限定発明
8月19日 GoogleのAI検索「AI Overviews」
8月18日 知財業界での教育
8月17日 知財実務オンライン「欧州単一特許/統一特許裁判所制度」
8月16日 自分の用途に合った生成AIを選ぶ
8月15日 NTT版LLM tsuzumi
8月14日 AIが自ら研究する時代へ「AIサイエンティスト」公開
8月13日 進歩性判断のダブルスタンダード
8月12日 知財実務オンライン関西から知財実務を発信!KTK
8月12日 生成 AI を活用した特許データの処理
8月11日 新規性・進歩性の判断対象たる「発明」の意義
8月10日 科学技術指標2024
8月 9日 発明の進歩性の判断における「効果」
8月 8日 生成AIは発明創作のための有効なツール
8月 8日 進歩性判断における技術的貢献の位置づけ
8月 7日 進歩性要件における二次的考慮説の現在地
8月 7日 AI政策の現状と制度課題へAI制度研究会始動
8月 6日 パテント誌の連続特集「進歩性」
8月 6日 令和4(ネ)10055(特定加熱食肉製品=「ローストビーフ」事件)
8月 5日 中高生からの東大AI教育とは?
8月 5日 令和3年(行ケ)10091「粘着テープ」 パラメータ発明
8月 4日 JPO, USPTO, EPO, CNIPA, KIPOの特許査定率の推移
8月 3日 2023年の特許査定率は76%
8月 3日 ChatGPT4oで特許明細書を作成
8月 2日 知的財産権に関する紛争の責任・負担を下請事業者に転嫁する行為
8月 2日 小野薬品オプジーボの「特許の崖」
8月 1日 特許査定率が高い上位50社(2024年版)
8月 1日 分割出願特許が増加 特許行政年次報告書2024年版
7月31日 日立製作所 「Lumada(ルマーダ)」稼ぎ頭に
7月31日 日立製作所、生成AIが作成した文章かどうか判定する新技術
7月30日 総合特許登録率が高い上位50社(2024年版)
7月29日 AI活用で商品開発プロセス革新を狙う「Idea Generator」
7月28日 生成AIを使ったNTTグループ「架空商品モール」
7月28日 OpenAIがAIのレベルを5段階で評価、現在レベル1
7月27日 祝知財実務オンライン200回 特許訴訟の重要論点総点検
7月27日 OpenAIが検索AIのSearchGPTを発表
7月26日 生成AIによる学術論文の執筆、査読、出版への影響
7月25日 「PCT国際調査及び予備審査ハンドブック」の改訂
7月25日 キリンによるファンケル買収の狙いは「特許」?
7月24日 著作権セミナー「AIと著作権Ⅱ」
7月24日 中小企業14社知財活動を紹介した「知財活動事例集」
7月23日 CHATGPTでクレーム作成の練習
7月23日 特許庁 特許出願技術動向調査の調査テーマを募集
7月22日 AI制度研究会」の設置
7月21日 イーパテントチャンネル「官公庁・企業・事務所と知財」
7月21日 キーパーソンが語る日本の生成AI 現在と未来
7月20日 生成AIとAI特許調査ツールの連携
7月20日 知財部員の発明ヒアリング
7月19日 知財実務オンライン「韓国の知的財産権訴訟」
7月19日 「情報の科学と技術」で6つの特許データベース,検索システムが紹介
7月18日 令和5(行ケ)10091 用途特定と技術的構成の相互関連性
7月18日 知財実務オンライン「知財を『学ぶ』から『伝える』へ」
7月18日 知財管理7月号「生成AIの知財業務での活用」
7月17日 日本新聞協会「生成AIにおける報道コンテンツの無断利用等に関する声明」
7月17日 有価証券報告書の記載で、ブランド戦略、知財戦略、IPランドスケープ増
7月16日 天秤AIで複数の生成AIを無料で比較
7月16日 AI革命をチャンスに世界へ挑む
7月15日 特許検索式作成GPTの使い方
7月15日 ホンダの経営に資する戦略的IPランドスケープ活動
7月15日 協業の成果をライバル社に売ってもOK、ホンダのオープンイノベーション
7月14日 F1で世界一になったホンダが、「あえて」特許を取ったワケ
7月13日 「ネオジム磁石」を発明した佐川真人氏に「欧州発明家賞」
7月12日 「令和6年度著作権テキスト」公開
7月11日 生成AIを追加した「DX推進スキル標準」の改訂
7月11日 PATENTSIGHT SUMMIT 2024
7月10日 深センの発展及び企業の成長
7月10日 生成AIでデジタル戦略は変わる
7月 9日 東京大学TLO設立以来の技術移転実績
7月 9日 コンテンツ制作のための生成AI利活用ガイドブック
7月 8日 知財実務オンライン UNITARY PATENT (UP)& UNIFIED PATENT COURT (UPC)-LATEST UPDATES
7月 8日 マーケティングにおける生成AIの活用
7月 8日 欧米で進むAI規制 出遅れ日本
7月 7日 CHATGPT 4OとJ-PLATPATで特許データを分析
7月 6日 生成AI「仕事で利用」4割、1年で倍増
7月 6日 令和6年版情報通信白書 生成AI利用は日本低水準
7月 5日 ソフトバンクGの生成AIを活用した効率的な特許出願
7月 4日 生成AI関連の特許出願、中国が7割
7月 4日 生成AI時代のマーケティング・クリエイティブ革命
7月 3日 令和5年(ネ)第10090号 発明者の認定
7月 2日 なぜ、経営戦略から孤立するのか? 漂流する知財
7月 2日 特許事務所のM&A
7月 2日 生成 AI 利活用におけるELSI(ETHICAL, LEGAL AND SOCIAL ISSUES)
7月 1日 除くクレームの有用性
7月 1日 ソフトバンクGの特許出願
6月30日 AI活用新規事業のアイデア共創プラットフォーム「IDEAFLOW」
6月30日 ソフトバンクとTEMPUS AI, INC.の新しい医療事業
6月29日 特許庁、特許庁政策推進懇談会中間整理を公表
6月28日 アナクアのAI搭載IP管理プラットフォーム
6月28日 J-PLATPATにおける特許文献アクセス状況
6月28日 J-PLATPATのキーワード検索でOR演算する
6月27日 特許IPから読み解く次世代自動車開発戦略
6月27日 知財実務オンライン:「MAKING OF "特許法講義"」
6月26日 知財におけるAI・技術革新を超越した生成型 AI
6月26日 特許の崖を転がり落ち独自技術で成長する住友ファーマ
6月25日 知財高裁が係属中の事件で第三者から意見募集
6月25日 日経ビジネス AI実装のコツ50
6月24日 GOOGLE VS MICROSOFT 生成AIをめぐる攻防
6月24日 本庶佑 京都大学がん免疫総合研究センター長「私の履歴書」(23)特許係争
6月23日 商標「知財実務オンライン」知財高裁判決
6月23日 教育の現場でのDXと生成AIの役割
6月22日 異議申立による特許の取消率が低下傾向
6月22日 知財実務オンライン:AIを題材にガバナンスを考える
6月21日 知財実務オンライン「知的財産推進計画2024」及び「知財・無形資産ガバナンスガイドライン」
6月21日 令和のビジネスモデルを考える─DX時代の新事業開発と知財ミックス─
6月20日 製造業における生成AI活用の実態調査
6月20日 三井化学 量子×AI技術を特許検索の高度化と新規用途発見に適用
6月19日 旭化成 組織の壁を越えたMIの活用で競争力強化
6月19日 PWCの2024年春の生成AI調査
6月18日 IT業界から知財業界に転職して
6月18日 ソフトバンク、生成AI検索「PERPLEXITY PRO」1年無料
6月17日 センサーメーカーの生成AI活用
6月17日 長引く知財訴訟、柔軟性欠く日本企業に原因?
6月17日 LUMA AIが動画生成AI「DREAM MACHINE」を一般公開
6月16日 知財実務オンライン「化学特許の出願戦略」
6月16日 IPS細胞特許の和解と公共の利益のための通常実施権
6月16日 令和4年(行ケ)第10097号 引用発明の認定
6月15日 小野薬品工業 特許の崖を乗り越える海外展開
6月15日 知財実務オンライン:知財でつなぐ「産」と「学」
6月15日 令和5年(行ケ)第10098号審決取消請求事件「衣料用洗浄剤組成物」
6月14日 中間対応で「除くクレーム」を検討するタイミング
6月14日 大和ハウス工業の研究員は通期で最低2件の特許出願
6月14日 生成AI戦国時代
6月13日 OPENAIの売上高が大幅増
6月13日 特許特別会計の財政運営状況等
6月12日 HITACHI INVESTOR DAY 2024
6月12日 APPLE INTELLIGENCE
6月11日 NVIDIAのCEOジェンスン・フアン氏の基調講演
6月10日 日本がテクノロジーで世界をリードするための戦略
6月10日 知財実務オンライン「稼ぐ経営者のための知的財産情報」
6月 9日 企業向け生成AIにおける富士通の取り組み
6月 9日 生成AIと安全性
6月 8日 IPS関連特許での裁定請求を審議の教授が語っていること
6月 8日 知財実務オンライン「大学知財の事業化の最新実務」
6月 8日 IPAS (IP ACCELERATION PROGRAM FOR STARTUPS) 成果事例集
6月 7日 第28回新しい資本主義実現会議
6月 7日 令和5(行ケ)10024審決取消請求事件 新規事項の追加
6月 6日 統合イノベーション戦略2024
6月 6日 知財実務オンライン「知財価値評価ことはじめ」
6月 5日 知財実務オンライン:クリエイターが実践する「知財のすゝめ」
6月 5日 知的財産推進計画2024及び新たなクールジャパン戦略
6月 4日 急増しているソフトバンク孫氏発明特許出願分析
6月 4日 ライオンとNTTデータ熟練者の暗黙知を生成AIで継承
6月 4日 知財実務オンライン「暗黙の知財同盟:高い企業収益を得る知財の活用」
6月 3日 令和5年(行ケ)第10057号「噴射製品および噴射方法」事件
6月 3日 クールジャパン戦略を再起動
6月 3日 日本においてもAI規制のハードロー(法律・基準)検討を始める
6月 2日 IPS特許で和解、制限はあるが特許の利用が認められた
6月 2日 すごい知財EXPO2024 今年の企画内容や新しい試み
6月 2日 大規模言語モデル(LLM)の開発:第38回人工知能学会全国大会
6月 2日 金融生成AI実務ハンドブック(第1.0版)
6月 1日 知財実務オンライン「これからの知財人財のスキルと育成」
6月 1日 特許の権利化における特許文書の読み方
5月31日 CHATGPT無料版ユーザーが多くの機能使えるように
5月31日 令和5(行ケ)10052 特許取消決定取消請求事件 除くクレーム
5月30日 AI家庭教師が米国の子供たちの勉強法を静かに変えつつある
5月30日 知財実務情報LAB.アセアン知財制度、知財情報収集法
5月30日 令和4(行ケ)10110 審決取消請求事件 パラメータ発明
5月29日 AI 時代の知的財産権検討会中間とりまとめ
5月29日 GPT-4がプロのアナリストに匹敵する精度の財務諸表分析
5月28日 攻めのオープンな知財戦略
5月28日 生成AIの進化と今後の展望
5月28日 「IPランドスケープをアップデートする」すごい知財EXPO 2024
5月27日 AIサミットで世界16企業が安全な開発を約束
5月27日 2024年後半、生成AIの産業利用が本格的に始まる
5月27日 完成形に近づく日東電工のニッチトップ戦略
5月26日 成長のカタリストとしての生成AI
5月26日 レゾナック、NECの好例から探るPBRの高め方
5月26日 全人類が史上最高のAIを使えるようになった「時代の転換点」
5月26日 大規模言語モデルが「人間レベルの知恵」を持つことはない
5月25日 知財強国へ駆け上がる中国の今
5月25日 OPENAIとGOOGLE発表から読み取る両社の戦略
5月25日 知的財産推進計画2024策定に向けた「構想委員会(第4回)」
5月24日 生成AIで日常化される知財 GEMINIによる要約
5月24日 AI 時代における特許翻訳
5月24日 生成AIの産業における可能性(AI戦略会議第9回)
5月23日 知財戦略についてのとことん議論
5月23日 「AI と著作権に関する考え方について【概要】」の英訳版
5月23日 生成AIの特許分野における活用
5月22日 何としても特許を取りたいときの思考術
5月22日 博報堂がAIとユーザーとの会話から商品紹介する技術を特許化
5月21日 世界初のAI規制法がEUで成立 今後「世界標準」化?
5月20日 新規上場企業の有価証券報告書に見る知財ガバナンス
5月20日 非構造化データを生成AIで活用する
5月19日 ソフトバンク孫氏発明者特許の公開件数が急増
5月19日 AI研究の最新動向(松尾豊教授2024年3月15日講演)
5月18日 研究用に提供した乳酸菌株を不法に使用?老舗みそ蔵が提訴
5月18日 CHATGPT無料ユーザーが最新のモデル「GPT-4O」を使う方法
5月18日 生成AI戦国時代 OPENAI対GOOGLE
5月17日 AI発明をめぐる実務上の懸念に対し立法論として検討を行うべし
5月16日 生成AIの業務活用への10の学び
5月16日 研究成果の価値を最大限に引き出すための大学研究者向け知財研修教材
5月15日 知財情報開示と株価の関係
5月15日 サマリアがGPT4O(GPT4 OMNI)対応
5月14日 CHATGPTが「GPT-4O」に進化 テキスト、音声、画像を高速処理、多くの機能が無料に
5月13日 特許裁判例事典(第4版)読み合わせ②(新規事項追加)
5月13日 ブランド価値向上による無形資産強化
5月12日 「富岳」で学習した日本語能力に優れた大規模言語モデル
5月12日 知財を積極的に公開して協業先を募るパナソニック
5月11日 提供価値の評価とアイデア創出プロセス
5月10日 日立製作所GENERATIVE AIセンターの現時点での成果、今後の展望
5月 9日 クレーム作成勉強会
5月 8日 「実装フェーズ」に入った生成AI
5月 7日 中国の知的財産概況2024年4月(WIPO⽇本事務所ウェビナー)
5月 6日 暗黙の知的財産同盟によるイノベーションの専有
5月 5日 特許出願の中間手続基本書 第5版
5月 4日 審査と審判における判断基準の相違
5月 3日 審決取消訴訟と侵害訴訟における新規性判断が分かれた例
5月 2日 先使用権の主要論点について大激論
5月 2日 日本政府がAI開発に法規制を検討
5月 1日 分野別特許出願技術動向調査結果:全固体電池は日本に強み
5月 1日 スズキ 知財強化へ社長・技術系役員が発明者と座談会
4月30日 ファミリーマートが生成AIで業務を50%削減
4月30日 令和5年度(2023年度)知的財産活動調査結果の公表
4月29日 発明の定義、先使用権の条文など変えた方が良い
4月29日 生成AIが起爆剤となって、製造業でのデータ活用が加速
4月28日 「知的財産推進計画2024」に向けた検討
4月28日 事業会社からのスタートアップ創出を促すカーブアウトの戦略的活用
4月27日 特許情報に係る商用データベースの機能水準
4月26日 IPランドスケープの仮想実施事例
4月26日 知財・無形資産の投資・活用を推進するためのチェックリスト
4月25日 先使用権についての若干の安心材料
4月24日 AIの利活用の拡大に伴い進歩性の考え方を変更すべきか
4月23日 AI 時代の知的財産権検討会中間とりまとめ(案)について
4月22日 AIを利活用した創作について
4月22日 東レは、材料開発のDXやMIでは世界のトップレベル
4月21日 企業・研究機関の34%が創作過程でAIを活用
4月20日 営業の7割が生成AIを活用している日清食品
4月20日 AI事業者ガイドライン(第1.0版)決定
4月20日 「大学経営とDX」、「生成AIで授業が変わる」
4月19日 文化庁が「AIと著作権に関する考え方について」の概要を公表
4月18日 オープンイノベーションに向けた大学向け契約書解説パンフレットとマナーブック
4月17日 特許データの内容分析と生成AIの活用
4月17日 CHATGPTの日本語処理能力が従来の3倍に
4月16日 日本の産業におけるイノベーションの専有可能性と技術機会の変容;1994-2020
4月15日 「特許法講義」 「田村特許法学」の到達点がこの1冊で学べる!
4月14日 令和4(ネ)10055(特定加熱食肉製品) 除くクレーム
4月13日 第19回知的財産分科会の議事要旨と速記録
4月12日 市場・戦い方・連携相手を見極めるIPランドスケープマニュアル
4月11日 新規性喪失の例外(グレース期間)の利用の実態とその影響
4月10日 読売新聞とNTTが生成AIのあり方に関する共同提言を発表
4月 9日 事例から学ぶ 商標活用ガイド2024
4月 8日 ⽇本の国際競争⼒を⾼める「⽤途発明」
4月 7日 古河電工の知的財産報告書2023
4月 7日 高砂香料の知的財産報告書2023-2024
4月 7日 中国電力「エネルギアグループ知的財産報告書2024年」
4月 6日 予測可能性の高い先使用権制度
4月 6日 グローバル知財戦略フォーラム2024開催報告アップ
4月 5日 生成AIがDXを加速させる
4月 5日 アートやデザインなどの表現分野の知的財産・法務=表現法務
4月 5日 産学連携の変化と企業の知財契約担当者
4月 4日 DXのトップランナー、中外製薬の生成AI活用
4月 4日 侵害予防調査について
4月 3日 20年以上前に公知となっている古い技術を探す
4月 2日 公然実施が認められたシュープレス用ベルト事件
4月 2日 特許出願非公開制度の施行
4月 1日 先使用権制度を巡る対立
4月 1日 「TRANSFORMER」後継期待の「RETNET」を活用した独自LLM
3月31日 ジーテクトの統合報告書
3月31日 アネスト岩田の統合報告書
3月30日 レゾナックの知的財産分野への生成AI活用
3月30日 日本語と英語を併記した「特許庁ステータスレポート2024」
3月29日 PATENTFIELDが生成AIを活用した特許査読支援の新サービスを発表
3月28日 カプコン有価証券報告書
3月28日 知財実務オンライン「知財ガバナンスと生成AIで変わってきた企業知財実務」
3月28日 セイコーエプソン有価証券報告書
3月27日 ロート製薬 統合レポート
3月27日 ナブテスコグループ統合報告書
3月26日 森永製菓グループ統合報告書
3月25日 審判実務者研究会報告書2023 事例2(特許化学1)除くクレーム
3月24日 審判実務者研究会報告書2023
3月23日 第23回知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会
3月23日 第6回AI時代の知的財産権検討会「AI 時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ骨子(案)」
3月22日 サーチ漏れ、判断の均質性
3月21日 日本は生成AIの業務活用において主要各国に先行 PWC調査
3月20日 第69回文化審議会著作権分科会「AIと著作権に関する考え方」報告書
3月20日 知財実務オンライン:WEB3分野における知財の留意点
3月19日 特許情報解析分野で生成AIによって可能になったたこと
3月18日 特許調査における特許文書の読み方~侵害予防調査を中心に~
3月17日 知財実務オンライン「未来の標準必須特許を考えよう -通信業界における特許の作り方-」
3月17日 AI研究の最新動向とAIが社会に与えるインパクト
3月16日 AIが変える未来と知財
3月15日 特許調査の王道
3月14日 EU議会が生成AIを含む世界初の包括的なAI規制法案を可決
3月14日 コア価値(知財・無形資産)による共創
3月13日 生成AIによる著作権侵害の実例の集積
3月12日 CHATGPT-4は日英翻訳において人的翻訳よりも高い翻訳精度
3月11日 画像生成AIの著作権問題のわかりやすい解説
3月11日 令和5年税関における知的財産侵害物品差止 大阪税関では過去最高
3月10日 GPT-4とCLAUDE3(OPUS)で特許の請求項を比較
3月10日 企業における生成AI活用:組織にあった導入の勘所
3月10日 CLARIVATE TOP 100 グローバル・イノベーター 2024に日本企業38社が選出
3月 9日 国内外のAIガバナンス動向の全体像
3月 9日 2023年の国際特許出願件数14年ぶりの減少
3月 9日 教育機関DXシンポでの生成AIに関する3つの発表
3月 8日 中国コンテンツ業界の最新事情
3月 7日 パターンで見る結合商標の類否~ 2つの視点から~
3月 7日 価値創造フォーラム2024「知的財産とデザインの融合」
3月 6日 なぜ引⽤発明の上位概念化が進歩性の否定に繋がるのか︖
3月 6日 明治 「きのこの山 ワイヤレスイヤホン」模倣品
3月 5日 除くクレーム 令和5年(行ケ)第10011号「携帯端末の遠隔操作用デバイス」事件
3月 5日 除くクレーム 令和5年(行ケ)第10046号「角栓除去用液状クレンジング剤」事件
3月 4日 IPナレッジカンファレンス FOR STARTUP 2024
3月 4日 知財実務オンライン 暗黙知をいかに形式知化するか?
3月 3日 AIとガバナンス 東京大学共同シンポジウム
3月 3日 生成AIの基礎と社会的影響が分かりやすい本「生成AIで世界はこう変わる」
3月 2日 AIと著作権に関する考え方について(素案)令和6年2月29日時点版
3月 2日 AIと著作権 東京大学共同シンポジウム
3月 1日 AIと著作権 現行規定の法解釈から立法論まで
3月 1日 AIコンピュート(計算処理能力)の必要性を誰もが過小評価している
2月29日 生成AIが変える仕事と産業の将来像予測
2月29日 ダイセルの防眩フィルム特許網
2月28日 TSMC熊本工場は日本経済の墓標?
2月27日 「知的財産推進計画 2024」の策定に向けた意見募集
2月27日 生成AI(CHATGPT)が弁理士試験に挑戦
2月26日 AI規制は有害な出力防止に絞り、情報解析の自由は堅持すべきか?
2月26日 銀行が無形資産に融資できるか
2月25日 第6期 知財AI活用研究会・最終報告会 2024年3月1日
2月25日 生成AIがイノベーションと知財戦略強化にどう役立つか
2月24日 知財実務オンライン:「やめた方がいい知財活動」
2月23日 特許ライティングマニュアルの紹介
2月22日 生成AIが「発明構築」「特許調査」「特許明細書作成」に活用できるか
2月21日 日本知的財産仲裁センター「生成AIと知的財産」
2月20日 CHATGPTが社内であまり使われない本当の理由
2月20日 サマリアが2024年の開発ロードマップ公表
2月19日 NECの独自開発LLMで描く「生成AI」戦略の“勝ち筋”
2月19日 第5回IP BASE AWARD受賞者
2月18日 CHATGPTが新たなビジネスチャンスをもたらす可能性
2月18日 第6回日本オープンイノベーション大賞 酸化制御技術『MA-T SYSTEM®』
2月18日 知財実務オンライン:ディープテックスタートアップの特許戦略
2月17日 30年間ほぼゼロ成長という日本経済は世界的に見て「異常」
2月17日 産業競争力強化法等改正案(イノベーションボックス税制、特定中堅企業者など)
2月16日 中⼩企業こそいち早く⽣成AIを活用すべき
2月16日 USPTO AIが関与する特許の発明者に関する詳細なガイダンスを公表
2月16日 生成AI法規制に関する自民党の動き
2月15日 OPENAIを相手に起こした著作権侵害訴訟の行方
2月15日 JASRAC 「AIと著作権」で著作権法の改定が必要と意見提出
2月14日 弁理士によるAIツールの適切な利活用を促すためのガイドライン
2月14日 知財実務オンライン「PATEPEDIAの世界へようこそ」
2月14日 進歩性の全論点+Α、知財実務情報LAB.
2月13日 イオンが生成AI利用 商品開発など支援
2月13日 「AIと著作権に関する考え方について(素案)」への懸念
2月12日 GPTに頼れ、大規模言語モデルと弁護士の比較
2月12日 産官学の生成AI導入事例集
2月12日 GOOGLEの生成AIサービスで、BARDがGEMINIに
2月11日 「小さいLLM」という生成AI戦略で勝てるか?
2月11日 生成AIに関する2024年の見通し
2月11日 生成 AI をアイデア創出に活用
2月10日 知財戦略の投資家対話への活用
2月10日 昨年8~9月で従業員1万人以上の日本企業では50%が生成AI導入済
2月10日 新聞協会が著作権法改正主張の意見書提出
2月 9日 日本ガイシとストックマークが独自生成AIで新規用途探索
2月 9日 古河電工 生成AIで技術資産を可視化
2月 8日 文系弁理士が特許実務をする強み
2月 8日 東北大学の生成AI業務実装
2月 7日 生成AIが企業の知財戦略を変える
2月 7日 タイ、ベトナム、インドネシアでは誤訳が致命傷になることも
2月 6日 経済安全保障推進法に基づく特許出願非公開制度
2月 5日 知財所得への優遇税制
2月 4日 知財実務オンライン:最終プロダクトの知財戦略・戦術
2月 4日 セキュリティ・クリアランス創設法案
2月 3日 「特許データベース・分析ソフト比較検討会」の録画
2月 3日 花王、茶カテキン飲料「ヘルシア」をキリンへ譲渡
2月 3日 技術者の特許に対する取り組みと知財部門との融合
2月 2日 「APPIA-ENGINE」で実現する新しい明細書作成
2月 2日 資本コストや株価を意識した経営の好事例29社
2月 1日 伝統的知財活動と現代的知財活動
1月31日 「何でもイノベーション」症候群
1月31日 トヨタグループビジョン「次の道を発明しよう」
1月30日 AI時代の知的財産権検討会(第5回)における残された論点について
1月30日 初心忘るべからず(30) 知財問題研究会への参加
1月29日 初心忘るべからず(29)審判実務者研究会への参加
1月29日 非財務資本強化による価値創造経営の実現
1月28日 特許明細書を徹底的にレビューする配信
1月28日 初心忘るべからず(28) ナノセルロースフォーラム知財戦略ワーキンググループへの参加
1月28日 ユニクロが不正競争防止法でSHEINを提訴
1月27日 知財実務オンライン:「令和5年不正競争防止法改正」
1月27日 初心忘るべからず(27) 業界の特許委員会への参加
1月26日 初心忘るべからず(26) 知的財産部長になって困ったこと
1月26日 グローバル知財戦略フォーラム2024視聴
1月25日 初心忘るべからず(25)進歩性が争われた判決の研究
1月25日 特許から認証試験不正を見る視点
1月24日 初心忘るべからず(24)知財高裁の進歩性判断の変化に対応した知財活動
1月23日 初心忘るべからず(23)標準化特許の効果的な出願・権利化戦術
1月23日 パラメータ発明の進歩性
1月23日 日本が国家ブランド指数で世界トップ
1月22日 大学入試共通テスト2024を3種類の生成AIに解かせた
1月22日 初心忘るべからず(22)特許の質
1月21日 生成AIを業務で日常使用は3割
1月21日 初心忘るべからず(21)産学共同研究契約交渉の事例集
1月20日 テスラの特許戦略は合理的か?
1月20日 初心忘るべからず(20)東北大学との産学連携
1月19日 初心忘るべからず(19)鳥取大学との産学連携
1月19日 地政学リスクと知財戦略
1月18日 初心忘るべからず(18)共同研究が成功した後の諸問題について
1月17日 初心忘るべからず(17)共同開発研究を成功させる
1月17日 生成AIの著作物無断利用に現行著作権法解釈明確化で対応
1月16日 PBRが低い企業ほど「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」を開示
1月16日 初心忘るべからず(16)知財教育
1月15日 荏原製作所の知財ROIC
1月15日 初心忘るべからず(15)審決取消訴訟(当事者系)
1月14日 初心忘るべからず(14)審決取消訴訟(査定系)
1月13日 日経平均7万円への3つのシナリオ
1月13日 初心忘るべからず(13)審査官による判断のバラツキ
1月12日 知財実務オンライン:「内閣府知財事務局活動内容、大学知財ガバナンスガイドライン」
1月12日 初心忘るべからず(12)面接審査
1月11日 「除くクレーム」と“進歩性” 知財実務情報LAB. 高石秀樹弁護士
1月11日 初心忘るべからず(11)他社基本特許を基に独自技術を開発
1月10日 面接ガイドライン【特許審査編】改訂
1月10日 AI関連技術に関する事例の追加
1月10日 初心忘るべからず(10)新市場創造と特許網構築
1月 9日 月刊「パテント」誌の特集<生成AIと特許>
1月 9日 初心忘るべからず(9)ロシアでの知財訴訟
1月 8日 年報知的財産法 2023-2024
1月 8日 初心忘るべからず(8)初めての特許侵害訴訟提起
1月 7日 初心忘るべからず(7)先使用権
1月 6日 初心忘るべからず(6)特許査定率の向上に向けた取り組み
1月 5日 初心忘るべからず(5)特許重視戦略への転換
1月 4日 初心忘るべからず(4)初めての知財訴訟
1月 3日 初心忘るべからず(3)初めての機械系特許出願
1月 2日 初心忘るべからず(2)初めての特許網構築
1月 1日 初心忘るべからず(1)初めての特許出願
12月31日 弁護士・高石秀樹の特許チャンネル「事業に資する知財戦略」
12月31日 令和4年(ネ)第10094号 特許権侵害差止等請求控訴事件 課題の認識とサポート要件
12月30日 生成AIを悪用した詐欺
12月30日 令和4年(行ケ)第10126号 審決取消請求事件 新たな技術的事項
12月29日 生成AI活用とその限界
12月28日 実務にRETURNした高林弁護士から見た現代特許訴訟の特色
12月28日 知的財産の流出は捜査機関とも連携して管理を徹底
12月27日 軍事転用可能な機械不正輸出めぐる冤罪事件で、捜査は違法 国と東京都に賠償命令判決
12月27日 軍事転用可能な先端技術の「特許非公開化」
12月26日 "攻めの知財"への転換
12月26日 日本の1人あたりGDPがG7最下位、OECDでは21位
12月25日 ブランドを築く知財ミックス
12月24日 労働生産性の国際比較 2023
12月24日 令和4年(行ケ)第10029号 技術的に一体不可分
12月23日 生成 AI 市場の世界需要額は年平均 53.3%で成長
12月23日 「AI事業者ガイドライン」だけで良いのか?
12月22日 経済発展を推進するのは「国民の創造力」
12月22日 特許裁判例事典(第4版・・・) サポート要件
12月21日 AIと著作権に関する考え方について(素案)公表
12月21日 令和3年(行ケ)第10152号 審決取消請求事件 サポート要件違反
12月20日 知財実務オンライン「今年の進歩性判例の頻出論点総まとめ」
12月19日 経営コンサルタントの特許分析・知財分析
12月18日 企業を守るAIガバナンスの構築と運用の実践ガイド
12月17日 「サマリア」を利用した侵害予防調査
12月16日 「スズキらしい」「そう来たか」目指す スズキの知的財産戦略
12月15日 NATURE’S 10 TEN PEOPLE (AND ONE NON-HUMAN) WHO HELPED SHAPE SCIENCE IN 2023
12月15日 企業がはまる「AIリスク」
12月14日 生成AIの「光と影」 共存のために必要なこと
12月13日 日本ゼオンの知財戦略
12月13日 12月11日に開催された「第4回AI時代の知的財産権検討会」
12月12日 ビジネス関連発明
12月12日 CHATGPT翻訳術のノウハウ
12月11日 バイデン大統領の「AIに関する大統領令」
12月10日 AI関連技術に関する審査ハンドブックの事例を追加
12月10日 EU、生成AIを含むAI利用の包括的規制案で暫定合意
12月 9日 令和4年(行ケ)第10125号 審決取消請求事件 除くクレーム
12月 8日 生成AIがもたらす4つの産業革命
12月 7日 AIと共同で特許情報から発明を生み出すAMPLIFIED.AI
12月 7日 出版記念特別講演『特許3.0 AI活用で知財強国に』
12月 6日 特許は「量より質」 シャープの特許改革
12月 6日 扶桑化学工業の知財戦略
12月 5日 新規性・進歩性判断時の「一行記載と引用発明の認定」
12月 4日 「第1回NIKKEI知財・無形資産シンポジウム」の記事
12月 3日 「知財・無形資産」ガイドラインVER2.0で描く価値創造戦略
12月 3日 授業に生成AI
12月 3日 知財管理システム
12月 2日 全ての AI 関係者向けの広島プロセス国際指針
12月 2日 ブリストル・マイヤーズ スクイブ(BMS)と沢井製薬の特許紛争
12月 1日 「知的財産推進計画2024」に向けた検討
11月30日 知財実務情報LAB.:生成AI(CHATGPT)の特許実務における利活用
11月30日 研究開発の常識を超えて事業化を追求 NEC研究所
11月29日 「選択と集中」は正解ではないのか?
11月29日 技術者・研究者のための 特許の知識と実務[第5版]
11月28日 オムロンの知財戦略
11月27日 株主重視経営の是非
11月26日 株式の非公開化
11月25日 『今年、部署に配属された最も優秀な同僚』生成AI
11月24日 J-PLATPAT リーガルステータス機能の第2弾リリース
11月24日 大和ハウスの技術戦略
11月23日 WIPO「エネルギー市場の未来を変える 知的財産国際シンポジウム」
11月22日 生成AIと著作権保護 文化庁が28の論点を提示
11月21日 東京大学知的財産報告書2023が発行
11月20日 日本製鉄対トヨタ特許訴訟での請求放棄をめぐる報道
11月19日 イノベーションボックス税制のメリットとデメリット
11月19日 IR優良企業賞2023 IR優良企業大賞は日立製作所
11月18日 大学等におけるCHATGPTの活用
11月18日 EPOの入力したテキストに基づいてCPCを予測するツール
11月17日 ゲーム会社の知財 コロプラ
11月16日 パラメータ発明のサポート要件 令和4年(行ケ)第10081号「ゴルフクラブ用シャフト」事件
11月15日 引用発明と課題が異なる場合の進歩性
11月14日 知財活動による企業価値向上ストーリーを客観的に検証 旭化成の知的財産報告書 2023
11月13日 任天堂の知財戦略
11月12日 KDDIの知的財産マネジメント
11月11日 大和ハウス工業の知財戦略
11月10日 レゾナックの知的財産戦略
11月 9日 50歳以上の全社員に生成AI研修を実施するサントリー
11月 9日 広島AIプロセス AI事業者ガイドライン 利用促進・開発力強化
11月 8日 意見提出数1132件 AI時代の知的財産権検討会(第3回)
11月 7日 大阪地裁令和2年(ワ)12107 職務発明の相当の対価請求訴訟
11月 6日 住友化学の競争優位&共創・協調に向けた知的財産活動
11月 5日 日本製鉄の知財戦略
11月 5日 特許文献を学習した生成AIによる発明提案サービス AXELIDEA PATENT
11月 4日 クボタの知的財産活動
11月 4日 古河電⼯の知財活動 マインドチェンジ
11月 3日 味の素IR DAYにみる知財戦略を通じた企業価値向上の実現
11月 2日 AI関連発明の出願状況調査結果
11月 2日 自社への他社営業秘密の不正流入による侵害リスク
11月 1日 「第1回NIKKEI知財・無形資産シンポジウム」のアーカイブ動画配信
11月 1日 令和4年(行ケ)第10111号審決取消請求事件 知財高裁が審判で認めた進歩性を否定
10月31日 高砂香料の知的財産活動
10月30日 アシックスの知財経営
10月29日 ファンケルの知財活動
10月28日 TOKKYO.AI 特許生成AIで特許明細書の作成を支援
10月27日 荒川化学グループの知財活動
10月26日 PBRを持続的に高めるオムロンのサステナビリティ経営
10月26日 保土谷化学の知財活動
10月25日 ブリヂストンの「攻めまくる」知財戦略
10月24日 特許審査官の特許査定率ランクなどがわかる「審査官ラボ」
10月24日 国内特許検索システム「CKS WEB」が生成AIを活用した検索・査読支援
10月23日 特許読解AIアシスタント「サマリア」 有料プラン導入
10月23日 第一工業製薬の知的財産戦略
10月22日 ニッタグループの知的財産活動
10月21日 証券アナリストジャーナルの特集「知的財産・無形資産の戦略」
10月21日 貝印の知的財産の取組み
10月20日 三菱鉛筆の知的財産への投資
10月20日 第一三共、がん治療薬「エンハーツ」の米特許侵害訴訟で敗訴
10月19日 無料のINPITの知財E-ラーニングサイトで新たな動画教材
10月19日 AI時代の知的財産権検討会(第2回)関連団体ヒアリング
10月18日 キューピーがESGブランド調査2023で総合順位急上昇
10月18日 知財実務情報LAB.セミナー「欧州における数値範囲の実務」
10月17日 「GPT―4」の化学知識は大学院レベル
10月17日 生成AIについての有識者ヒアリング
10月16日 日本製鉄がトヨタを特許侵害で提訴してから2年
10月15日 富士通 売上高の伸びと異動者増に強い相関、生成AIで開発効率30倍
10月14日 マーケティング本部内に知財部門を配置した横河電機
10月13日 小林製薬 ヒット商品づくりに全従業員が生成AI活用
10月12日 知的財産を起点とした共創を目指すパナソニック
10月11日 知財部のすべて(貝印、小林製薬、知財図鑑、弁理士)
10月11日 知財の成功事例 三菱電機・レゾナック・村田製作所
10月11日 AI時代の知的財産権検討会
10月10日 アイデアとは既存の要素の新しい組み合わせ以外の何ものでもない
10月10日 サンリオの知財戦略
10月 9日 中外製薬のR&D領域での生成AIに関する取り組み
10月 9日 特許の調査はいつ、誰がすべきか?
10月 8日 特許で競争優位を築くセイコーエプソンの知財ポートフォリオ戦略
10月 7日 生成AIを「業務で日常利用」は2割に到達
10月 7日 令和4年(行ケ)第10064号「微細結晶」事件 阻害要因
10月 6日 日本企業のAI導入と生産性
10月 6日 第1回AI時代の知的財産権検討会と意見募集
10月 5日 特許活動に関する情報開示量を増やした企業ほど株価の上昇率も高い
10月 5日 商標 コンセント制度の導入と実務上の留意点
10月 4日 世界の大学ランキング:新指標「特許への貢献度」で日本の大学が躍進
10月 4日 J-PLATPATの機能改善
10月 3日 「除くクレーム」の効果を主張すべきでないか?
10月 3日 第1回NIKKEI知財・無形資産シンポジウム
10月 2日 「イノベーションボックス税制」創設で国内投資促進
10月 2日 令和 5 年度特許審査の質についてのユーザー評価調査報告書
10月 2日 新冷戦は日本企業にとっては復活の好機。知財・無形資産の活用がカギ
10月 1日 3年前の知財実務オンライン配信
9月30日 特許で選ぶ「投資先」
9月30日 生成 AIの特許データ分析への活用
9月29日 CHATGPTを搭載した特許書類作成の戦略的な活用方法(9/27開催セミナー)
9月28日 用途・機能で発明を特定したクレームの問題点
9月27日 パラメータ発明の進歩性
9月26日 IPランドスケープ分析におけるCHATGPTの活用
9月25日 第8回 知的財産と先端技術に関するWIPO対話:生成AIと知的財産
9月25日 生成AIのタスク遂行メカニズムから考えた生成AIのポテンシャル
9月24日 IPランドスケープ推進協議会2 年目の活動総括と今後
9月24日 J-PLATPATの機能改善
9月23日 知財DX2023 知財業界におけるAI活用 の行方
9月23日 知財実務オンライン:「大学知財担当のシゴト」
9月23日 技術ありきで生成AIは導入しない 日立製作所
9月22日 特許庁がAI発明の審査強化
9月21日 知財経営のトレンド(2023特許・情報フェア&コンファレンス特別講演)
9月21日 連載「生成AI 動き始めた企業たち」第10回
9月20日 JAPIO YEAR BOOK 2023のCHATGPT・生成AI関連4題
9月20日 三井化学 生成AI/GPT活用により新規用途の発見数倍増
9月19日 公開シンポジウム「生成AIの課題と今後」
9月19日 トヨタテクニカルディベロップメント:知財業務への GPT 活用
9月18日 CHATGPTを活用した対話型の特許書類作成システム『AI SAMURAI ZERO』
9月17日 「発明を生成するAI 」AXELIDEA PATENTを使ってみた
9月17日 すごい知財EXPO2023 アーカイブ動画アップ
9月16日 セミナー「特許権侵害訴訟と独占禁止法違反・権利濫用」の録画公開
9月16日 便利すぎる「除くクレーム」 第159回知財実務オンライン
9月16日 2023特許・情報フェア&コンファレンス最終日
9月15日 やっぱりすごい 特許読解アシスタント「サマリア」
9月14日 2023特許・情報フェア&コンファレンス AI関連が約30%
9月13日 生成AIは低スキルの人ほど恩恵が大きい
9月13日 パナソニック自社保有知財情報検索サイトを外部公開
9月12日 進歩性判断に何故「本件発明の課題」が影響するのか?
9月12日 日清食品グループにおける生成AI活用
9月11日 髙部眞規子弁護士の自叙伝
9月11日 高林龍弁護士の自叙伝
9月10日 人工知能 (AI) に関する世界原則
9月10日 新AI事業者ガイドライン スケルトン(案) AI戦略会議
9月 9日 AI技術の進化によって知財戦略が大きく変わる
9月 9日 キーエンスの特許戦略
9月 8日 知的財産部門の歩き方(特許事務所→企業3社)第159回知財実務オンライン
9月 8日 CHATGPT APIを活用した特許明細書の作成支援ツール
9月 7日 社会と業界の姿を未来予測する技術
9月 7日 AIで発明創出できるのか?
9月 6日 DENAの知的財産への投資
9月 6日 日立が「CIPO」主導で挑むグローバル知財活動と知財部門が目指す「公邸料理人」
9月 5日 なぜユニ・チャームは値上げしても売れ続けるのか?
9月 5日 特許資産規模ランキング1位の三菱電機“驚き”の知財戦略
9月 4日 理想の発明提案書
9月 4日 東京都の「文章生成AI利活用ガイドライン」
9月 3日 チャットGPTは製紙技術者にとっての有能な助手となり得るのか
9月 3日 塩野義製薬「特許の崖」回避
9月 2日 「大学10兆円ファンド」「国際卓越研究大学」
9月 1日 日本の特許査定率の推移と特許戦略
9月 1日 令和6年度 特許庁関係(特許特別会計)概算要求
8月31日 「意匠の実務的戦略」の録画
8月31日 レゾナックのインテリジェンス活動
8月30日 北大サマーセミナー2023 4日目
8月29日 北大サマーセミナー2023 3日目
8月28日 「第9回特許・実用新案審査基準の勉強会」のセミナー録画公開
8月28日 北大サマーセミナー2023
8月27日 PATENTSIGHT SUMMIT 2023 明治HD
8月27日 知っておくべきAI・CHATGPTの用語41選
8月26日 PATENTSIGHT SUMMIT 2023:日東電工
8月26日 CHATGPTコードインタープリターの凄さ
8月25日 東南アジアの知財制度・知財実務
8月25日 味の素の中期経営計画(中計)策定の廃止
8月24日 アップルが、銀行やホテルを始めるのはなぜか?
8月24日 PATENTSIGHT SUMMIT 2023の講演レポートが公開(日東電工、日立製作所、明治HD、レゾナック)
8月23日 CHATGPT搭載の新製品『AI SAMURI ONE』リリース
8月23日 J-PLATPAT リーガルステータス機能
8月23日 日立製作所の復活
8月22日 「サマリア」機能アップデート(2023-08-21)
8月21日 CHATGPTの法律
8月21日 CHATGPTで競合会社の特許出願・権利化動向を分析
8月20日 CHATGPTが得意なのは、コード生成、文章の要約や論点の洗い出し、アイデア提案
8月20日 CHATGPTで特許情報をグラフ化:バブルチャート、三次元散布図
8月19日 特定特許とセマンティック検索で見つけた類似特許をCHATGPTに読ませた
8月19日 発明提案書が提出された際の対応に関するCHATGPTの回答
8月18日 特許出願状況、特許戦略のCHATGPTによる分析
8月18日 J-PLATPATからの特許情報をCHATGPT CODE INTERPRETERでグラフ化
8月17日 CHATGPT CODE INTERPRETERで、要約欄の課題と解決手段を分離
8月17日 プログラミングの知識なしでデータ分析できるCHATGPT「CODE INTERPRETER」
8月16日 CHATGPT最強の仕事術
8月15日 審査請求件数が多い上位50社(2023年版)
8月14日 特許出願件数が多い上位50社(2023年版)
8月13日 一次審査における記載要件充足率が高い上位50社(2023年版)
8月12日 一次審査における新規性充足率が高い上位50社(2023年版)
8月11日 審査請求率が高い上位50社(2023年版)
8月10日 化学研究者のための やさしくて役に立つ特許講座
8月10日 製造業の生成AI活用「7割が前向き」
8月 9日 「質の高い論文数」日本は過去最低の12位
8月 8日 生成AI時代のDX推進に必要な人材・スキル
8月 8日 知財が今後の企業価値を左右
8月 7日 知財の解析や戦略立案も…AGCの対話型AI「CHATAGC」
8月 7日 日経「知財経営ランキング」20位の大塚ホールディングス
8月 6日 日経「知財経営ランキング」19位の東洋紡、特許も示す「脱・繊維」
8月 5日 日経「知財経営ランキング」18位 アステラス製薬
8月 4日 日経「知財経営ランキング」17位のMUJIN
8月 3日 グローバル出願率が高い上位50社(2023年版)
8月 3日 日経「知財経営ランキング」で16位の東レ
8月 2日 法務省がAI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供の指針公表
8月 2日 日経「知財経営ランキング」15位の日本製鉄
8月 1日 国産生成AI 日本語対応や分野特化でチャットGPTに対抗できるか
8月 1日 日経「知財経営ランキング」14位の武田薬品
7月31日 日経「知財経営ランキング」13位のJFEホールディングス
7月31日 総合特許登録率が高い上位50社(2023年版)
7月30日 特許査定率が高い上位50社(2023年版)
7月30日 日経「知財経営ランキング」で11位の住友電工
7月29日 日経「知財経営ランキング」で12位の富士通
7月29日 特許行政年次報告書2023年版公表
7月29日 小野薬品 アストラゼネカ社との特許訴訟で全面的和解
7月28日 特許発明の技術的範囲と発明の作用効果・作用機序
7月27日 外部ツールによるCHATGPT等大規模言語モデルの拡張
7月26日 生成AIを活用した読解支援AIアシスタント「サマリア」大幅アップデート
7月26日 「効果」を発明特定事項とする物の発明の特許性
7月25日 日本のプロパテントがさらに一歩進んだ
7月24日 日経「知財経営ランキング」10位のクラレ
7月24日 日経「知財経営ランキング」9位のデンカ
7月23日 日経「知財経営ランキング」8位のダイキン工業
7月23日 日経「知財経営ランキング」7位のファナック
7月22日 日経「知財経営ランキング」で6位の京セラ
7月21日 周知技術追加の補正は復活した!・・・第152回知財実務オンライン
7月21日 「知財経営ランキング」で4位、日東電工の「知財くるま座」
7月20日 AGCの「他社が欲しがる特許」を評価する知財戦略
7月20日 「知財経営ランキング」で、3位の東京エレクトロン
7月19日 「知財経営ランキング」で、2位の日本たばこ産業(JT)
7月18日 村田製作所『屈辱から始まった「攻め」の知財経営』
7月17日 CHATGPT を使用したイノベーションの成功と評価の予測
7月17日 CHATGPTを活用した外国特許調査
7月16日 画像生成AI (MIDJOURNEY 5.2 , STABLE-DIFFUSION XL, ADOBE FIREFLY)
7月16日 文科省の生成AI取り扱い指針と大学生の生成系AI活用実態
7月15日 令和4年(行ケ)第10009号 引例上位概念化と周知技術
7月15日 カシオ腕時計G―SHOCKの立体商標登録
7月14日 日経ビジネス 知財経営ランキング 特許で攻める村田製作所
7月13日 除くクレーム(新規事項追加、進歩性)
7月12日 生成系AIと記号処理系AIとの適切な融合を期待
7月12日 CHATGPTはなぜ計算が苦手なのか
7月12日 知的財産発のイノベーション
7月11日 WIPO⽇本事務所ウェビナー
7月10日 APPLE、先使用権を主張して「APPLE MUSIC」商標登録に失敗
7月 9日 技術的思想がないと先使用権不成立⇒課題を解決する意図がないと実施ではない?
7月 9日 偏光フィルム知財高裁大合議判決のサポート要件判断基準
7月 8日 取締役の善管注意義務の判断基準
7月 8日 産総研「情報漏えい事案に係る再発防止策」へのCHATGPTの見解
7月 7日 生成AI ・大規模言語モデル(LLM)に関するNEC、ソフトバンクの動き
7月 7日 化合物発明の新規性と技術常識 令和4年(行ケ)第10091号
7月 6日 特許読解支援AIアシスタント「サマリア」アップデート
7月 6日 日本語に特化した生成AI
7月 5日 東大×生成AIシンポジウム「生成AIが切り拓く未来と日本の展望」
7月 5日 除くクレームで進歩性OK 令和3年(行ケ)第10111号
7月 4日 AMPLIFIEDに生成AI搭載 キーワード提案・要約文書生成により特許情報活用と発明創出を加
7月 3日 「イノベーションボックス税制」の創設
7月 3日 北大サマーセミナー2023申込み開始
7月 2日 有価証券報告書の記載で知財戦略、IPランドスケープ増加
7月 1日 文化審議会著作権分科会で生成AIと著作権の論点整理へ
6月30日 アセアン主要6か国での知財権利化および権利行使時の注意点
6月29日 出願後の技術水準の上昇と進歩性のレベル
6月29日 パナソニックコネクト、自社CHATGPTを「自社特化AI」へ
6月28日 リコーと理研の新たな技術の兆しを発見する可視化手法
6月27日 新規事項の追加の有無が争われた 令和4年(行ケ)第10092号
6月26日 ファーウェイ 日本の中小にも特許料要求
6月26日 CHATGPTを超える日の丸LLMへの期待
6月25日 信頼できるAIとは?
6月24日 マテリアルズインフォマティクスでハミガキ組成開発期間を約半分に
6月23日 厚生労働省の後発品の承認ルールに不満があるならば・・・
6月22日 令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」の講演映像及び講演資料公開
6月22日 『下町ロケット』のモデル 鮫島正洋弁護士の半生記
6月21日 令和5年度著作権セミナー「AI と著作権」
6月21日 米国特許査定率の推移
6月20日 JACK DANIEL’S V. VIP PRODUCTS 事件
6月20日 特許やソフトウエアの知財から得る所得に軽減税率を適用する税制
6月19日 INTEL とVLSI TECHNOLOGY(VLSI)との特許訴訟
6月19日 特許庁によるIPランドスケープの定義
6月18日 中国企業が特許取得した産総研情報漏洩事件
6月18日 世界初の人工知能に関する包括的なルールを定めたEUのAI規制法案
6月17日 「それってパクリじゃないですか?」の監修ものがたりが約47分
6月17日 産総研の技術情報漏洩事件
6月16日 CHATGPTを活用した発明発掘術
6月15日 CHATGPT等のAI技術の発展と法務実務への影響
6月15日 生成AIと著作権をとことん議論
6月14日 日本は生成AIを起爆剤にできるのか?
6月14日 経済安全保障推進法に基づく「特許非公開」の対象
6月13日 CHATGPTの利用目的 米国ではアイディア生成用途でも
6月13日 イノベーション主導の成長と知的財産の役割の未来
6月12日 【CHATGPT】~知財業務を革新できる? CHATGPTの活用ポイントと留意点~
6月12日 AI活用によるSOCIETY 5.0 FOR SDGSの実現に向けて
6月11日 北海道大学がTHEインパクトランキングで4年連続国内1位
6月11日 デジタル化に伴うブランド・デザイン等の保護強化
6月10日 知財・無形資産の投資・活用促進メカニズムの強化
6月10日 AI 技術の進展を踏まえた発明の保護の在り方
6月 9日 「知的財産推進計画2023」決定
6月 9日 CHATGPTプラグイン、課題は開発よりも法務
6月 8日 特許文書読解アシスタント「サマリア」~人工知能技術の特許実務への活用・展望~
6月 8日 経済安保で政府の制度案まとまる 25分野「特許非公開」
6月 7日 欧州単一特許制度が開始
6月 7日 KDDIの知財戦略と知財KPI
6月 6日 文化庁が「AIと著作権」の無料セミナーをYOUTUBEライブで配信
6月 5日 生成AI、国内企業の参入
6月 5日 パナソニックグループにおけるCHATGPT活用状況
6月 4日 令和4年(行ケ)第10030号「積層体」事件 「除くクレーム」と訂正要件
6月 4日 「生成AIと著作権」に関する分かりやすい資料
6月 4日 AI に関する暫定的な論点整理
6月 2日 CHATGPTを活用した知財業務の革新
6月 1日 技術者向け知的財産教育
5月31日 ナブテスコの知財戦略と知財KPI
5月30日 令和4年(ネ)第10046号事件 知財高裁でのドワンゴ逆転勝訴
5月30日 ブリヂストンの知財戦略と知財KPI
5月29日 知財・無形資産 KPI の事例
5月28日 旭化成の知財戦略と知財KPI
5月27日 古河電工の知財KPI
5月26日 令和4年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書
5月25日 改訂CGCに対応した知財KPI、特に特許KPI
5月24日 非製造業はもっと無形資産のアピールを
5月24日 生成AIに関する実態調査2023(PWCコンサルティング)
5月23日 令和4年度ニーズ即応型技術動向調査結果
5月23日 CHATGPTの国内利用率
5月22日 事業会社とスタートアップのオープンイノベーション促進のためのマナーブック
5月22日 「AMGEN V. SANOFI」 機能的クレーム 米国最高裁判決
5月21日 医薬発明の用途限定に関する記載要件と訂正要件 令和2年(行ケ)第10135号
5月21日 化学・バイオの特許
5月20日 用途発明で差止請求認容 令和2(ワ)19221 「洗濯用洗浄補助用品及びこれを用いた洗濯方法」事件
5月20日 CHATGPT-4提案「マイクロ泡が泡立つ緑茶飲料」特許明細書案
5月19日 「それってパクリじゃないですか︖」第6話 大学との共同開発でトラブル
5月19日 AIの最新潮流2023~CHATGPTの衝撃 ~
5月18日 日本語をしっかり学習した大規模言語モデルの開発を期待
5月18日 ドワンゴ大合議判決を前に知っておくべき諸論点
5月17日 CHATGPT-4が提案した「緑茶飲料」開発のための新技術(3)
5月17日 日本語研究から見たCHATGPT
5月16日 食べログによるCHATGPTプラグイン開発の舞台裏
5月16日 日立製作所「GENERATIVE AIセンター」新設
5月15日 生成AIを活用した特許文書読解支援サービス「サマリア」
5月14日 知財経営の実践に向けた経営層と知財部門とのコミュニケーション
5月14日 AIを使った特許審査履歴分析
5月13日 CHATGPT-4が分析した緑茶飲料特許出願動向(2)
5月12日 CHATGPT-4が分析した緑茶飲料特許出願動向(1)
5月11日 CHATGPT-4が提案した「緑茶飲料」特許出願(4)
5月10日 CHATGPT-4が提案した「緑茶飲料」特許出願(3)
5月 9日 CHATGPT-4が提案した「緑茶飲料」特許出願(2)
5月 8日 特許文書品質特性モデル
5月 8日 CHATGPT-4が提案した「緑茶飲料」特許出願(1)
5月 7日 COHESIVE AI が作成した「日本の緑茶飲料市場のトレンドと今後の見通し」
5月 7日 CHATGPT-4が答えた「日本の緑茶飲料市場のトレンドと今後の見通し」
5月 7日 CHATGPT-4が提案した「緑茶飲料」開発のための新技術(2)
5月 6日 知財DXで日本の開発力を甦らせる
5月 6日 CHATGPT-4が提案した「緑茶飲料」開発のための新技術(1)
5月 6日 CHATGPT等の生成AIと特許情報解析ツール組合せによる競合調査
5月 5日 CHATGPT時代の営業
5月 5日 CHATGPT-4からの商品アイデアの提案
5月 4日 ヤッホーブルーイング、CHATGPT導入へ 開発・マーケなど検証
5月 4日 CHATGPT を商品開発に取り入れた創業116年の丸七製茶
5月 4日 特許スコアリング・レイティングの活用方法
5月 3日 JDLA「生成AIの利用ガイドライン」公開
5月 2日 スタートアップ経営者と知財をざっくばらんに語る
5月 1日 CHATGPTの活用を見据えたAIによる特許書類作成の戦略的な活用方法
4月30日 数値限定の「技術的意義」 令和3年(行ケ)第10135号
4月30日 CHATGPTなど生成AIの活用の仕方
4月29日 CHATGPT時代のAI講座
4月29日 チャットGPTは何が凄い?今後、何が起きる?
4月28日 CHATGPTなどの生成AIはビジネスの創造力をどう高めるか
4月27日 CHATGPT等の生成AIの驚異と脅威
4月26日 AIで特許業務を大幅効率化! 生成AIの活用範囲と今後の期待
4月26日 それってパクリじゃないですか? 第3話侵害予防調査
4月25日 CHATGPTによって描かれる未来とAI開発の変遷
4月25日 三井化学の生成AIとIBM WATSON融合による新規用途探索
4月24日 知財人材がスタートアップを加速する秘訣
4月24日 日本企業のPBR1倍割れ問題と知財・無形資産投資の重要性
4月23日 面接審査による特許査定率の増加
4月23日 GAFAMを除くと、日米の経済成長に大差はない?
4月22日 人工知能を利用した知財活用可能性分析の有効性に関する調査研究報告書
4月21日 知財経営の実践に向けたコミュニケーションガイドブック
4月21日 「空調服の空気排出口調整機構」事件 令和4年(行ケ)第10037号
4月20日 特許出願内容に関連した技術情報の秘密管理
4月19日 それってパクリじゃないですか? 4月19日第2話商標権
4月18日 【意匠法講義】出版記念セミナー(杉光一成先生)
4月17日 従来型の中期経営計画は廃止し、無形資産に投資する味の素の中期ASV経営
4月16日 用途発明、パラメータ発明からパブリック・ドメインを保護する先使用制度の現代的な意義
4月15日 イナズマメソッドで成功する事業承継
4月14日 日テレ水曜ドラマ「 それってパクリじゃないですか? 」
4月14日 カプコンが目指す次世代型知財部のあり方
4月13日 化学系特許調査と海外特許FTO/侵害予防調査セミナー動画
4月12日 知財ガバナンス革命(オンデマンド配信)
4月12日 アメリカ及び欧州連合における立体商標の保護
4月11日 【知的財産法を理解するための法学入門】出版記念セミナー
4月11日 商標の「藪」を乗り越える
4月10日 大学知財担当者から見た産学連携事業
4月 9日 オプジーボ関連特許訴訟で小野薬品工業、BMS社、ダナ・ファーバー癌研究所全面的和解
4月 8日 今後の裁判例が踏襲していくべき方向性を示した?用途発明に関する知財高判令和令和3(行ケ)10066
4月 7日 グローバル知財戦略フォーラム2023開催報告書
4月 6日 「コト」分野の発明発掘について
4月 5日 特許の質が低い企業ほど有価証券報告書での開示量が多い?
4月 4日 新規事項追加が争点の裁判例からみた発明発掘のポイント
4月 3日 知財実務家が考える発明発掘
4月 2日 企業における発明発掘活動の典型例(キヤノン)
4月 1日 大学知財ガバナンスガイドライン
3月31日 特許法を理解するためには法律の基礎知識が必要
3月31日 IP EPLATに「経営における知財戦略事例集についての全体概要紹介」がアップ
3月30日 パラメータ発明は活用したい
3月30日 当業者とは?
3月29日 数値等の重複を避けるだけの「除くクレーム」での対応を試みる価値はある
3月28日 企業が成長するための「知財・無形資産ガバナンスガイドライン)VER.2.0」とロゴマーク
3月28日 漏れのない権利を取得するテクニック
3月27日 IPランドスケープ推進協議会の9つの仮想IPL
3月26日 「審判実務者研究会報告書2022」が公表
3月25日 CHATGPTの知財実務への活用
3月25日 営業秘密侵害事件の増加
3月24日 情報提供制度をより活用するための提言
3月23日 CHATGPT-4で、AIの時代がまた変わった いまのタイミングは突っ込んでいった方がいい
3月22日 知的財産情報の開示 ブリヂストン、KDDI、ソフトバンク、富士通
3月21日 知財・無形資産投資の正統性
3月20日 用途発明の重要性
3月19日 阻害要因ありと進歩性が認められた令和3年(行ケ)第10165号「配送荷物保管装置」
3月18日 中小企業の未来をひらく「デザイン経営×知財」セミナー
3月18日 ふじのくにCNFフォーラム第10回セミナーの講演動画が公開
3月17日 セミナー「クレーム記載における「略(ほぼ)」の話」の録画無料公開
3月16日 特許製品を譲り渡した後も、特許権行使が可能にできないか
3月15日 経済的意義を有する特許価値指標YK値(工藤一郎弁理士講演資料)
3月14日 日本ペイントデータ流出事件の民事訴訟が和解
3月13日 権利者が分からない著作物の二次利用を促す著作権法改正案
3月12日 「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が閣議決定
3月11日 重要特許が企業の財務データに及ぼす影響
3月10日 知財・無形資産ガバナンスガイドラインVER2.0案の意見募集期間3月17日まで
3月10日 知財戦略カスケードダウンによるオープン・クローズ戦略の実例検討
3月 9日 新時代のスタンダードテキスト 知的財産法 第2版
3月 9日 発明の新規性理論の特許法29条の2の規定及び発明の進歩性への展開
3月 8日 クボタのスマート農業の競争優位性とその源泉を保護する特許戦略
3月 7日 「知財」がまるごとわかる 入門 知的財産法 第3版
3月 7日 明治グループのコア事業への注力と将来の成長ドライバーとなる事業の育成
3月 6日 セルロースナノファイバーの社会実装を進める先駆者たちの戦略
3月 6日 知的財産推進計画2023検討の視点(案)
3月 5日 国際シンポジウム「欧州の単一特許制度・統一特許裁判所の動向」
3月 4日 「リーガルテック展2023」のアーカイブ動画(村田製作所、ユーグレナなど)
3月 3日 第18回産業構造審議会知的財産分科会
3月 2日 欧州の単一特許制度・統一特許裁判所 オプトアウトが可能となるサンライズ期間が開始
3月 1日 単一の色彩のみからなる商標の登録のハードルは高い
2月28日 中国電力グループ「エネルギアグループ知的財産報告書(2023年2月)」
2月27日 日本企業のブランド価値
2月26日 「知財とパブリック・ドメイン」の第3巻「不正競争防止法・商標法篇」
2月25日 CLARIVATE TOP 100 グローバル・イノベーター 2023
2月25日 知財ガバナンス研究会有志 関東リアル研修会
2月24日 「つながる特許庁IN日立」アーカイブ動画
2月24日 日本企業と欧米企業にある「20年の差」 荏原製作所のDX
2月23日 強すぎる著作権の保護は行き過ぎると新たな創作活動を妨げる
2月22日 特許庁の審査の品質管理・品質向上に向けた方向性
2月21日 メタバース上のコンテンツ等をめぐる法的対応の動き
2月20日 海外サーバ問題(プログラムの提供、配信システム)~有体物の場合との対比
2月19日 パラメータ発明や内在同一の取り扱い(前田健 教授)
2月18日 オムロンのサステナビリティ経営
2月17日 ヤマハ発動機におけるデザインの利活用
2月17日 失敗するIPランドスケープ
2月16日 社会課題解決による企業価値向上への知財の役割
2月16日 収益機会のサステナビリティ指標としてIPランドスケープ実施率を設定している古河電工
2月15日 デジタル時代の知財経営戦略
2月14日 特許の出願の非公開に関する基本指針(案)がパブリックコメントに
2月13日 出願時の独立請求項
2月13日 “貿易立国”日本の苦闘 三菱電機経済安全保障統括室長密着取材等
2月12日 親子孫(三世代)分割出願戦略と留意点
2月11日 成功するIPランドスケープと失敗するIPランドスケープ
2月11日 社会課題への対応に向けたダイセルの知財戦略
2月10日 化学分野における特許出願戦略とAIの活用
2月 9日 パブリック・ドメインの醸成こそが,知的財産法の究極の目的
2月 8日 「特許」から組み立てるエアロネクストのドローンビジネス
2月 7日 化学分野における進歩性拒絶理由通知への日米の対応の違い
2月 7日 グローバル知財戦略フォーラム2023(2/17までアーカイブ配信中)
2月 6日 ビジネス関連発明における明細書作成ガイドライン
2月 5日 ソニー 知財が要 御供俊元氏が4月から副社長CSO
2月 4日 「特許出願の非公開制度」に関する基本指針案
2月 3日 「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会」(第19回)
2月 2日 プロダクト・バイ・プロセスクレーム明確性要件違反 令和3年(行ケ)第10140号 「電鋳管の製造方法及び電鋳管」事件
2月 1日 米国におけるパラメータ特許
1月31日 北大サマーセミナー2023
1月30日 改訂CGCに対応した知財KPIの策定と開示
1月29日 新規事業・用途開発段階での協業相手の選定を目的としたIPランドスケープの活用方法
1月28日 イノベーション創出に貢献する「架け橋」としての知財部門
1月27日 ブレインテックスタートアップ 株式会社CYBERNEXの価値創造、特許戦略
1月26日 早期審査の審査過程ではサポート要件違反が見過ごされやすい?
1月25日 メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題への対応
1月24日 知財・無形資産ガバナンスガイドラインVER.2
1月23日 スタートアップに投資を行う投資家向けの知財ホワイトペーパー
1月22日 コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー®2022
1月21日 石灰石を主原料とした新素材「LIMEX」で234億円の資金を調達 株式会社TBM
1月21日 作用効果のクレームアップ 令和3年(行ケ)第10090号「噴射製品および噴射方法」
1月19日 リコーにおけるIPランドスケープの取り組み
1月18日 進歩性に関する東北大学知財セミナー
1月17日 「略多角形」が不明確 令和4年(行ケ)第10019号「多角形断面線材用ダイス」事件
1月16日 均等論第2要件を認めた令和3年(ネ)第10040号「学習用具」事件
1月15日 チャイノベーション2023 コロナ禍でも研究開発の手緩めず
1月14日 グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方
1月13日 数値限定発明の公然実施による新規性欠如を認めた事例(東京地方裁判所:平成31年(ワ)第7038号及び第9618号)
1月12日 シンポジウム「音楽教室事件最高裁判決を語る」アーカイブ動画公開
1月12日 事業の優位確保から社会の課題解決へ転換する「パナソニック知財」
1月11日 出願発明が公知技術の上位概念又は同一概念=新規性否定の必要十分条件
1月10日 年報知的財産法2022-2023
1月 9日 著作権の潮流
1月 8日 増補改訂版 日米欧中対応PCT明細書作成のキーポイント
1月 7日 デザインと知的財産法実務─ブランドビジネスのための権利保護
1月 6日 無知財は無知罪
1月 5日 知的財産で社会を変える SSP−IPの挑戦
1月 4日 役員・経営者のための知的財産Q&A
1月 3日 「テプラ」成功の慢心が招いた地獄 特許侵害で100億円の請求
1月 2日 サステナビリティ実現に向けた国際知財戦略の在り方
1月 1日 特許出願技術動向調査 令和5年度調査予定テーマ
12月31日 競争力を高める特許リエゾン 改訂版
12月30日 独占禁止法上の「優越的地位の濫用」
12月29日 商標を活用したブランド戦略展開に向けた 商標制度の見直しについて(案)
12月28日 音楽教室事件最高裁判決
12月27日 公正取引委員会のスタートアップをめぐる取引に関する調査結果
12月26日 新しい時代における柔らかい標準
12月25日 大学知財ガバナンス
12月24日 知財訴訟の取り組み方
12月23日 「知財活用促進に向けた特許制度の在り方(案)」に対する意見募集
12月22日 クレーム用語の意義解釈
12月21日 「技術常識によれば当業者は認識」として用途発明の新規性を否定
12月20日 日本の特許分析と素材戦争 期間限定WEBINAR
12月19日 不確実な状況におけるPCT出願の価値
12月18日 知財戦略は発明起点から価値起点に変えることが大事
12月17日 競争力を高める化学・材料系特許明細書の書き方 改訂版
12月16日 「無形資産を巡らし、価値に変えて、世界を幸せにする」パナソニックグループの知財部門
12月15日 JAPAN BRANDING AWARDS2022 味の素と丸亀製麺が最高賞
12月14日 スタートアップ連携にかかるリコー、デンソーの事例
12月13日 知財・無形資産投資と指標(KPI)
12月12日 東京大学 知的財産報告書2022
12月11日 明治ホールディングス㈱)2022 年3月期の統合報告書
12月10日 第16回知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会
12月 9日 日立製作所の研究開発・知財戦略説明会アーカイブ動画
12月 8日 「知財・無形資産 経営者フォーラム」のスタート
12月 7日 日立製作所の研究開発・知財戦略説明会
12月 6日 進歩性判断では、非容易推考説に加えて、技術的貢献説の枠組みも重視すべき
12月 5日 令和 3 年度特許侵害訴訟における損害論等の概況(齋藤誠二郎弁護士)
12月 5日 令和 3 年特許侵害訴訟の裁判例における侵害論の概況(和田研史弁護士)
12月 4日 東芝テックと寺岡精工のセミセルフレジに関する特許訴訟における和解
12月 3日 名ばかりの「知財立国」
12月 2日 特許権侵害の紛争事例から学ぶ権利行使の実務
12月 1日 日本製鉄の「利益なき顧客至上主義」への戒め
11月30日 ビジネス関連発明の最近の動向について
11月29日 ブリヂストンの知財・無形資産投資の開示
11月28日 旭化成がAI特許調査プラットフォームAMPLIFIED を全社員に導入 事業発案を後押し
11月27日 シスメックスの研究開発・事業展開の自由度を確保する知的財産活動
11月26日 第 15 回知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会
11月25日 特許権を乱用した訴訟の増加がイノベーションを阻害
11月24日 特許スコアの活用に関する研究
11月23日 特許文書品質特性モデルの学習用テキスト
11月22日 SDGS 取組や知財 KPI 策定にも威力を発揮するIP ランドスケープ
11月21日 リコー対ディエスジャパン 再生トナーカートリッジ訴訟
11月20日 第14回知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会
11月19日 特許無効審判等の実務に役立つ記載要件のロジック
11月18日 特許情報をめぐる最新のトレンド
11月17日 新規事項追加の観点からの審査基準と裁判所の判断との乖離
11月16日 東芝テック 寺岡精工セミセルフレジに関する特許訴訟で特別損失
11月15日 旭化成グループにおける知財インテリジェンス活動
11月15日 JAPIO YEAR BOOK 2022
11月14日 EPOではどんな場合に実験データの追加が認められるか?
11月14日 アメリカ/EUにおけるプロダクトデザイン知財重複保護戦略
11月13日 経営・事業戦略と知財戦略の結節点
11月13日 ESG経営への知財活用 企業価値向上に向け
11月12日 特許情報解析の未来~解析技術、サービスはどう進化するのか~
11月11日 IPランドスケープ推進協議会 活動第2フェーズ
11月10日 AIと著作権
11月 9日 なぜ日本企業の知財・無形資産投資は消極的か
11月 8日 新たな模倣品対策
11月 7日 アメリカ/EUにおけるプロダクトデザイン知財重複保護戦略
11月 6日 日本からの新型コロナウイルス関連研究論文 主要7カ国で3年連続最下位
11月 5日 課題・作用効果をクレームに書けばサポート要件は満たされるのか?
11月 4日 知財部門がイノベーションを駆動できるのか
11月 3日 スマートシティにおける新技術の実装,新ビジネス,連携,データの取扱い
11月 2日 日本弁理士会中央知的財産研究所「第19回公開フォーラム」の講演録
11月 1日 俯瞰的で柔軟な知的財産マネジメントの高まり
10月31日 日本企業に対する投資家の企業価値評価が低い主因は説明不足にある。
10月30日 均等論(各要件と認容事例17件)
10月30日 弁護士・高石秀樹の特許チャンネル 近時の特許重要裁判例20選(2022年9月収録)
10月29日 日本の電機メーカーの失敗
10月28日 シスメックスの知的財産活動
10月27日 DXの欠如が品質不正の温床 三菱電機品質不正問題
10月26日 特許の現在地・高石秀樹弁護士
10月25日 音楽教室における著作物使用に関する最高裁判決
10月24日 積水ハウスの知財活動
10月23日 マッサージチェア特許訴訟(フジ医療器VSファミリーイナダ)
10月22日 JASRACと音楽教室の裁判、10月24日に最高裁で決着へ
10月21日 新しい技術・モダリティから強力な知財を創出するアステラス製薬
10月20日 投資家の目線からの知財投資・活用戦略の有効な開示
10月19日 金融庁が技術力や知的財産も担保にできる新法を検討
10月18日 丸井グループの無形資産投資
10月17日 東京海上ホールディングスにおける知財・無形資産の開示
10月16日 荏原製作所の技術人材の見える化
10月15日 味の素グループにおける無形資産を活かす価値創造の取組み
10月14日 令和4年度特許審査の質についてのユーザー評価調査報告書
10月13日 知財部署は社内のどこにでも潜んでいる スリーダムアライアンス
10月12日 知財は価値を生む「ウナギ屋秘伝のタレ」 ブリヂストン
10月11日 コーポレートガバナンス・コード改訂で変わりつつある知財戦略
10月10日 株式会社明治 特許、技術ノウハウ、商標の3つの観点からの知的財産マネジメント
10月 9日 DX時代における特許審査官とのコミュニケーション
10月 8日 ドワンゴ V. FC2事件控訴審 第三者意見募集制度
10月 7日 グローバル・イノベーション・インデックス (GII) 2022年版:日本は昨年に引き続き13位
10月 6日 営業秘密 不正競争防止法
10月 5日 発明ヒアリング
10月 4日 特許無効と特許権の安定性
10月 3日 特許「出願」価値の最大化戦略
10月 2日 サーチャー弁理士が語る特許調査のイロハ
10月 1日 IPデータ集 INTELLECTUAL PROPERTY DATA BOOK NO.13
9月30日 音楽教室における生徒の演奏 10月24日に最高裁判決
9月29日 弁理士サーチャーが明かす実務における特許調査の活かし方
9月28日 ダイキン工業テクノロジー・イノベーションセンターの目指すもの
9月27日 AVANCI の 4G ライセンス供与先が 80 を超える⾃動⾞ブランドに
9月26日 「稼ぐ力」「事業の差別化」のための特許を探す!
9月25日 特許を活用する! 特許の“現在地”
9月24日 改正意匠法に基づく新たな意匠権の動向
9月23日 低い技術的効果を狙った発明の方が権利が広くなり易い
9月22日 新しい査証制度―伝家の宝刀か、錆びた刀かー(令和元年特許法改正)
9月21日 特許調査における先行技術資料および無効資料の変化
9月20日 営業秘密侵害と差止請求
9月19日 特許評価・作成サービス WITH 知財訴訟費⽤保険
9月18日 エーザイで確立した「柳モデル」
9月17日 キリンホールディングス「プラズマ乳酸菌」
9月16日 石川県産高級ブドウ「ルビーロマン」
9月15日 中国は世界のイノベーションリーダー
9月14日 三菱電機「オープンテクノロジーバンク」の取り組み
9月13日 オムロン、旭化成の事例
9月12日 新型コロナウイルスのワクチン
9月11日 特許権存続期間の延長登録を巡る新たな論点
9月10日 個人使用目的で輸入される模倣品(偽ブランド)も10月から税関で没収
9月 9日 SX(サステナビリティトランスフォーメーション)
9月 8日 マッキンゼー 新規事業成功の原則 LEAP FOR GROWTH
9月 8日 旭化成 「特許価値」を投資家との対話に生かす
9月 7日 共同研究開発契約の法務
9月 7日 「100%メロンテイスト」が実はメロン2% 景品表示法違反
9月 6日 令和5年度 特許庁関係概算要求
9月 5日 バイオ医薬品の「特許の藪(やぶ)」
9月 4日 効力の範囲が「広すぎる」特許
9月 3日 ヒトではなく AI が特許を取る日 ~ 元米特許庁長官「国家安全保障上不可欠」
9月 2日 研究開発部門、知財部門の連携によるR&Dテーマの発掘
9月 1日 中間対応のマニアックな論点を実務家でとことん議論
8月31日 美容と健康と頭に良い紫式部ジャム。
8月30日 北大サマーセミナー2022(商標権、不正競争防止法)
8月29日 北大サマーセミナー2022(著作権)
8月28日 方法特許の消尽
8月27日 優越的地位の濫用及び下請法と知財契約
8月26日 特許権侵害と取締役の責任
8月25日 オムロンの「ROIC経営」「ROIC逆ツリー展開」
8月24日 マルチマルチクレーム制限が日本の審査実務および外国出願へ及ぼす影響と対応策
8月23日 後出の特許による既存事業の差止めは許されるか
8月22日 人工知能(AI)を活用した知的財産分野のサービス
8月21日 一次審査における新規性充足率が高い上位50社
8月20日 審査請求率が高い上位50社
8月19日 LIXILのグローバル事業戦略を支える「戦略組織」としての知財部門
8月18日 総合特許登録率が高い上位50社
8月17日 グローバル出願率が高い上位50社
8月16日 特許査定率が高い上位50社
8月15日 井関農機における知的財産権取得への取組
8月14日 先行技術に開示されていない構成 P(内在特性)の新規性
8月13日 知財実務オンライン:「明細書・意見書を書く人が絶対に読むべき書籍7選」
8月12日 外縁説という迷宮&数値限定発明の憂鬱(そーとく日記)
8月11日 科学技術指標 2022
8月10日 昭和電工はなぜ日立化成を買ったのか
8月 9日 無効審判等における「オンライン口頭審理」の運用開始後の実施状況について
8月 8日 東亞合成の知財・無形資産への投資
8月 7日 ホンダとソニーのEV連合
8月 6日 APPLE CAR
8月 5日 【GX技術:バイオ固体燃料】特許総合力トップ3
8月 4日 SUBARU知財部「技術者になれなかった」若手社員、挫折を糧につかんだ新たな夢
8月 3日 広報誌「とっきょ」メタバース特集
8月 2日 技術法務のススメ 第2版
8月 1日 昭和電工のSDGSへの取り組み
7月31日 アシックスの知的財産活動 ~ ブランド保護活動事例
7月30日 第一工業製薬(DKS)グループの価値創造プロセス
7月30日 「産学連携契約」―知的財産に関する課題とコーポレートガバナンス・コードの改定―
7月29日 特許行政年次報告書2022年版が公表
7月28日 KDDIが1位 オープンイノベーションに積極的な大企業
7月28日 「医療、ライフサイエンス、バイオの企業が知っておきたい 知財戦略と契約 BY IP BASE IN 神戸」の開催報告がアップ
7月27日 統合報告書に記載された知的財産に関する取り組み 中外製薬、デンソー、キヤノン、Z ホールディングス、東宝、昭和電工、荏原製作所、バンダイナムコホールディングス
7月26日 荏原製作所における知財価値評価とその活用
7月25日 経営目標への「非財務KPI」の導入 旭化成、三井化学
7月24日 後発でも勝てる特許出願と権利化戦略
7月23日 数値限定発明の憂鬱
7月22日 スタートアップ向け知財戦略と契約
7月21日 経済安全保障推進法「特定重要技術」の基本指針案
7月20日 キユーピーの社会的価値向上に向けた知的財産投資
7月19日 初めての口頭審理~初めてでも慌てないための実務的な留意点~
7月18日 日東電工の知的財産活動
7月17日 企業成熟度と技術競争力(YK値)とデフォルトリスク
7月16日 JPX400 のコーポレートガバナンス報告書での記載内容分析
7月15日 発明の課題や作用効果を参酌してクレームを限定解釈した事例
7月14日 数値限定発明に特有の問題について
7月13日 村田製作所の事業拡大を支える知財部門
7月12日 知財ガバナンスに関する企業の取組事例集(旭化成、味の素、伊藤忠商事、オムロン、キリンHD、東京海上HD、ナブテスコ、日立製作所、丸井グループ)
7月11日 改訂10版 化学・バイオ特許の出願戦略
7月10日 旭化成初の「知財戦略説明会」
7月 9日 「知財投資・活用戦略の有効な開示及び ガバナンスに関する検討会」 (第 11回)
7月 8日 弁理士のための特許調査の知識
7月 7日 三菱重工 知的財産
7月 6日 経済安全保障推進法案における特許非公開制度
7月 5日 進歩性判断における有利な効果
7月 4日 進歩性判断における示唆
7月 3日 進歩性判断における後知恵
7月 2日 キヤノンにおける発明発掘活動
7月 1日 特許庁政策推進懇談会「知財活用促進に向けた知的財産制度の在り方~とりまとめ~」
6月30日 進歩性判断における周知技術
6月29日 進歩性判断における設計事項
6月28日 帝人グループのイノベーション創出と知財インテリジェンス
6月27日 データビジネスの法律・知財・契約
6月26日 培養肉製造技術に見る、特許付与がイノベーションにもたらす影響
6月25日 共創を加速する知財戦略 ソニーの新素材プロジェクトを紐解く
6月24日 RWS SPECIAL SEMINAR 明日から使える 化学系特許調査のTIPS
6月24日 グリーン・トランスフォーメーション技術区分表(GXTI)
6月23日 IOT時代における特許権の消尽について
6月22日 進歩性の本質について 技術的貢献説の再生
6月21日 進歩性判断が甘いのではないかという声に対する特許庁の対応
6月20日 近年の日本の特許査定率の推移について
6月19日 東北大学知財セミナー 米国知的財産法の近時の動向
6月18日 企業価値(コア価値)を支えるIPランドスケープ
6月17日 マレリHDの経営再建、特許分析ではいばらの道
6月16日 特許判例の論点を実務家でとことん議論
6月15日 知財ミックスによるビジネスモデル保護の戦略
6月14日 弁護士高石秀樹の特許チャンネルで数値限定発明(統合版)アップ
6月13日 アナクア・オンラインセミナー:「知財・無形資産ガバナンスガイドライン」の動画
6月13日 DENBA JAPAN 株式会社(企業価値向上に資する知的財産活用事例集)
6月12日 調査分析のマニアックな論点
6月11日 知財実務に役立つマーケット情報の調べ方、知財情報のマーケティングでの使い方
6月10日 株式会社デンソー(企業価値向上に資する知的財産活用事例集)
6月 9日 意欲ある個人・プレイヤーが社会の知財・無形資産をフル活用できる経済社会への変革(知的財産推進計画2022)
6月 8日 投資家とのIP・無形資産コミュニケーション PATENTSIGHT SUMMIT 2022
6月 7日 これからの企業知財(DIC株式会社知的財産センター 小川 眞治氏)
6月 6日 株式会社LIXILの知財活動(PATENTSIGHT SUMMIT 2022)
6月 5日 株式会社村田製作所の知財活動(PATENTSIGHT SUMMIT 2022)
6月 4日 帝人株式会社の知財活動(PATENTSIGHT SUMMIT 2022)
6月 3日 旭化成IPランドスケープの新段階、知財インテリジェンス室の創設
6月 2日 ソフトバンク株式会社(企業価値向上に資する知的財産活用事例集)
6月 1日 特許庁における人工知能(AI)技術の活用に向けたアクション・プラン(令和4~8年度版)
5月31日 新たな段階に入ったマーケティングと融合する貝印の知財活動
5月30日 ソニーグループ株式会社(企業価値向上に資する知的財産活用事例集)
5月29日 「知財・無形資産ガバナンスガイドライン」の理解を深める
5月28日 知財実務オンライン「訴訟と外国出願に耐え得る明細書作成の基礎」
5月27日 知的財産権の保護とデータ活用AOS 2022 MAY
5月26日 株式会社 ゼンリン(企業価値向上に資する知的財産活用事例集)
5月25日 NHKアカデミア 第1回 <生命科学者・山中伸弥>
5月24日 株式会社 スノーピーク(企業価値向上に資する知的財産活用事例集)
5月23日 株式会社 五合(企業価値向上に資する知的財産活用事例集)
5月22日 発明の効果のクレームアップ(進歩性)
5月21日 KDDI 株式会社(企業価値向上に資する知的財産活用事例集)
5月20日 GROOVE X 株式会社(企業価値向上に資する知的財産活用事例集)
5月19日 味の素株式会社(企業価値向上に資する知的財産活用事例集から)
5月18日 最速3分特許出願書類を作る、AIによる「特許文書作成支援」
5月17日 キリンとサントリー、糖質ゼロビールの特許でクロスライセンス契約締結
5月16日 試される知財部。(企業法務戦士の雑感 ~SEASON2~)
5月15日 企業価値向上に資する知的財産活用事例集―無形資産を活用した経営戦略の実践に向けてー
5月14日 中小企業 ベンチャー スタートアップの知財担当者のための知財戦略ガイド
5月13日 第6次知財ブーム コーポレートガバナンス・コード改訂で経営層に火が付く
5月12日 無効審判実務に役立つ進歩性ロジックの検討
5月11日 数値限定発明の進歩性に関する審査基準と裁判所の考え方の乖離
5月10日 進歩性の観点からの審査基準と裁判所の判断との乖離についての検討
5月 9日 アシックスの中国における商標武装した模倣品との闘い
5月 8日 開示で投資家の評価仰ぐ
5月 7日 社外に切り出し事業化も
5月 6日 技術もブランドもアピール ホンダ
5月 5日 「経営判断の重要なツール」旭化成会長 小堀秀毅氏
5月 4日 日経新聞 複眼「知財・無形資産 生かすには」
5月 3日 北海道大学が「THEインパクトランキング2022」で総合ランキング世界10位(国内1位)にランクイン
5月 2日 特許「出願」の価値を「オプション権」と捉えた最大化戦略
5月 1日 知財紛争をめぐる産学連携研究の課題 オプジーボ訴訟
4月30日 SDGSと価値創造~探究の入口~(授業で使える知財創造教育コンテンツ)
4月29日 第92回知財実務オンライン:「遂に始まる欧州単一特許パッケージ」
4月28日 「世界知的財産の日記念オンラインイベント」の無料動画配信
4月27日 弁護士高石秀樹の特許チャンネル【特許】数値限定発明(統合版)
4月26日 グローバル知財戦略フォーラム2022開催報告書
4月25日 特許面接審査を活用した広い権利範囲の取得
4月24日 弁理士業務と AI 特許作成
4月23日 特許庁業務における人工知能技術の活用
4月22日 知財担当のための特許情報を用いた俯瞰分析〜競合調査・分析/報告資料の作成方法について〜
4月21日 特許「出願」価値の最大化戦略《5分短縮版》高石秀樹弁護士
4月20日 「特許情報に基づく特許価値の分析と検証に関する調査研究」報告書
4月19日 知財の目線で事業計画に向き合う!経営者との対話術
4月18日 社会価値創造型企業として「未来の共感」を創る日本電気の知財活動
4月17日 知財は企業の競争力強化の一手段 これからの知財部門には戦略提案力が求められる
4月16日 ここがすごいぞ!日本の十大発明家
4月15日 知財実務オンライン:「イノベーションに資する知的財産制度の意義とWIPOの役割」
4月14日 特許明細書作成のマニアックな論点
4月13日 コーポレートガバナンス・コードに基づく知財戦略の戦略的開示
4月12日 アシックスの知財戦略の推進と知財戦略委員会の設立
4月11日 コニカミノルタの事業ポートフォリオ転換を支える知財戦略
4月10日 用途発明のクレーム解釈と差止請求の可否及び損害賠償の範囲
4月 9日 「知っておきたい特許契約の基礎知識」が12年ぶりに改訂
4月 8日 知的財産に関する情報開⽰の際のKPI (重要業績評価指標)の例としての中核特許
4月 7日 知的財産に関する情報開⽰の際のKPI (重要業績評価指標)の例としての重要特許
4月 6日 「知財・無形資産ガバナンスガイドライン」を踏まえた具体的なアクションプラン
4月 5日 特許審査において面接・応対を行うことによる効果の分析
4月 4日 日本マルチマルチクレーム禁止による外国出願への影響
4月 3日 ロシアが「並行輸入」を認可 世界的ブランドの販売停止に対応
4月 2日 三極知財・環境問題シンポジウムの結果について
4月 1日 経済産業省が「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」策定
3月31日 審判実務者研究会報告書2021の公表
3月30日 パナソニックのOKRによる知的財産活動のマネジメント
3月29日 SDGS,ESGをめぐる世界の情勢からみるESG投資を呼び込む知財活用・知財戦略
3月28日 知的財産をめぐる今後の取締役会のあり方
3月27日 ガイドラインに基づく「知財・無形資産ガバナンス」の実践方法
3月26日 知財投資等に関する情報開示の具体的対応
3月25日 知財・無形資産の投資・活用における「開示」と「ガバナンス構築」のすすめ方
3月24日 マルチマルチクレーム制限に伴う特許・実用新案審査基準の改訂
3月23日 知的財産戦略のプレゼンテクニック(本田技研 別所氏)
3月22日 拒絶査定不服審判
3月21日 特許異議申立制度の利用
3月20日 情報提供制度の利用
3月19日 営業秘密漏えい事件 元専務らに無罪判決 名古屋地裁
3月18日 面接審査の活用
3月17日 早期審査請求の利用割合
3月16日 優れたコーポレート・ガバナンス報告書
3月15日 中国電力株式会社コーポレートガバナンス報告書
3月14日 除くクレーム
3月13日 マルチマルチクレームの制限への対応について
3月12日 味の素、アメリカでの特許権侵害訴訟で韓国企業と和解
3月11日 住友商事株式会社コーポレートガバナンス報告書
3月10日 積水ハウス株式会社コーポレートガバナンス報告書
3月 9日 改訂コーポレートガバナンス・コードへの対応・事例(住友商事、積水ハウス)
3月 8日 令和3年の税関における知的財産侵害物品の差止状況
3月 7日 特許検索手法の見直し~短時間でそれらしい特許をみつける手順~
3月 6日 IP BASEチャンネル よくわかるIPランドスケープ!
3月 5日 「知的財産推進計画 2022」の策定に向けた意見募集
3月 4日 第17回産業構造審議会知的財産分科会
3月 3日 AI SAMURAIによる「AI特許作成」システムは「適法」
3月 2日 月刊パテント2022年1月号の進歩性特集
3月 1日 WITH· AFTERコロナで生まれた新しい潜在・将来ニーズの発掘と新製品開発への応用
2月28日 マルチマルチクレームの制限
2月27日 株式会社アクセルスペース「超小型衛星ビジネスの発展とそれに伴う知財意識の変化」
2月26日 コーポレートガバナンス・コード改訂を踏まえたESG時代の企業価値向上における知財情報活用
2月25日 Zホールディングス/ヤフーの知的財産活動
2月24日 ニデックの知的財産活動
2月22日 キーエンスの稼ぐ力、成長力
2月21日 特許情報をめぐる最新のトレンド(コーポレートガバナンス・コード、IPランドスケープ、ESG · SDGS)
2月20日 「人間知能」主導によるAIの特許調査への応用
2月19日 コーポレートガバナンスコードへの対応と、事業保護と特許収入増の両方を達成する知財戦略
2月18日 デジタル知財時代 ブロックチェーン、NFT、そして特許NFT
2月17日 味の素のIPランドスケープとCGC改定対応
2月17日 富士通のIPランドスケープ
2月16日 パナソニックの伴走型IPランドスケープ
2月16日 KDDIのIPランドスケープ(「フォアキャストIPL」と「バックキャストIPL」)
2月15日 知財ガバナンス時代におけるナブテスコの知財活動
2月14日 企業価値創造へ向けて知財をどう活用するか(一橋大学伊藤邦雄名誉教授)
2月13日 DX専門組織をつくったユニ・チャームの知財本部
2月12日 マルチマルチクレーム制限に関する特許・実用新案審査基準改訂案
2月11日 2022年の知的財産法分野の動向 – CGコード対応、特許法、意匠法、商標法、注目訴訟
2月10日 アシックスが牛に靴を売る?スポーツメーカーの強みを活かす新戦略
2月 9日 株価上昇率で「グーグル超え」のダイキン
2月 8日 プラスチック資源循環技術
2月 7日 2021特許・情報フェア&コンファレンス「オンライン展示会」
2月 6日 新型コロナワクチン
2月 5日 2021年度『産学連携学会シンポジウム』
2月 4日 AI SAMURAI新機能「AI特許作成」
2月 3日 令和2年の審決取消訴訟の概況
2月 2日 裁判を通じて伝えたかった本庶氏の「次世代研究者への思い」
2月 1日 第4世代AI技術動向調査
1月31日 コーポレートガバナンス・コードへの対応状況
1月30日 「柿の種」パッケージで亀田製菓と久慈食品が和解
1月29日 ユニ・チャームの知財戦略
1月28日 知財・無形資産ガバナンスガイドライン)VER1.0の策定
1月27日 『冷凍餃子の特許合戦!』味の素と大阪王将
1月26日 論点別・特許裁判例事典「第3版」 出版記念セミナー
1月25日 「ナノセルロース特許入門」オンラインセミナー
1月24日 ファストリテイリングとアスタリスクの和解
1月23日 共同発明における発明者性の判断基準
1月22日 コーポレートガバナンス・コードと知的財産 IPジャーナル9月号論文
1月21日 アシックス「王者奪還」への執念「Cプロジェクト」
1月20日 特許情報のマーケティング活用
1月19日 「つながる特許庁 IN 長岡」アーカイブ動画
1月18日 経営トップは無形資産に定見を、ゲームチェンジ仕掛けろ
1月17日 大学における産学連携活動の実態 ~企業出身の知財専門家の目線から~
1月16日 実務家のための知的財産権判例70選
1月15日 「言ったもん負け」の縦割り文化を「知財」を武器に打破する三菱電機
1月14日 医薬・バイオ分野の知財戦略
1月13日 アイシンの知的財産活動
1月12日 コーポレートガバナンス・コード改訂に伴う知的財産に関する KPI 等の設定(中間報告)
1月11日 論点別特許裁判例事典 第三版
1月11日 技術者・研究者のための 特許の知識と実務[第4版]
1月10日 2022年・第20回「このミステリーがすごい! 大賞」大賞受賞作 特許やぶりの女王 弁理士・大鳳未来
1月 9日 持続的価値創造のための知的財産ガバナンス
1月 8日 初学者向け 知的財産のリスクマネジメントとトラブル対応の実務
1月 7日 特許権侵害訴訟において公然実施による特許無効の抗弁を主張する際の留意点
1月 6日 公然実施発明に基づく進歩性欠如の特許無効を争う裁判例
1月 5日 化学分野における公然実施製品と他者登録特許
1月 4日 公用発明(公然実施発明)と進歩性について
1月 3日 公然実施発明に基づく新規性、進歩性判断
12月31日 今年の知財ニュースランキング
12月31日 再公表特許の廃止に伴う留意点
12月28日 日本製鉄が特許侵害でトヨタに続き三井物産も提訴
12月27日 ユニクロのセルフレジ訴訟の和解
12月26日 「勝つ」より妥当な「解決」
12月25日 大野聖二弁護士「戦略的特許侵害訴訟を目指して-担当した最高裁判決、知財高裁大合議判決を振り返って-」
12月24日 高石秀樹弁護士の「特許出願戦略(当初明細書の記載とクレーム文言の工夫<10選>)」
12月23日 5つのプリンシプル(原則)と7つのアクション
12月22日 IPランドスケープに関する研究─初めて取り組む方への手引き─
12月21日 バイオナノマテリアルシンポジウム2021- アカデミアからの発信 –
12月20日 「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン(案)」に係る意見募集
12月18日 知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会(第9回)
12月17日 マルチマルチクレーム制限の例外は設けない
12月16日 ナブテスコにおける知財・無形資産の投資・活用戦略
12月15日 審判の最新状況
12月14日 マルチマルチクレーム制限について
12月13日 知財担当者になったら読むべき本 第2版
12月12日 サステナビリティ・ガバナンス改革
12月11日 発明者認定基準 日米比較・紛争回避対策
12月10日 新規ビジネスのための事業戦略と知財戦略
12月 9日 壮麗な装丁と「知的財産権の紋章」が特長の本「世界の知的財産権」
12月 8日 トヨタの知財活動と経営・事業に資する知財情報の活用に向けての特許庁の取組み
12月 7日 横